|
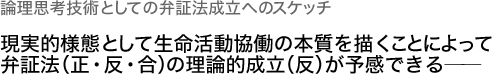
論理思考への関心が高まっている。
論理思考の百花繚乱である。論理思考には、その土台となる思想や理論など哲学が必要だと思う。哲学をもった論理が少ない。
本投稿は、イントラネットの電子オフィス、平成17年3月20日 電子掲示板「営業情報」への投稿を修正して、本文を作成しました。みなさんは、平成17年1月28日〜2月9日に社内学習情報として「本局発表」に投稿した日本経済新聞の 野中郁次郎先生「知識社会と企業」なども参考されて、論理思考について更に学習を進めてください。

(親、兄弟、姉妹や村社会の共同体との交通、そして交換)
きょうはきのうの続き。そして、そこから生きていく夢と希望の未来への志向。
「現実を否定」して、「現実的」に生きる。きのうの続きの行為ではなく、「実践」を目指す。
「相手を批評しつつ、自分をも批評している。
ある集中が、確実におこなわれていて同時に、その集中によってもっていかれそうになる自分を引き離すような、ある拮抗する力がはたらく。集中という形で、表現の領域へ没入する自分と、それを対象化し批評する自分の精神と身体とが同時に成立している。
ここに全的な共感がワープロ画面に対象化――自分の考えや労働が外化(自分の外で、形になること)され協働という形で「共有」されるのです。生命活動の協働たる生産物――トランスクリプションは本来なら、この証明により、翻案権が成立するはずです」(ホームページ「事業領域 トランスクライバーの心象風景から」)
現実を否定して現実的に生きることの意味である。
そして、「人間社会」(人類)に生きているのではなく、「人間社会史(人類史)」的に生きている。
わが国の保守派は、現代によみがえる歴史観(歴史認識)の武装が必要で、歴史観を周辺諸国民族との対等に尊厳し合う歴史認識や政治や経済が、政治政策などの結果、わが国社会の未来へ鏡映している諸問題の歴史的展望などが欠落していると感じます。
「新しい歴史教科書をつくる会」の事務局が本郷にあった頃から、いく度かの録音スタンバイなども通じて、編集支援ディクテ原稿の制作を続けてきました。
なぜいま「歴史教科書なのか?」、その求められる意味のお仕事だと自覚してきました。そして、歴史教科書や書籍にもなりましたが……。
(わたしの現実的な生命(いのち)の過程は、弁証法の「(正)現実的、歴史的本質」へと発展させる)
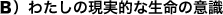
「外からの意識の注入」によってのみ意識という自己精神は変革される。
「稽古の精神」(森本哲郎先生)と「学習の姿勢」、勉強や練習などの重視。
「基本はいつもものまね上手」(石井威望先生)、「守・破・離」へ。
(PHP研究所『THE21』バックナンバー参照)
事例研究、研修、訓練。学校(教育)制度の重要な意味。
「やりたい仕事、なりたい自分」を目指す意識。
(わたしの現実的な生命意識は、弁証法の「(反)理論的本質」へと発展させる)
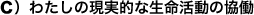
アウフヘーベン(止揚)された未来志向。
行為は協働へ
協働(労働過程・仕事)への実践(止揚(目的)された行為)
考えることを考える。
実践の土台には、行為の「哲学」がある。努力による能力の開発ばかりでなく、自己を超えて更に自己変革へ、そしてそれは「生命活動協働の場」におけるサーカマスタンス(circumstance 周囲の情況)と共にある。
たとえば、中東におけるイスラエルとパレスチナのサーカマスタンス。北方4島のロシアとのサーカマスタンス。最近では、竹島の韓国とのサーカマスタンス――de facto。
生命活動の「現実的な場」に「個」は立つ(アウフヘーベンする)。
ここから弁証法成立へと発展・止揚(アウフヘーベン)される。
(わたしの現実的な生命活動の協働は、弁証法の「(合)実践的本質」へと発展させる)
以上を、現実的様態と考え、類的(社会的)行為(協働社会)を抽象する。
思考構造はアウフヘーベンしていくので、次の発展へと自己精神は成長する。
(ホームページ「会社経営理念 2005年」から)
弁証法は、唯物弁証法ではない。そんなものはない。「正・反・合」といわれている。
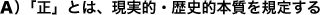
過去の歴史はどうだったのか? 現実はどうなっているのか。ぼくたちがものを考えていくにあたって、過去と現実を知らねばならない。ここでは現実と、その歴史的把握を行う。政府審議会や会社の会議などでも現実について論証しなければならない。現状分析(心情や感情)も大事だが、今日的な「歴史的」視座を強調しておく。
「いま、こうなっているよ」とシャガールの絵は語る。

理論的に「あるべき、望ましい姿」を論証する
本来は、「こういうのがあるべき姿だよ」と論証する。
P.F.ドラッカー先生は「学者や知識人は、政治、社会、経済、心理は理論から生まれると言う。もちろん、そういうこともある。だが滅多にはない。理論が現実に先行することはない。理論の役割は現実を組み立てることにある」と。
私鉄沿線の都市計画という理論と「現実」は、理論が「現実」を生み出した、と見るべきか? もちろん、そういうこともある。
理論的な論究など行い、「どうあるべきだったか」について述べる。
「こうしたほうが望ましいよ」「こうやって生きていけよ」とシャガールの絵は語る。

最高の方針を政治方針や経営方針にまで高め、いかに対策をとったか、その解決策と「行為」(実践)がひとつになる。
「こうしよう」「これを守って暮らしていけよ」とシャガールの絵は教える。
(テルアビブの美術館に門外不出のシャガールの三部作がある。絵画はユダヤ人に教える遺言である)
(ホームページ「会社概要 経営理念」の2005年に弁証法の枠組を一筆しましたのでご参考され、そこへ連結していく思考の土台がこれです)
(これは、平成17年3月24日「本局発表」に投稿されたものです)

本稿は、採用時に送られる書類の三部作の一つです。
ひとつは、『よみがえれ「稽古の精神」』、もうひとつは、『基本はいつも「ものまね上手」』と、平櫛田中先生の「尋牛」(じんぎゅう)の写真とともに送っていました。
自己実現への道は、尋牛の道でもあります。それは同化模倣の道です。
上記の本文とともに、お読みいただければと思います。
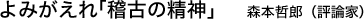

勤勉さ・几帳面さ・礼儀正しさ……。
長く日本人を特徴づけてきたこれらの美徳が、
近年、急速に影を潜めつつある。
無原則に新しきもののみを追いかけてきたツケが回ったのだ。
私たちは今こそ、古きに学んで新たな創造を求める
「稽古の精神」を取り戻さねばならない。
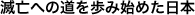
現在の日本が置かれている状況を一言で言うなら、「流行が不易を侵食している」ということではないでしょうか。「流行」とは、時代とともに変わりゆくもの、「不易」とは、いつの世にも変わらないものを意味します。「流行が不易を侵食している」とは、科学技術の進歩によって、誰もが新しいものに価値を見出すようになり、時代を超えて持ち続けてきた民族固有の伝統、特質といったものが失われつつある、という意味です。
たとえば日本人の美徳と言われてきた勤勉さ・几帳面さ、礼節といったものが、最近ではすっかり影を潜めてしまいました。日本的なるものが、音を立てて崩壊していると言えるでしょう。
世の中には、逆に、一部のイスラムやヒンズーのように「不易」の部分だけに固執する、原理主義を主張する勢力もあります。しかし世界全体の流れは、確実に「流行」に押し流されています。世界のそこここで民族固有の伝統や特質が失われつつある。「流行が不易を侵食している」のは、何も日本に限ったことではありません。
コンピューター社会の到来が、新しいものだけに価値を見出す風潮を生み、この流れを加速させています。コンピューターは、本来、人間の道具(手段)であるはずです。ところが今はコンピューターを操作すること自体が目的になっている。コンピューターの普及に伴い、全世界から「何のために」という根本的な目的意識が欠落しつつあるのです。これは地球規模の危機到来と考えてよいのではないでしょうか。その危機に最先端でさらされているのが、残念ながら日本なのです。
一九八九年前後から、日本でバブルが崩壊しました。このバブル崩壊は、もちろん経済現象なのですが、それだけではありません。戦後五〇年間、わずかながらも日本の社会が持ち続けてきた旧来の価値が完全に崩れ去ったのです。
バブル崩壊の前にあったのは、高度経済成長が生み出した「豊かな社会」でした。その「豊かな社会」が何を生んだかと言えば、?無秩序?です。新聞を賑わしている住専の問題が、融資の無秩序から生まれたことを考えれば、おわかりいただけるでしょう。「貧すれば鈍す」と言われますが、実際にはその逆で「富すれば鈍す」です。「衣食たりて礼節を知る」と言いますが、これも逆で、衣食たりているときに礼節を守るのはたいへん難しい。最近はマナーを守らない人ばかりで、町を歩くのがいやになるほどです。こういったモラルの喪失、無秩序は、国を衰亡に追いやり、やがて滅亡に導きます。日本は今、滅亡するか、繁栄を取り戻すか、の岐路から、滅亡への第一歩を踏み出そうとしているように思えてなりません。
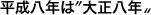
現在日本が置かれている状況を見定め、今、何をすべきかを見極めるために、歴史を振り返ってみましょう。
私は明治期と戦後をパラレルに捉えています。明治時代は四五年間でしたが、昭和二〇年の敗戦から昭和が終わるまで、ちょうど四五年でした。明治の四五年間で日本は「近代化」に成功し、戦後の四五年間で「現代化」に成功したのです。
明治の近代化は、福沢諭吉、西周、新渡戸稲造などがリーダーとなって推し進めました。ヨーロッパの合理主義を導入した彼らは、一見、古い価値観をすべて捨てたように見えるかもしれません。しかし、彼らが目指したのは「和魂洋才」で、日本古来のエートス(精神)を持ちながら、合理主義のよい面だけを取り入れていきました。だからこそ日本の近代化は成功したのです。
戦後の日本にも、吉田茂、池田勇人などのリーダーが出て、現代化に取り組みました。明治と戦後で一つだけ違うのは、明治期の変革が日本人自らの手で行なわれたのに対し、戦後はアメリカの占領下で行なわれた点でしょう。戦後はアメリカが絶対で、日本の古きものはすべて悪、という風潮が生まれました。それでも豊かな社会を築き上げることができたのは、日本人の血のなかに、まだ古来の価値観が残っていて、それが無意識のうちに作用したからだと、私は思っています。
さて、明治時代の後には大正時代が一五年続きますが、この大正期は、まさに平成期とパラレルにふりかえることができます。平成八年は、大正八年と同じ状況下に置かれているのです。
大正期には、大正デモクラシーという大きなうねりが起こりました。それと同時に、あまりに性急な近代化をはかった明治という時代を反省し、日本のアイデンティティーの模索がなされています。
飜って平成期を見てみますと、戦後の現代化に対する反省が全くなされていません。日本古来の価値観に対する否定が強すぎたためですが、かといって日本がアメリカの民主主義を真に理解しているとも思えない。日本は表面的には民主主義を取り込みましたが、それも本当には、日本人の血肉となっていないのが実情です。
急速な現代化によって、伝統的なものへの尊重の念もなく、かといって新しく取り込んだものの完全な消化もできていない。この現状からアナーキーな状態、無秩序が生まれたと思われます。
大正期に生まれたデモクラシーの波は、昭和初期に起こった大恐慌、軍閥の抬頭によって打ち砕かれ、日本はファシズムの時代へと移行していきました。歴史の流れと照らし合わせて考えますと、平成八年の今、我々は豊かな社会に浮かれたツケを払わされていますが、日本人はこの時期に、依然として、過去への反省もないままに時を過ごしている。このままでは、かつてファシズムが抬頭したように、歴史の流れに翻弄される危険が多分にありましょう。
同じ轍を踏まないためには、ここ四〜五年をどう過ごすかが問題です。今がまさに、日本にとっての正念場なのです。明治・大正の歴史が鳴らしている警鐘に、今こそ、耳を傾けねばなりません。
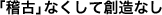
日本の社会が、これほどまでに精神の秩序を崩壊させてしまったのは、戦後の教育によるところが非常に大きいと思います。日本の子供に必要なのは創造性であり、それを育てるためには古い日本的なモラルを否定し、「自由」にさせなければいけない、といった単純な思い込みに基づく教育が繰り返された結果、現在の無秩序が生まれたのです。
この無秩序状態から脱却するために、私は新しい価値観、モラルの樹立を早急に進める必要があると考えます。現代という時代に合った新しい行動規範づくりに、一刻も早く真剣に取り組まなければなりません。
秩序をつくり出すには、それを支えるエートスが必要です。つまり信念、確信、理念といったものが求められる。私はこれからの日本をつくるエートスの中心に据えられるのは、「サムライの精神」だと思っています。
「サムライの精神」、すなわち「武士道」などというと、封建主義の遺物のように考える人がいるかもしれません。しかし、「武士道」とは、そんな因循姑息なものではありません。詳しくは、新渡戸稲造の『武士道』を読んでみてください。温故知新と言いますが、新しい時代へのヒントこそ、じつは古きもののなかにあるものなのです。
そこで「武士道の精神」について、私なりにもう少し掘り下げてみたいと思います。江戸時代の儒学者・太宰春台は、「武士道の精神」の本質は「礼」にあると言っています。「礼」とは「道」より生まれるもので、「礼」を失ったときに日本は滅びる、と。
「道」とは何かと言われても、わかりにくいと思いますので、武道、茶道、書道などの芸事を思い浮かべてみてください。「道」を極めるために、春台はまず、形、つまり作法から入ることをすすめています。決められた礼儀作法を守ることにより、「道」に行きつける。長い歴史がつくりあげた「型」を守るということは、文化を守るということであり、日本古来の文化は「型」のなかに結晶している、と言えるのです。
こういった文化を受け継ぐには、「稽古」が必要です。芸事を習得するには稽古をしますが、稽古の「稽」とは「考える」ということ、「古」は過去から受けつがれてきた形を意味します。つまり先人がやってきたこと、師匠の提示するものをよく考え、まねるのが稽古というわけです。
よく人のまねはいけない、と言われますが、学習とは模倣から始まるのです。完全にまねができるようになって、はじめて先生に追いつくことができ、先生を超えることができる。あの天才的な音楽家ベートーヴェンでさえ、モーツァルトの模倣から始めているのです。
先生と同じことができるようになれば、免許皆伝となります。しかし問題はそれからです。きっちり師匠のまねができるようになってから、はじめて創造の世界に踏み込んでいける。模倣の繰り返しから創造が生まれるのです。
ところが日本人は、戦後、先達をまねることをすべて否定してしまいました。「稽古の精神」を失ってしまったのです。過去を弊履(破れたクツ)のように捨て去るところには、何も生まれません。私は、日本の発展を支えてきた「稽古の精神」を失ったところに、今日の混迷の原因がある、と思うのです。そこで、「稽古の精神」を取り戻すこと、それを私は主張したい。それによって、日本人ならではの美徳と言われてきた勤勉さ、几帳面さを取り戻せるにちがいないからです。
日本人にそのような美徳を植えつけた要素はいろいろ考えられます。稲作民族であったということも大きいでしょう。なぜなら亜熱帯の稲を日本でつくるには、勤勉さ・几帳面さが要求されるからです。日本人の美徳をつちかったのは、営々とつづけてきた稲作への取り組みだと思います。
それは、まさしく「稽古の精神」にほかなりません。伝統という「不易」に立ち、創造という「流行」を求める「稽古の精神」を取り戻さないかぎり、社会の秩序をつくる「礼」はよみがえらず、日本人はエートスを失ったまま、さ迷い歩くことになる。私は、こうした「稽古の精神」を取り戻さないかぎり、日本に未来はないと思います。(談)
(PHP研究所 月刊誌『THE21』平成8年に掲載、PHP研究所『THE21』編集部編集長 山岡 勇二様よりホームページ掲載のご許可をいただきました)

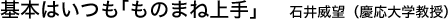

戦後、目覚ましい経済発展を遂げてきた日本だが、
海外からは、「ものまね上手」と批判されてきた。
奈良の大仏の時代から、戦国時代における鉄砲、
明治の文明開化と発揮され続けてきたこの特質を、
マルチメディアの時代へと歴史が変わりつつある今、
どのように活かしていくべきなのであろうか……。
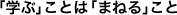
一九六〇年代の中頃、ヨーロッパの街角で日本車が一台走っているのを初めて見たとき、涙が出るほど感激したことを覚えています。今、次々に工業化に成功しているアジア各国の人々も、恐らく同じ感動を体験しているのではあるまいかと推察します。
六〇年代中頃の日本の工業製品は、性能面でも機能面でもかなりお粗末で、欧米に対抗できるのは価格だけといわれていました。車も例外ではなく、ドイツのアウトバーンをフルスピードで走ることができるかと心配になるほどでした。それから三〇年を経て、今や「メイド・イン・ジャパン」といえば、性能の良さ、信頼性の高さの代名詞にさえなっています。
技術後進国であった日本は、戦後、欧米に追いつこうと懸命にまねをし、わずか三〇年そこそこで追いついたのです。しかしその結果、日本人は「ものまね上手」であると評価されるようになりました。――ものまね上手なだけで、何一つ自分たちで考え出さない国民であり、「独創性」がまったくないと繰り返し批判されるうちに、それがわれわれのコンプレックスにまでなってしまったのではないでしょうか。
ところが、歴史をひもといてみますと、かつて日本人は「ものまね」に対して、それほどコンプレックスを抱いてはいませんでした。
たとえば、職人の世界に代表されるような技術の現場では、昔から必ずグループで仕事をしてきました。そこでは、一人が何か新しい技術をマスターするとみんながまねをしますし、教える際にも、手取り足取り教えるのではなく、「慣れろ」とか「盗め」といいました。つまり、「学ぶ」ことは、徹底して「まねる」ことだったのです。
芸事などでも、古くから「守・破・離」という一つの発展段階説があります。まず伝統的な古いやり方を、どんなことでも変えないで徹底的に学ぶ(「守」)。そして基本技術を十分にマスターしたうえで、次の段階として、古い伝統的なものを「破」り、やがては学んだものとはまったく違った、新しい独創的な方式を確立し(「離」)、新たな流派を形成(「立派」)していったのです。
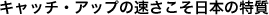
このように、独創性を発揮する大前提にあるのは、徹底して「まねる」=「学ぶ」姿勢であることを、日本人は古くから当然のこととしてきました。
ところが、それを「ものまね」=「独創性のなさ」と勘違いするようになったのは、「破」とか「離」が明確にされていないからです。
そこで、「独創性」と「ものまね上手」について、もう一度考えてみましょう。
まず「独創性」ですが、これは時間軸のうえで非常にきわどいバランスで成り立っています。「守・破・離」においても、「破」と「離」の間には、大きな隔たりがあり、「破」の段階で文字通り破門されて没落してしまうか、「立派」だとされるかという評価の分かれ目は、その時代の尺度にかかっているのです。時代のほうがまさに新しい評価尺度に変わったときには、破門された者が破門したほうより、栄えていくという歴史も山ほどあります。
また、ニュートンの「万有引力」にしても、今、彼が現れて同じことを主張したとしても今さら誰も相手にしません。子供でも知っている常識だからです。当時では独創的であった彼のアイデアも、永遠にそうあり続けることはできないのです。しかも、ニュートンは生きている間に幸運にも評価されましたが、これはむしろ珍しい例で、かの有名な「メンデルの遺伝法則」の発見者メンデルのように、死後かなり年数が経ってから再評価される例も少なくありません。逆にいえば、時代が天才に追いつくのを待つしかないのです。このように「独創性」は、時間との関数で考えなくてはならないことがわかります。
次に「ものまね上手」ですが、これは一言でいえば、キャッチ・アップの速さ=最先端の技術を取り入れ、消化する速さを意味しています。日本人の「ものまね上手」というのも、実は「キャッチ・アップが速い」ということです。
日本人のキャッチ・アップの速さは、明治以後や太平洋戦争後だけではありません。奈良の大仏や、戦国時代の鉄砲伝来に代表されるように、異質で高度な文化に触れたとき、日本人はそれを素直に評価し猛烈な勢いで取り入れ、追いつき、ときに追い抜いてきました。
一六世紀の鉄砲を例にすれば、種子島に伝来したのは、たった二挺です。それがあっという間に全国に伝わり、しかも世界でも有数の鉄砲製造国となりました。いかに時代が戦乱の世で莫大な需要があったからだとしても、この速さは特筆に値します。
明治維新のときもそうです。蘭学を学んだ勝海舟がその知識を話しただけで、鍛冶屋は鉄砲を作り上げてしまったといわれています。
このキャッチ・アップの速さの裏には、その最新の技術を受け入れ、消化するだけの素地が日本にはあった、すなわち、日本の潜在能力が、海外に負けないくらいのレベルに達していたといえます。鉄砲の場合は、伝来以前に高度な金属加工の技術がありましたし、幕末でも、木工技術には欧米人が目を見張るものがありました。しかも産業構造においても、素材から関連下請けまで、すべての関連する社会的機能が整っていたことがこれらを可能にしたのです。
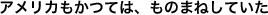
独創性がなく、ものまねしていると批判されたのは、日本に限ったことではありません。
現代では世界の最先端を行くアメリカも、一九世紀には技術後進国で、ヨーロッパの進んだ技術文明を模倣していました。その証拠に、アメリカ人がノーベル賞を多く取り始めたのは、たかだか第二次世界大戦以後のことです。
大切なことは、時代的発展段階を織り込んで考えてみることだと思います。時代的発展経過を考えるとは、次のようにたとえることもできます。
温度差のある暖流と寒流がぶつかるところに魚が集まって良い漁場となるように、異質な文化がぶつかるところに新しい文化が生まれてきます。そのとき、技術的に優越している側は「独創性」があると評価され、劣等感を持つ側は、同じ温度となるまでは「ものまね」をしているということになります。しかし、そこで生まれた新しい文化も、やがて均一な温度の海流になれば良い漁場ではなくなります。するとまた、温度の違う海流が存在するところが、さらに新しい文化をつくり上げるために必要となってくるのです。このようなサイクルのうえで考えるということが、時代的発展段階でみるということです。

自分たちに独創性がなく、ものまね上手であると、現代の日本人が卑下しているのは、異質で高度な文化に触れるとまるごと取り入れてしまい、それまで培ってきた良いものを切り捨て、さらには心情的な部分までも変わってしまうと思い込んでいる点もあるからではないでしょうか。
ところが、決してそうではないのです。
古代において日本は、政治、文化など、あらゆる分野で中国を模倣してきました。しかし、「宦官」と「科挙」の制度だけは導入していません。きちんと取捨選択を行ない、日本の風土にとって良くないと思われるものは、厳然と拒否しているのがわかります。
また、明治維新のときには、それまで主流だった東洋医学はまったく顧みられなくなり、漢方の医者は医師の免許さえ取れなくなってしまいました。ところが、漢方医学が世の中からなくなってしまったかといえば、そうではなく、現在でもずいぶん盛んです。良いものは失わずに、残しているのです。
さらに、心情的な部分でも決して変わっていないことを端的に表しているのが、明治維新前後の「和魂洋才」という言葉で、魂の語が強調されています。革命政府をつくった勤皇の志士たちは、ある時期に尊王攘夷派から開国派へと豹変しましたが、当時、「西洋かぶれ」とみなされた者は何人も殺されています。日本の陸軍を創設した、長州の大参謀・大村益次郎も命を狙われた一人ですが、そのとき彼は、「開国や文明開化は方便だ」と刺客に答えていました。「方便」として、異質で進んだ西洋文化を取り入れていくという、本来アイデンティティ保持の立場なのです。これが、「和魂洋才」です。
面白いことに、現代の最先端技術においてもこの心情(魂)が和の言葉存続に現れています。人工衛星や半導体といった技術は取り入れますが、現場の人々は無意識のうちに、人工衛星を「ほし」、半導体の集積回路を「いし」と呼んでいます。使われているのは、不思議と大和言葉です。そうでないと現場ではなじめず、ストレートに通じないのです。根っこの部分では、日本人の和魂ともいうべきものが、地下水のごとく、脈々と溢れ続けていることがわかります。
一方で欧米においてさえ、今日では自分たちが独創によって考え出した原理を、実用化して工業製品として世界中に売ることができるのは、それが高度なものになるほど、一番確かなのは日本だといわれています。今日、欧米諸国にとって日本は独創性を具現化し工業的に実証する不可欠なパートナーと認識されるほどになってきているのです。
今、歴史は情報化社会へと大きく変わろうとしています。しかし情報化において日本は、アメリカに一〇年は遅れているとよく海外からもいわれています。日本はこれから再び、このギャップのキャッチ・アップの時代に入ることでしょう。おそらく、マルチメディア時代にも「守」段階では、「ものまね上手」といわれることもあるかもしれません。その際、キャッチ・アップの速さが日本の特質であり、?マルチメディア?文明開化でも「和魂」がそう変わるものではないことを再認識し、したたかな自信を秘めて対処していけばよいのではないでしょうか。
(PHP研究所 月刊誌『THE21』平成8年に掲載、PHP研究所『THE21』編集部編集長 山岡 勇二様よりホームページ掲載のご許可をいただきました)
|