|
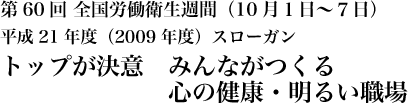
今年は禅の立場から自分でつくる健康について考えてみました。
日常生活を健康におくるための自分にとっての仕付けです。躾ではありません。
自分の健康を管理し、意識を爪の先まで保つようにと願っています。
自分の健康ばかりでなく両親の健康にも目配りし、家族が健康に生活できるよう、子どもの仕付けにもこころを配りましょう。健康で働けることは毎日の生活から生まれます。
今回は新聞記事から構成し、新聞記事も禅というか、日常の生活の視点から記事が企画されているように思います。歓迎です。毎日の生活の基本というか、心構えというか、生活管理の基本に立ちましょう。それが今年のぼくたちのテーマです。
日刊工業新聞 2009年(平成21年)8月6日
尿意感じる仕組み解明
生理学研と山梨大 頻尿改善薬の開発へ
【名古屋】自然科学研究機構生理学研究所の富永真琴教授と曽我部隆彰助教は5日、マウスを使った研究で、膀胱(ぼうこう)に尿がたまったことを感じるメカニズムを解明したと発表した。膀胱内側の細胞にあるたんぱく質の「TRPV4」が膀胱のふくらみを感知することが分かった。ヒトにもTRPV4があり頻尿などを改善する薬剤の開発につながるという。
山梨大学医学部との共同研究による成果。TRPV4が存在する膀胱上皮細胞を培養し、その細胞を引っ張って伸ばした。するとTRPV4がこれを感知して活性化し、細胞内にカルシウムが入り込む。これを受け、膀胱に尿がたまったことを神経に伝えるアデノシン三リン酸(ATP)が細胞から放出される仕組み。TRPV4を欠損させた細胞では一連の動きは起きなかった。
読売新聞 2009年(平成21年)7月8日
尿モレ2
骨盤底筋を鍛える
膀胱(ぼうこう)や子宮などの臓器を支える骨盤底筋(こつばんていきん)が弱くなっていると、尿漏れになりやすい。そのため骨盤底筋を鍛えることで、尿漏れの予防や改善につなげることができる。
尿漏れの電話相談を行っているNPO法人日本コンチネンス協会(東京)の寺内淳子さんに骨盤底筋体操のやり方を教わった。
姿勢は自由で、立っていても座っていてもいい。(1)体の力を抜いて、リラックスする(2)肛門(こうもん)と膣(ちつ)を締める。ゆっくり「1、2、3…」と五つ数えてから、緩める。これを5回繰り返す(3)次に、縮めたらすぐに緩める。これを5回繰り返す。(1)〜(3)を1セットとし、1日10セット行う。一度にまとめて10セットするのではなく、1日で何回かに分けて行う。毎日続けて、効果が表れるには3か月ほどかかる。
特にせきやくしゃみ、スポーツをしたときなどに尿が漏れる「腹圧性尿失禁」の場合、骨盤底筋体操で40〜50%の人は症状が改善するという。加齢により膀胱のコントロールがうまくいかない「切迫性尿失禁」の場合でも、体操の効果はあるそうだ。
「おなかやお尻に力が入らないよう、肛門や膣を軽くふさぐような感覚でやってみましょう」と寺内さん。うまく締められているか心配なら、入浴時に、肛門のわきの辺りを触って、縮めたり緩めたりして確認する。
地味な筋力トレーニングなので、毎日続けるためには生活の中での習慣づけが大切だ。例えば、<朝起きあがる前に布団のなかで><通勤途中の電車のなかで>など日常の行動のなかに組み込むようにする。「簡単なので、尿漏れで困っている人はもちろん、そうでない人も予防のために取り組んでほしい」と寺内さんは話している。
骨盤底筋体操
家でも外出先でもやりやすい姿勢で
座って
机にもたれて
あおむけ
読売新聞 2009年(平成21年)7月9日
尿漏れ3
トイレ尿意感じてから
急にトイレに行きたくなってトイレに駆け込もうとしたら間に合わなかった――中高年女性にはこうした尿漏れの経験や症状がよくある。「漏らしたくない」「漏らさないように」と、尿意がなくてもこまめにトイレに行く女性は少なくない。
しかし、「それは膀胱(ぼうこう)にとってよくありません。膀胱に尿が十分たまっていないのに排尿していると、逆に膀胱に尿をためにくくなることがあります。尿意を感じてからトイレに行くようにしましょう」と、東京都東大和市の東大和病院泌尿器科の医師、大川あさ子さんは指摘する。尿漏れ予防のつもりの行動が、逆効果になりかねないというのだ。
そこで、不必要にトイレに行っていないか、自分の排尿パターンを確認するために、1日分の排尿日誌をつけてみることを大川さんは勧める。トイレに紙コップや計量カップを用意し、排尿するたびに尿量を測る。何時にどれだけ排尿したか、1日分を記録する。尿漏れがあったかどうかも書き込む。できるだけ水やお茶など水分をとった量も記録しておく。
用紙は何でもいいが、日本排尿機能学会のホームページ(http://www.luts.gr.jp/guideline/index.html)から、ひな型をダウンロードすることもできる。
排尿の量は正常な人なら1回150〜400ミリリットル、1日10回以下が目安。日誌の記録を見て、何時間ぐらいなら我慢できているか、我慢できる量や時間を見極める。そのうえで、トイレに行くタイミングを修正してみる。それでもうまくいかない場合は、医療機関に相談する。
また、尿漏れ予防には、水分の取り方も大切だ。漏れを心配して水分摂取を控えるのもよくないが、一度にまとめて水分をとるのも望ましくないそうだ。飲み物は1日1200〜1600ミリリットルほどを、間隔をあけて飲む。
「尿漏れの予防には、骨盤底筋体操と併せて、日常生活の見直しも大切です」と大川さんは話している。
| 排尿日誌 |
| 時間 |
排尿 |
尿量 |
漏れ |
その他 |
| 6:15 |
○ |
350ml |
|
寝起きでギリギリだった |
| 8:30 |
○ |
200ml |
|
|
| 11:20 |
○ |
120ml |
○ |
水仕事をしていたら急に行きたくなったが間に合わなかった |
| 計 |
7回 |
1350ml |
|
|
■男子の尿漏れ危機を改善するには肛門のところに人差し指をあて、指をつかまえるように肛門を収縮させる。それを50回続ける。こうした運動として改善していく。
読売新聞 2009年(平成21年)7月11日
尿漏れ4
対策には専用パッドを
「尿漏れパッドと生理用ナプキンはどう違うのですか」「トイレに流しても大丈夫ですか」。尿漏れに関する電話相談を受け付けている「ユニ・チャーム」(東京)には、消費者からこんな相談が寄せられている。
同社では尿漏れ専用のパッドを、吸収量の異なる8種類販売している。しかし、過去の調査では、尿漏れのある女性の3割程度しか利用しておらず、多くの女性が生理用ナプキンで代用していたという。一般に専用パッドの方が3割ほど高いのも、利用を控える原因になっているようだ。
ただ、尿と経血では性質が異なるため、パッドの吸収剤や表面の構造も異なる。青い色水を尿漏れパッドと生理用ナプキン両方に同時に流してみたところ、生理用ナプキンの方が水の吸収が遅く、表面に手を当てると水が逆流した。これでは、肌を傷めたりする恐れがある。
ユニ・チャームでは希望者に尿漏れパッドの試供品を無料で配布している。「使用方法は生理用ナプキンと同じ。ぬれたら交換し、製品の包み紙で包んでトイレのゴミ箱に捨てましょう」(同社広報)
尿漏れの症状があっても一人で悩む女性は少なくない。インターネットや無料相談を上手に活用して、症状が悪化する前に対策をとりたい。
NPO法人日本コンチネンス協会(東京)では、尿漏れに関する無料電話相談を不定期で行っている。同協会の専門講座を修了した相談担当者が対応する。30〜70歳代の女性からの相談があり、必要に応じて全国各地の医療機関を紹介している。
看護師や保健師らが相談にのる「ウーマンズヘルス・パートナー」もある。
インターネットで情報収集することも可能だ。大鵬薬品の専門サイト「頻尿.jp」では、尿漏れの基礎知識のほか、ヨガや骨盤底筋体操などを動画で見ることができる。(小坂佳子)
無料相談窓口やホームページ
▽NPO法人日本コンチネンス協会
03・3301・0725(不定期) http://www.jcas.or.jp/
▽ユニ・チャーム
「いきいきダイヤル」0120・041・062(平日午前9時30分〜午後5時)
「尿もれケアナビ」http://www.nyoucare.jp/
▽ウーマンズヘルス・パートナー
0120-744-066(平日午前10時〜午後4時)
▽大鵬薬品
「頻尿.jp」http://www.hinnyou.jp/
読売新聞 2009年(平成21年)3月25日
妊婦の健康管理1
やせすぎ 子に悪影響
1年間に生まれる赤ちゃんの数は少子化の影響で、減少傾向にあるが、2500グラム未満で生まれる「低出生体重児」の割合は増加している。厚生労働省によると、1990年に全出生数の6.1%だった低出生体重児は、2006年には9.6%まで上昇した。
兵庫県立柏原病院副院長の上田康夫さんは、「妊婦が太らないようにしているため。特にやせ形や標準体形の人までが体重抑制したことが大きい」と指摘する。赤ちゃんの大きさは、母体の体重増加に関係する。体重増加が7キロ未満の妊婦は、2500グラム未満の低出生体重児を生みやすいと言われる。
こうした傾向は、30年以上前から提唱された「小さく産んで大きく育てよ」という考え方と日本人女性のやせ願望が重なったためとみられる。妊婦の肥満は、妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)にかかりやすく、体重4000グラム以上の巨大児が生まれる率も高く、難産にもつながるとされてきた。
しかし、最近、「小さく産め」という指導はやめるべきだとの声が高まる。2500グラム未満で生まれる子どもが増えている上、低出生体重児は成人後、糖尿病や高血圧などになりやすいという研究が相次いでいるからだ。
国立保健医療科学院母子保健室長の滝本秀美さんは「やせた妊婦の増加は、子供の発育を損なう。適正な体重増を知ることが大事」と話す。
厚生労働省は、肥満度の国際指標「BMI」による「普通」「やせ形」「肥満」を基に、妊娠中の体重増加量の目安を公表している。普通なら7〜12キロ、やせ形の場合は9〜12キロを推奨する。
滝本さんは、「日本人の感覚では太りすぎと感じるかもしれないが、子供のためには一定の体重増も必要」と語る。
BMIの計算方法
体重(キロ)÷身長(メートル)÷身長(メートル)
→18.5未満は「低体重(やせ)」
→18.5〜25未満は「普通」
→25以上は「肥満」
日本肥満学会の推奨体重
身長(センチ) 体重(キロ)
やせ 普通 肥満
145 ← 38.9 ←→ 52.6 →
150 ← 41.6 ←→ 56.3 →
155 ← 44.4 ←→ 60.1 →
160 ← 47.4 ←→ 64.0 →
165 ← 50.4 ←→ 68.1 →
厚生労働省が推奨する妊娠後の体重増加量
9〜12 7〜12 5(医師に個別相談)
読売新聞 2009年(平成21年)3月
妊婦の健康管理2
散歩で食欲と体力増進
妊婦の栄養摂取と胎児への影響を研究する三重大学教授の佐川典正さんの興味深いデータがある。同大病院など3施設で出産した1523人の妊婦のうち、やせすぎの妊婦は2割に上り、やせ形の妊婦から低出生体重児が生まれる確率は標準体形に比べ1.8倍も高かったという。
「現代の若い女性はやせすぎだ。健康な赤ちゃんを産むためにはもっと栄養を取り、体重を増やす必要がある」と佐川さんは強調する。
妊婦の必要な摂取エネルギーはどれくらいか。18〜29歳の専業主婦の場合、1日摂取量は通常約1750キロカロリーとなるが、それに加え、16週までの妊娠初期はプラス50キロカロリー、28週までの中期はプラス250キロカロリーが望ましい。
それ以降はプラス500キロカロリーの2250キロカロリーとなるが、その時の推奨メニューを厚生労働省研究班が示している。主食のごはんは「中盛り4杯」、副菜の「野菜料理4、5品」とかなり多め。主菜の「肉・魚料理は1、2皿」と少ない。これにミカン2個、牛乳1本(200?)程度が加わる。
普段小食の女性が、これほどの食事を取るのは大変だ。そのため、日本助産師会副会長の岡本喜代子さんは「1日1時間以上の散歩」を勧める。「おなかが減り、気分転換にもなる。お産に必要な体力もつけられる」と語る。
最近注目される栄養素が緑黄色野菜や糖類に含まれる「葉酸」。葉酸が不足すると、貧血や出血が起こりやすく、赤ちゃんの脳や神経管が正常に形成されない「神経管閉鎖障害」のリスクが高まる。
国は、2000年に妊娠を望む女性に対し、「食事以外にも、栄養補助食品から1日0.4ミリグラムの葉酸を取る」ように勧めている。しかし、日本ではまだ葉酸の重要性は認識されていない。
厚生労働省研究班が推奨する1日の食事
※食品例の( )の数字を合計し、上の単位数になるような献立を考える
主食は多め、主菜は少なめの「逆三角形型」が理想
適度な運動 水分
1日分 食品の例
主食(5〜7単位) うどん・そば1杯(2)、ごはん小盛り1杯・食パン1枚(1)
副菜(5〜6単位) 野菜いため(2)、野菜サラダ、ほうれん草のお浸し、みそ汁(1)
主菜(3〜5単位) ハンバーグ、鶏肉の空揚げ(3)、焼き魚(2)、目玉焼き(1)
牛乳・乳製品(2単位)牛乳1本(2)、ヨーグルト1パック、チーズ1片(1)
果物(2単位) りんご・梨1個(2)、みかん・柿1個(1)
読売新聞 2009年(平成21年)3月27日
妊婦の健康管理3
喫煙・飲酒 胎児に影響
国が2000年に実施した乳幼児身体発育調査で、喫煙する妊婦は10%に上る。10年前の5.6%に比べ倍近い。このうち1日11本以上吸う妊婦は22%を占める。
「喫煙する妊婦は、若いときから吸い始め、夫や両親が喫煙する人に多い。喫煙が悪いとの自覚はあるが、胎児へのリスクは考えない人が目立つ」。妊婦向け禁煙外来を04年に開設した大阪府立母子保健総合医療センター母性内科副部長の和栗雅子さんは指摘する。
妊婦の禁煙指導が求められるのは、喫煙する女性の増加に加え、胎児の発育に影響することがわかってきたからだ。厚生労働省研究班によると、喫煙妊婦から2500グラム未満の低出生体重児が生まれる割合は、非喫煙妊婦の約2倍だ。赤ちゃんの体重も平均200グラム少ない。早産、自然流産の発生率も高まる。
発育に影響するのは、たばこに含まれるニコチンと一酸化炭素によって血行が悪くなり、胎児が低酸素状態になってしまうためだ。そのため同センターでは、ニコチンの尿中濃度、一酸化炭素の呼気濃度を測定し、それを基に禁煙指導を行う。約8割が「妊娠初期に禁煙すれば胎児への影響は少ない」ということを理解し、一度は禁煙する。しかし、出産後まで禁煙が続く人は、喫煙する妊婦の約3割にとどまっている。
一方、飲酒の影響も注目される。厚労省研究班によると、妊婦が1日にアルコールを60ミリリットル(グラス4杯のワインに相当)摂取すると、胎児の成長障害を引き起こす率が高まることがわかっている。
国立成育医療センター周産期診療部長の左合治彦さんは、「胎児に影響のないアルコール摂取量は不明だ。少量でも胎児に影響を及ぼす恐れはある」と妊婦の飲酒は控えるよう警告する。
●妊娠中の1日の喫煙本数と早産率
非喫煙 6%
5本以下 7%
6〜10本 12%
11〜20本 13%
21〜30本 26%
31本以上 34%
●胎児に影響を及ぼす恐れのある1日の飲酒量(厚生労働省研究班)
ビール 中瓶 約2.5本
ワイン グラス 約4杯
日本酒 約2合
ウイスキー ダブル 約2.5杯
読売新聞 2009年(平成21年)3月24日
動物とふれあう2
「ペットロス」重症化に注意
ペットを失った時、悲しみや喪失感を感じる「ペットロス」はしばらくすると回復するが、重症化するケースもあり、注意が必要だ。
日本ペットロス協会(神奈川)の代表で、心理カウンセラーの吉田千史さんは「家族同然にかわいがっていたペットを失った場合、悲しみにくれ、気分が沈みがちになるのは自然なこと」と話す。通常は半月から1か月ほどで回復するという。ペットロスに伴う心の変化を図にまとめた。
しかし、いつまでも悲しみが治まらず、強い罪悪感や抑うつ、睡眠障害などが続くケースも数%程度ある。こうなると、かなり重いペットロスと言える。
ペットをでき愛していたが、十分に看護できなかったという強い葛藤(かっとう)がある場合、重いペットロスになりやすい。まじめできちょうめん、責任感が強く、他人に気を使いがち、熱中しやすいといった性格の人も陥りやすい。
吉田さんによると、ペットロスを重症化させないためのポイントは、(1)ペットは自分より先に死ぬことを自覚する(2)過剰に依存せず、ほどよい距離をとる(3)ペットを介した仲間を作っておく(4)ペットロスについて正しい知識を持っておく――の四つ。「仲間がいれば、悲しみを共有したり慰めてもらったりできる。知識をもっていれば、必要以上の苦しみや不安を防ぐことができます」と指摘する。
ペットロスへの認知はまだ低く、周囲の理解は得られにくい。「ペットが死んだくらいで」と言われることもある。しかし、悲しみを抑えこまないことが大切だ。
吉田さんは「1か月たっても悲しみが癒えないかひどくなる、体重の極端な増減が見られる、死にたいと口に出したり考えたりするといった場合には、ペットロスに詳しい診療内科医やカウンセラーなどの専門家に相談しましょう」と助言する。
●ペットロスの過程
準備期
獣医師に余命を宣告されるなど、ペットの死が現実的になる。死までの期間が短いことが多く、心の準備があまりできない
↓
ペットの死
↓
衝撃期
死の直後から1〜2日か1週間程度。衝撃と不安の強さは人により異なる。
↓
悲痛期
一両日または1週間ほどたって、改めてしんみりとした悲しみや寂しさが強くなってくる。申し訳なさや絶望感に襲われる
↓
回復期
気持ちの整理がつき始める。いない生活に少しずつ慣れ、思い出しても以前ほどつらくなくなる
↓
再生期
悲しみから立ち直る。ペットへの感謝の気持ちが生まれ、失った経験を肯定的に振り返ることができる
読売新聞 2009年(平成21年)3月20日
動物とふれあう3
ペット感染症 予防必要
飼っているペットから感染症がうつることもあり、注意が必要だ。
東京都内の30歳代の女性は、長くぜんそくのような症状を見せていたが、原因が分からず、治療しても改善が見られなかった。詳しい検査をしたところ、Q熱に感染していることが分かり、抗生物質を服用すると症状が緩和した。室内飼いしている3匹の犬から感染したと見られる。
「ペット溺愛(できあい)が生む病気」の著書がある日本大学医学部助手の荒島康友さんによると、Q熱は動物からうつる感染症の一つ。飼い猫は25%、飼い犬は15%が菌を持っているとされる。人は空気中に飛散した菌を吸い込んで感染する。「慢性化すると、うつ病に似た症状になる場合もあります」と話す。注意が必要な感染症を表にまとめた。
ペットブームの中、犬や猫の習性やしつけの仕方を十分に知らずに飼い始める人も多く、犬や猫がいやがることをして、かまれたりひっかかれたりして感染するケースがある。また、ペットを溺愛して接触の程度が強くなり、感染する場合もある。
荒島さんは予防法として、(1)定期健診を受けさせる(2)屋内で飼う猫は爪を切っておく(3)ふん便は早めに処理する(4)口移しで餌を与えない(5)寝る時には寝室に入れない――などを勧める。「ペットは人間ではないということを認識して、節度あるふれあいをしてください」と呼びかける。
感染症を疑う症状が出て、受診する際には、医師にペットを飼っていることを伝えることが大切だ。ペットからの感染症を考える医師はまだ多くないからだ。できれば、ペットの種類や飼い始めた時期、接触状況などを書いた紙を渡しておくといい。
愛犬や愛猫などとは節度を持ってふれあい、豊かなペットライフを楽しみたい。
注意すべき感染症
パスツレラ症(猫、犬、ウサギなど)
・かまれたり、ひっかかれたりして化のうする。気道感染して、せきやたんが出る。
Q熱(猫、犬)
・インフルエンザのような症状。慢性化すると、肝障害や不定愁訴、慢性疲労のような症状
オウム病(鳥、特にセキセイインコが多い)
・インフルエンザのような症状。40歳以上の場合、多臓器障害になり死亡する場合も
猫ひっかき病(猫、犬)
・かまれたり、ひっかかれたりしてリンパ節が腫れる
サルモネラ症(ミドリガメ、犬)
・食中毒になる
エキノコックス症(犬、猫)
・体内で寄生虫が転移し、有効薬はない。感染から発症まで10年ほど。北海道で多い
読売新聞 2009年(平成21年)4月2日
呼吸の方法3
鼻呼吸で集中力向上も
口呼吸は、身体の健康に悪影響を与えることがあるだけでなく、集中力や感情コントロールといったメンタルな面でもマイナスに働くという指摘もある。逆に鼻呼吸に改めることによって学習効率が高くなる、といった研究もある。
「吸って吸って止めて、ゆっくりゆっくりゆっくり吐いてーー」
明治大学の斎藤孝教授(教育学)のセミナーには、大勢の親子が訪れていた。子供は幼児から小学校高学年まで様々。真剣なまなざしを教授にむける。
斎藤教授は学生時代から子供の呼吸に関する研究を続けてきた。「精神を集中し、感情をコントロールするには呼吸法が重要。鼻から深く吸って強く吐く、ということができなくてはならない。しかし、今は鼻呼吸ができずに、口をぽかんと開けている子供が多い。こうしたことが、子供の集中力のなさ、キレやすさにつながっているのではないか」
自ら開く塾でも斎藤教授は、子供たちに鼻呼吸の呼吸法を指導している。まずは姿勢を正し、(1)3秒間鼻から吸う(2)2秒間止める(3)15秒間かけてゆっくり口から吐く、という手順だ。
最初は長い時間をかけて吐き出せない子供が多いが、練習するとできるようになる。
「静かに強く吐くことで気持ちは落ち着く。落ち着いているのに、作業の速度は上がる」と斎藤教授。つまり勉強や試験には最適な状態だ。高校生に行った実験では、この呼吸法を行った前後で、約9割の生徒の計算問題の成績が上がったという。
集中力不足の子供に、言葉で「集中しろ」と言っても効果は上がりにくい。わが子の成績に悩みを抱える親たちにとって、鼻呼吸の“効能”は一つのヒントになりそうだ。
斎藤教授の今年度の塾は9月に開講の予定。詳細は未定。
読売新聞 2009年(平成21年)7月16日
よい姿勢の保ち方3
体に合うような机など調整
長時間、机に向かって勉強や仕事をしていると、首や腰の痛みを覚えるという人は多いだろう。その原因となる姿勢の乱れは、机やいすの位置や高さを調整すると改善される。
体に負担の少ない机やいすの研究開発をしている慶応大学の山崎信寿(のぶとし)教授は、「頭は重いので、首が前傾すると疲れやすい。顔を起こした状態を基本に、パソコンの配置やいすの高さを決めてください」とアドバイスする。
パソコンのモニターは、目の高さに。ノートパソコンの場合は、キーボードとマウスを別に用意し、前かがみにならないようにする。
字を書いたり、読んだりする時には、丈夫な板や箱を用意し、手前が低くなるよう5〜15度の傾斜をつければ、顔を下に向けずに作業ができる。
理想の姿勢は、いすに深く座って背もたれに支えられ、肩が上がらずに机に前腕を載せることができ、床に足がかかとまでつく状態。しかし、職場では高さ70センチの机が使われている場合が多く、小柄な女性が足が接地するようにいすの高さを決めると、肩が上がる。机に前腕を載せると、足が床に届かない。
山崎教授は「足がぶらぶらすると、座面でひざ裏が圧迫され、血行が悪くなってむくみやすい。足台を置くなどして安定させて」と言う。山崎教授が事務機器メーカーのイトーキと共同開発した女性用のいすは、座面の前端を下に折ることが可能。子ども用学習いすには、いすの脚に足置き台がついているものもあるが、床につくほうが望ましい。
今年オープンした「オカムラいすの博物館」(東京・千代田区、予約制)には、体にかかる圧力の分布測定や、体格に合ったいすを再現する装置があり、疲れにくい姿勢を体験することができる。
●机に向かう作業の注意点
深く腰かける。
肩が上がらないように
モニターを見たり字を書いたりするときに前かがみにならない
記帳や書見用の台。5から15度の角度をつける
足が床に届かないときは台を置く
読売新聞 2009年(平成21年)9月18日
「せき」の見立て3
たん出たら市販薬は禁物
せきが止まらないとき、まず思い浮かべるのが市販のせき止め薬。しかし、どんなせきにも有効というわけではない。「市販のせき止め薬を使用していいのは、たんの出ない乾いたせきの場合」と話すのは、金沢大学病院の藤村政樹准教授(呼吸器内科)だ。
まずは、せき止めのメカニズムから。せきは、気管内のウイルスや細菌などの異物をたん(粘液)と一緒に体外へ出す、生体の防御反応だ。気管内の気道壁にある細かい線毛が、徐々にたんを運ぶとともに、せきで一気に排出する。
一方、せき止め薬は中枢神経に働いてせきを止める。つまり、たんがあってもせきは止まってしまう。「そうなると、たんを体外に排出できなくなるばかりか、たんが肺に落ちて肺炎になってしまう危険もある」と、藤村さんは説明する。
たんを伴うせきが長引く場合は、かぜ以外の疾患が隠れていることもある。「せき止め薬に頼らず医療機関へ」が鉄則だ。
たんが出ないせきに対しては、薬剤師に相談し、早めにせき止め薬を使うほうがいい。薬を使わないでいるうちに、せき込むことで、のどの粘膜を傷めてしまい、そこから感染を引き起こすことがあるからだ。また、せきは体力をひどく消耗させるし、「映画館や食事に行けない」など、生活上の不自由も生じる。ただ、乾いたせきでも、長引くようなら医師の診察を。
せきの予防のためには、住まいの環境に気を配ることも大事だ。せきぜんそく、アトピーせきなどのアレルギー性のせきを防ぐには、「じゅうたんを化学繊維のものに換える、ぬいぐるみを置かないなどの工夫も必要。エアコンなどのカビも要注意です」と藤村さん。
これからの季節、就寝時は、加湿器や湿ったタイプのマスクの使用もお勧めだ。
読売新聞 2009年(平成21年)9月19日
「せき」の見立て4
マスクの前に水飲み保湿
せきといえばマスクだが、正しくつけなければ効果は半減する。情報サイト「オールアバウト」の薬ガイドで、AMC代表の三上彰貴子(あきこ)さん(薬剤師)に正しいマスクの選び方、つけ方を聞いた。
マスクにはガーゼタイプと使い捨ての不織布タイプがある。ガーゼタイプは洗って何回も使え、顔に密着し温かいが、使い捨てに比べ不潔になりがちだ。
乾燥によるせきを防ぐにはどちらも有効だが、「マスクをする前に水を飲んでおくのも保湿にはいい」と三上さんはアドバイスする。
他人のせきによるウイルス感染を防ぐためには、衛生的な不織布タイプがおすすめ。高性能の商品もあるが1枚数百円と高価だ。「着用すると息苦しさもあり、通常の予防用では、そこまでの必要はないでしょう。インフルエンザ患者を看病しなければいけない場合には有効かも」
不織布タイプを装着する時には、まず鼻の部分を折ってフィットさせる。次に下の部分をあごまで持っていって、すき間がないように整える。きちんと装着するためには、女性用、子供用など、自分に合ったサイズを選ぶこと。
電車内など人が密集する場所以外で予防用にマスクをする必要はない。せきだけが感染源ではないので、つけたり外したりするときには、汚れた手でマスクの内側に触れないこと。そして、「マスクに頼らず、手洗い、うがいを励行すること」と三上さん。
マスクで感染を完全に防げるわけではない。せきをするとき、マスクの上からでもハンカチで押さえる配慮が必要だ。(梅崎正直)
読売新聞 2009年(平成21年)9月28日
爪をいたわる1
指先より短く切らない
爪は指先にありながら、その役割について日頃、意識されることが少ない。手入れの方法を知り、いたわりたい。
通常、爪と呼んでいる指先の硬い部分は、正式には爪甲(そうこう)と言う。爪は爪甲のほか、爪甲を作る根元の爪母(そうぼ)や、爪甲の下にあり、爪甲が載っている爪床(そうしょう)など、複数の部位を含んだものだ。ここでは一般的な言い方にならい、硬い部分を指して爪と呼ぶ。
爪は皮膚の表面を覆う角質と同じく、ケラチンというたんぱく質でできている。爪と皮膚の硬さが違うのは、ケラチンの中に含まれるシスチンというアミノ酸の割合が違うからだ。皮膚は3%だが、爪は12%と多いため、硬い。
東皮フ科医院(堺市)院長の東禹彦(のぶひこ)さんは「爪が持つ役割の一つは、指先に加わる外力から、指先の皮膚を保護することです」と指摘する。手先を使う作業をする時、爪があることで指先の皮膚に加わる力は小さくなり、皮膚はその分、保護される。爪を短く切りすぎると指先の皮膚が擦れて荒れることがあるが、爪を伸ばすと荒れは治る。
爪には指先の形を整える役割もある。幼児によく見られるかみ癖のために爪が極端に短くなっていると、指先も短くなり、横に少し膨らむ。かみ癖をやめ、爪の長さが正常に戻ると、綺麗な指先になる。東さんは「爪があることで指先に力が入り、細かい物をつかむことができる。これも役割の一つです」と話す。
爪がこうした役割を果たすようにするには、切り方が重要になってくる。指先を守るのだから、指先よりも短く切らないことが大切だ。「短く切るのは、爪の先のすき間に汚れがたまるのを嫌がるため。しかし、それは洗えばいいことです」と東さん。
子どもの頃、爪が伸びていると、親から「みっともないから切りなさい」と言われた記憶のある人も多いだろう。ただ、それも程度問題。切りすぎには十分注意する必要がある。
読売新聞 2009年(平成21年)9月30日
爪をいたわる2
陥入爪 角を切ると悪化
爪の中でも特に無関心になりがちなのが、普段は目に触れることが少ない足の爪だ。ただ、注意を怠ると、深刻なトラブルが起こる恐れがある。
代表例が、爪の角がトゲのようになって周りの皮膚に食い込み、痛みを伴う陥入爪(かんにゅうそう)だ。足の親指に発生することが多く、幼児から高齢者まで幅広い世代の人が悩まされている。陥入した部分は細菌が感染しやすくなり、赤く腫れたりうみがたまったりして、激痛で歩けなくなることもある。
整形外科医の町田英一さんは「爪の角を切れば治ると思っている人が多い。しかし、これが原因で症状がどんどん悪化していくのです」と話す。
悪循環の仕組みは、図の通りだ。(1)爪の角が皮膚に食い込んで軽い痛みがあるため、角を切る。痛みは消える(2)爪がなくなった部分は肉が盛り上がるため、爪が伸びるとさらに食い込み、また痛みが出る(3)(1)と(2)を長年繰り返すと、爪が巻きながら伸び、角を切ろうとしても、肉に食い込んで取り切れない。トゲのように肉の中に残り、痛みは消えない(4)トゲがさらに巻きながら伸びて深く潜り込み、肉もさらに盛り上がって悪化する。
「足の爪を切る際は、角を肉の外に残すのが大切」と、町田さんは助言する。
通常、爪が巻かないのは、歩く際に指の腹に力が加わり、爪の両端を押し上げているからだ。高齢になってあまり歩かなくなると、指の腹に力が加わる機会が減り、爪は巻きやすくなる。
ハイヒールにも注意が必要だ。履き続けていると、親指の腹が地面を押しにくくなり、爪が巻きやすくなる。町田さんは「通勤では歩きやすいウオーキングシューズ、オフィスではかかとの低い靴、デートではハイヒールといった具合に、履き分けてみては」と勧める。
読売新聞 2009年(平成21年)10月1日
爪をいたわる3
はがれ 菌の繁殖に注意
爪にマニキュアを塗ったり、付け爪をしたりするネイルアートは、女性に人気が高い。ただ、塗ったものを落とす際に爪の健康を損ねる恐れがあり注意が必要だ。
マニキュアなど爪に塗ったものを落とす際には、リムーバー(除光液)を使う。このリムーバーには有機溶剤のアセトンが含まれているものが多く、落とす際に爪が傷み、薄くなったりもろくなったりする恐れがある。
また、最近人気を集めているジェルネイルは、ジェル状の樹脂を爪に塗り、紫外線を当てて固めるもので、丈夫で長持ちする。ただ、これを落とす際もリムーバーを用いることがある。
よしき皮膚科クリニック銀座(東京)の院長、吉木伸子さんは「リムーバーを使う頻度を少なくすることが大切」と助言する。
より注意を要するのは、爪の先がはれ、皮膚との間に深いすき間ができる爪甲剥離(そうこうはくり)症だ。爪を伸ばしたまま、日常的にパソコンのキーボードをたたくといった状況が続くと、徐々に爪がはがれてしまうが、通常は気付く。だが、マニキュアをしていると、気付きにくい。長い付け爪をしている場合も同じだ。初期の段階であれば、付け爪や爪を伸ばすのをやめればすき間は治るが、慢性化すると元にもどらなくなることがある。
また、爪甲剥離症になると、すき間に緑膿菌(りょくのうきん)という菌が繁殖し、緑に変色するグリーンネイルも起きやすくなる。すき間は乾きづらく、常に湿った状態になるためだ。
緑膿菌そのものは病原性が弱く、健康な人にとっては怖いものではない。だが、病気などで抵抗力の弱った人は、感染して肺炎を起こすこともある。
吉木さんは「爪は生え替わるから何をしてもいいなどと考えるのではなく、治らなくなるものもあることを念頭に置いてほしい」と指摘する。
■みなさんの親で老人ホームや旅行好きの方がおいでになると思います。
老人ホームや旅行先のホテルでの入浴は、爪に細菌が感染し、足の爪が変色していたらなんらかの感染菌におかされていると思ってください。爪の健康色に注意をもって異常があったら皮膚科で診てもらってください。
(次回、ドラッカー先生の『ネクスト・ソサエティ』をなぞって思うことをアップロード予定しています。現在、執筆中です。できるだけ早く投稿します。9月は佐藤の前立腺切除の入院もあってアップロードが遅れてしまいました。お詫び申し上げます)
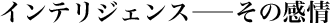
第二次世界大戦は軍部の真珠湾攻撃で開戦となった。
欧米とわが国のインテリジェンスは初めて衝突した。わが国近代明治以来のインテリジェンスとして昇華し表面化した。
日本人の思考の中に歴史や時間の過程を「ひと言」で表現する習慣があるが、こんにちまでこの思考は継続されている。これをインテリジェンスの「感情」と把える。ここに論理性はない。
第二次世界大戦は広島と長崎に原爆が投下され終戦を迎えた。
戦後64年目を迎えた。
アメリカ合衆国のインテリジェンスは真珠湾攻撃に対する「報復」であったと思う。
日本人インテリジェンスの中にこの「報復」に対して怨念を持ち続けることではなく、真珠湾攻撃に対するアメリカインテリジェンスは9.11ニューヨークの高層ビル崩壊の衝撃が二重写しになる。アメリカのブッシュ大統領は「テロリストに対する報復」を各国の仲間たちに求めた。世界の警察としては許しがたい感情であったと思う。
オバマ大統領はわが国の原爆投下に対し道義的な、ということばで核廃絶に言及した。
多くの被爆者たちにもインテリジェンスという感情の扱い方について許すわけではないが、苦痛と苦難を乗り越えるべき、戦争に対するけして戦争をしてはならないという感情を持ってこの原爆投下を風化させるのではなく、乗り越えていく感情がいま芽生えてきたと思う。この地球から戦争をしてはならないというインテリジェンスはオバマ大統領のソフトパワーを歓迎した。国際問題は「対話」によってのみ解決できるもので、対話から諸問題の解決へと「インテリジェンス――その感情」の絡まった糸をほぐしていく以外に解決の道を求めてはならないことを広島・長崎はわが国戦後を生きてきた者に教えている。
それはこうした悲劇の芽は国連による解決を求めて、どの国のインテリジェンスにも警察行動による解決ではなく、解決の糸口を探ることで、それは警察行動による力の民族的抑圧による外交ではなく、こうした国家間対立の芽をつむぎながら努力していかねばならないだろう。歴史的転換期の新現実主義的外交の姿と考える。
古い体質のアメリカインテリジェンスはオバマ大統領によって変化するだろうか?
自公政権は北朝鮮に対する感情をあおっている。危険な外交政策と映る。
世界はグローバル化し、わが国近隣外交は長い歴史の中で関係がつくられていく。
冷戦の終結をもって自民党の外交政策は終焉を迎えた。自民党の長期政権はきわめてセクト主義であった。民主主義の大衆政治はひと握りの政治的セクト主義で国民を統治する政治構造をつくってきた。官僚内閣制の崩壊をもってわが国歴史は大転換する。
いまその歴史的瞬間がやってくる。
われわれはアメリカに対し、原爆の投下に対し、この民族的な感情を持ち続けることではなく、同時に報復するインテリジェンスの感情について新しい国際社会における自らの民族的体験で乗り越えていかねばならないだろう。
そして、表面的な現象としての国益とは自社の利益だ、と考える政治と経済のあり方を商人の損得によって行動してはならない。悠久の民族的対話の歴史を生み出していかねばならないだろう。
自民党の外交政策は破産した。いま歴史の新しいページを切り拓く時だ。
日本経済新聞 平成21年8月22日
日米地位協定
鳩山氏「改定も必要」
外交・安保で6党首討論
与野党の6党首は21日、テレビ東京番組の収録で、外交・安全保障政策を巡って討論した。民主党の鳩山由紀夫代表は日米関係について「オバマ大統領が対話協調路線に転じており、対等な日米関係を築けるタイミングだ」と強調。日米地位協定についても「基本的には改定も必要だ」と述べ、政権を獲得すれば、日米同盟の包括的な見直しの中で検討していく考えを明らかにした。
日本が米国の核の傘の下にあることについては「北朝鮮の情勢をみればやむを得ない。今すぐ核の傘から出るべきだとは主張するつもりはない」と語った。
麻生太郎首相(自民党総裁)は民主党が米国に核兵器の先制不使用を求める方針を示したことについて「日本と同盟を持つ米国に核の先制不使用を言うのは、日本の安全を考える上で現実的ではない」と述べ、北朝鮮が核実験をしたことなどを挙げて反対する考えを示した。
民主党は新しい国民大政党を目指すべきだ。
たぶん揚子江のこちら側から、揚子江のあちら側の岸は見えないだろう。比喩的に言っているが、民主党指導部の政党設立理念をしっかりとした思想的核として党内における勉強会を政策立案をとおして党員は学んでいくことだ。
自民党と公明党はわが国政権を担ってきた半世紀の謹慎期間があっていい。それは新しいわが国21世紀にふさわしい政党としての姿へと生まれ変わるまで逆転の少数政党として反省期間が必要だろう。まさしく政治のコペルニクス的転回だ。
野党諸党派は大同につけ。保守合同により自民党の結党は反自民の反対派により小異を捨て大同につくことだ。わが国自民党と公明党はいらない。
1998年、この不況はパラダイム転換の年であった。原理・原則・基礎・基本・ルール・手順・順序の新しい政治の風を起こす時だ。それは古くて新しい政治原理への回帰といえる。
佐藤にとって青春時代からバブル経済の崩壊まで地獄の時代であった。この期間中の成功の法則を全面否定し、いま新しい政治の時代がやってきたのである。
それはいかなる時代であっても、若者に夢を与えない時代は地獄の時代といえる。
古い時代の指導者は退場せよ。若者に夢と希望のある時代を生み出していけ。
自民党は戦後半世紀の政治を総括をせよ。しかし、世代の交代をもって新しく再生しないかぎり今回の衆議院選は過去自公政権の政治総括に注視している。まったくイロハの政治総括の手法すらもっていない。権力亡者になりさがり国民そっちのけだ。
新しい産業社会がやってくるだろう。まず破壊された国民生活を建て直すことが第一である。国民経済の内需を再生し、幅広い中間層の安定した層を育てていくことだ。
安全保障と外交はグローバル社会におけるわが日本国の存在理由(レーゾンレートル)をどのように求めるか?
佐藤も学生時代、まだ海外旅行の自由化が始まったばかりであったが、その時多くの民族の世界史の中でドイツ人、ユダヤ人、日本人のインテリジェンスに関心を持った。
なぜ世界の知性をリードしているのか? 漠然とした問題意識から見えないこころの道を探し求めた。
非哲学的な生き方は国家を危うくするだろう。国家建設の理念はここから生まれる。
経済商品、「政策」という名の商品政策はカネによる国民統治の手法でしかない。理念がないからだ。社会の閉塞感はここにある。国家がけして手を出してはいけない無思想による企業の統治と同じ傾向を持つ。国による公共政策のあるべき姿に帰れ。
北朝鮮問題は武力による対峙ではなく、わが国広く国民が求める世界平和を目指す平和外交に、どのような近隣外交の中で民族的ふれあいをつくり生み出していくか、中学生や高校生にもわかりやすい外交インテリジェンスの思想を創造し、外交を理論的に建設していくべきだ。
自公政権の体質といえる利害ある仲間意識――国民諸階層を分裂させた資本の論理の狭いセクト主義が今回の衆議院選の結果となるだろう。若者に夢と希望を奪った「政治的犯罪」がどこまで総括されるか。
大企業は一人前の自立心を持て! 国益は自社の利益と考える不道徳こそ、この国をどん底におとしいれた。プロ野球の民間商品に罪なき大衆を動かし、民間企業の「利益」にグルになって笑っているのは、国家の公共政策のあるべき一線を越えてはならない。国家政策と商人の間に一線を越えない「距離」を持て!
「けじめ」を持つことだ。この国を大掃除しなければならない。明治以来の大掃除だ。
愛するわが日本国の新しい再生なのである。
現代資本主義の進むべき道を求めて、直近の課題と未来の道について民主党の政治の課題は大きい。大国民政党として社会諸階層の知恵を吸収し、原理・原則・基礎・基本・ルール・手順・順序の公共政策に活かされることを期待している。自公政権の資本の論理による狭いセクト主義から大きく区別される。文字通りの民主主義国家として国民大政党を目指せ。
そしてこの衆議院選は新しい日本へと変わる時である。このパラダイムの転換が企業社会から政治構造へと大転換する時である。
破壊された国民の生活を政治のあるべき土台として公共政策があるべき姿に戻るべきだ。国民生活も再建の時でもある。
自公政権がもしこの政治総括をしっかり成し遂げ、自らを再生できるなら、しかし、古い政治家は退場せよ。商人の立場から公共政策に口を出すことは、その道徳と倫理が明らかでなければならない。民主主義政治はここに公共政策としてあるべき姿がなければならない。国益とは自社の利益ではない。
日米同盟から新しい日米関係へ、弁証法第一系列、理論的本質において世界の直近の現実的歴史的な望ましい姿として日本人の世界平和とのこころの距離感を理論系列においてわが国現実的歴史的本質として民主党は安全保障、外交政策として、思想として武装し、現実的な理論武装をしなければならないだろう。ゆっくりでいい。ゆっくりと構築していくべきだ。
うさぎのうんこのように国際的文民政策であってはならない。かつての大日本帝国陸軍のインテリジェンスを学べ。どのように日本国らしさを出していくか。大アジア諸国へ未来の国家建設に希望と夢を与えよ。
アメリカ合衆国の市民の60%は広島・長崎への原爆投下を容認している。アメリカ市民のインテリジェンスはいまだ古き良きアメリカの国家幻想を持っているのではないか?
わが国市民レベルの新しい国際活動という自公政権では積極的でなかったわが国市民の心情を伝えるべき組織的活動を反自民のレベルと市民レベルで、けしてイデオロギーとは関係なく、叙情の詩(姿勢)として被爆者の静かな叫びを各国へ届けるべきだ。
新しい政権が出来る新しいわが国らしい市民外交を展開せよ。
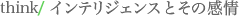
(この間、母の死があった。仕事を休むことはなかった。関西や北海道へも行ってきた。
忙殺されたが、本日短文を投稿します。今週中にもう一本投稿したいと考えております)
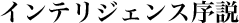
インテリジェンスの概要とその枠組みは既にホームページに投稿されましたが、それに対する「インテリジェンスの世界」としてこの概念の枠組みについて考えてみます。
インテリジェンスという概念には思い込みがあるように感じます。それを取っ払う意味で今回投稿の機会を持ち、このテーマにしました。
以前に投稿した「出版インテリジェンス(PI)とビジネスインテリジェンス(BI)のあいだ」を今回投稿分の最後に連結し、インテリジェンスとビジネスインテリジェンスの概念の広がりを描きます。
インテリジェンスに対する一般的な思い込み、思考停止など創造的なインテリジェンスの必要性について、佐藤の連関する問題意識としてここに描いていきます。
だからこのページの最後には既に投稿されている文章を連結させています。
わが国政治政策は単なる「政治商品」なのか?
――この社会の閉塞感、その原因はどこにあるか?
5月の下旬、NHK総合テレビが国会中継をした。
ここで石破農水大臣の答弁に気になることがあった。
佐藤も民間トランスクライバーの端くれである。農水相は農業政策について答弁中、言い直しともとれない、「商品」ということばを使って答弁を続けた。佐藤は企業社会にはいろいろな商品があるように、電子商品、健康商品、衣料品、食品など、大臣の答弁を「農業商品」というふうに聞こえた。
国会の速記者はこの答弁をどのように速記されているか? 大臣の言い回しなのか、言い直しなのか、言い間違いなのか、どのように速記されていくのか、NHKには当然VTRとして保存(記録)されていると思う。トランスクリプション(録音再生原稿)のあるべき筆記について、佐藤の求めるこの事実についての「国定速記録」について評価することができる。
国会当局がどのように速記者を教育しているか、速記はどのようにあるべきか、民間のトランスクライバーの端くれとして関心は高い。
国家政策が政治商品、農業商品であったり、もちろん安全保障と外交には商品など存在しないと思うが、わが国における農業政策は「農業商品」として石破大臣はとらえているのかどうか、自公政権に国家政策というものに理念のない「各種商品」として国民の血税を使って、こうした政治商品に群がる企業に対して「おもろいうまみ」を持つ国家政策としての経済合理的と考えるのか、どうか、各種商品に、群がるいわゆるエコノミストのアイディアかどうか知らないが、こうした不逞のやからからの政治政策の商品開発のアイディアを集めることが政権担当能力といっているのかどうか、わからないが、自公政権はたしかに政治政策(国家)に対する政治理念を失っている。
こうした疑問がある。
経済政策においても企業のおもろいうまみを隠して、各省庁のこうした背景に基づいた理念のない政治・国家政策が「商品として構想」されている。
現下の社会の閉塞感は理念のない「政治」から生まれている。
企業経営者やエコノミストの「商品開発アイディア」を募集(提案)して、それを国家政策だと言って国家建設の理念など何もなく、もはや国民に目指すべき国家像すら示さず、希望を持てる政治ではない企業が儲かる「政治」をすることが自公政権の目的ですよね。
自公政権は、佐藤の言う疑問を持つている。
政権担当能力なんか何もない。政治に理念のない政治政策にピリオドを打たねばならない。
佐藤のバカ息子をなんとかしなければならない
息子は私立大学の医療系学部にいる。作業療法学を専攻している3年生である。
いろいろ屈折してきたが理科系で受験し、「人間を相手に仕事をしたい」と言ってこの専門コースを選んだ。3年生になったこの春からリポートの提出が多くなってきたようだ。
先月5月下旬、久しぶりに3人で食事をした。そこで感じたことは、息子がゆとり世代でゆとり世代特有の甘えというか、野放しにしていたこともあって、佐藤は親としてなんとかしなければならないと思っていた。息子の進路、就職先、生涯の仕事として息子の今という時間と、進路、就職先、生涯の仕事を結びつけるには3年生になって自分のしっかりとした職業意識を育てる土台である「こころ」の養生が必要だと思った。自分の仕事に人間としての魂を持つこと、それは仕事のこころというか、自分の未来を描く土台というか、息子のことだから途中で挫折しないように独り立ちできる医療のこころというか、こころのいのちなんていう表現はないかもしれないが、3年生になって父親として希望するのは作業療法学を一生学んでいくこころを持てというか、「人間を相手にしていく」こころというか、それをしっかりと持つことが自分の一生の仕事を究めることにつながると思った。作家のように人間に関心を持てと言うことだ。多くは文芸や芸術から学ぶが、これまでの学校生活で屈折してきた。教師は学校教育でこころの感受性を育ててきたのか、「国語の技術」を教えられたのか? 息子が求める「生き方」を育ててくれたのか? 「文芸と芸術と自分」の関係に好奇心を刺激する学校教育だったのか?
そして、英語について毎日少しずつ勉強を習慣づけていけとアドバイスした。英書からどんなことを学ぶべきか? アメリカの最先端作業療法学を学んでいく力を持てということだ。バカ息子のことだから屈折があってもしかたない。
作業療法学の未来はIT環境と結びついた臨床工学や最先端医療ロボットを操作する医術と同等に比較されるような早稲田の理工学部で開発されているような最先端の作業療法ロボットも発明されるかもしれない。勉強の時間はまだ5、6年先まである。チーム医療の一員として人間性を養うことだ。
まず筋肉の働きの基礎を学ぶこと、アメリカの最先端医療情報に接すること、そうしたことを前提として、まず3年生のバカ息子に「医療のこころ」をしっかりと自分の本能にすることだと思った。
ゆとりの世代の子供たちは入社して2、3年で辞めてしまうだろう。どこでもそうだが、「今の働く現場」の土台にある魂というこころを育てていくことが、自分にとっても、社会にとっても必要なことだと思う。一本道だ。
これは脱線だが、家庭から離れて独り立ちしていく学生の息子にはどうやって自分の仕事のこころを養い、育てていくか、それは小社においても、日本人としても「医療現場」からの「仕事のこころ」を学び伝えていくことだと思った。現場から考えることを考える「思考(気づき)の泉」は医療のこころである倫理から生まれる。常にチームの一員ではあるが、独立した人格を養っていくには、世阿弥の「離見」に立つことだ。どんな専門分野にもここに学問的良心が宿る。バカ息子は中学生の時から平和主義者と担任の教師から言われてきた。やさしい息子(親バカの表現)だが、大学生活で養うことは、人格として独立できるこころを持つことだ。
小社の設立時の「会社案内」にイラストがある中扉があったが、佐藤は「ぼくたちの仕事のこころを伝えます」という一文があった。
これら一文はバカ息子にも読ませてあげたい。
今、社会に欠けているのは人を育てるとは一般的に「こころ」を育てることだ。この人生の道はサラリーマンの生涯か、起業への道(独立できる人格)か、その分かれ目はここから始まる。
ホームページを見て応募される最近の傾向
小社の仕事には出版業界という傾向がある。
ホームページビューを通して感じることは不幸にして失業中にあるか、最近の残業減による収入の減少で職を求めている女性もいるだろう。
本局ではこれまで一般公募、スタッフの紹介などを通して採用してきた。
小社のような仕事は一般的ではないと思うが、スタッフの紹介も少し変化の傾向をもってきたと感じている。大学入学にあたって推薦制度も一般的になってきて、裏口入学とはいわないが、堂々と正門から入る姿勢に欠けているのではないかと思う。
大学入試も就職試験も同じように理解される傾向にあると思う。本局のスタッフ採用も以前とは変容している。
小社は能力・実力・出来高制の在宅就業を土台とした生産関係で、就職すると仕事が与えられると思っているのかどうか、スタッフのご紹介は人柄や人間性に間違いがないと思ってきた。しかし、一般公募では人柄や人間性は応募の指定のテーマで作文をお願いしている。まずお人柄や人間性を見ている。仕事をしなければ能力・実力は測定できない。
一面で学歴が一定のレベルを期待しているが、こうした思い込みを持とうとは思わない。
30代や40代になってもいわゆる偏差値を抱えている人もいる。
大学卒業以来、どんな勉強や教養を自分の生きるテーマとして学習してきたか、佐藤の過去のサラリーマン生活においても自分の研究テーマを持って働くことは難しい。
やはり大学生活の中でどのように生き、学び、大学生活を送ってきたか、その人の基礎知識資産は大学時代の学習生活の中で蓄積されているはずだと思う。4年制大学とは自分の生きるテーマを求めていく場であり、生きるテーマを持った「就職先」をみつけて会社生活を送っている人もいるだろう。
小社ホームページはリクルートのための目的であったが、訪問者のページビューを見てみると生きる目的がなく、一般的に「就職先」を探しているのかどうか、そして「大学入学推薦制度」のような方法で「就職」を目的とした考え方が広がってきていると感じる。
結局今の小学生のように自分の未来はサラリーマンになることだと、そのための学校教育制度になってしまったのか、資格取得はそのためにあると思い込んでいるのかどうか。
佐藤のことばで言えば、「自分はどんなふうに生きるのか」というこころにいのちのテーマがないと思われる。極端に言えば、「自分はこう生きたい」とこころに夢や希望の信念を持てば、自分で、自分の力で、生きていく以外に自分は生きる道を拓いていけない。
こうした気持ちが自分の中で充満してくるのは、40歳を過ぎて自分に責任が持てる歳を自覚できて、はじめて自分は自分になることができる。極端にいえば、「金儲け」などと軽がるしくいえないし、それでは多くの人から信頼されて生きてもいけない。金儲けが人生の目的だという人もいるだろう。それはそれで金儲けが自分の一定の成果を自覚した時、社会的貢献という人間の生き様も生まれるだろう。そうなっているだろうか。
佐藤は知的な生き方を求めている。金儲けは不得手だ。資産運用にも関心はない。
生き方はいろいろあって自由だ。しかし、どんな自分になりたいか、今それが見えない人が多くなったような気がする。画一性を破る人生があってもいい。
佐藤の今は、会社設立にあたって社名を「佐藤正明事務所」という名もあった。しかし、構想は現在の社名になったが、私的企業ではあるが、社会的に存在し、集うスタッフと共に共通のことばで企業の事業としての目的を持っていこう、と決意した。自分の姓や意味不明な社名よりも事業理念を掲げて起業した。これは一般的にいえば、人間の生きる志といえる。給料生活者のような与党政治家、サラリーマンエコノミスト、サラリーマン大学教授などなど、そんな生き方を求めたのではない。
結論としては自分はどう生きるか、自分の生きる希望や夢をぶつけてみろ、と言いたいのである。
ビジネスインテリジェンスの世界――民族の歴史と、生活と文化(理性)
税務経理協会刊『知識情報戦略』石川 昭・中川十郎編著(平成21年2月10日初版発行)を購入したのは6月17日だった。パラパラめくって見た。わが国においても「インテリジェンス」が防諜として理解している人が多いと思う。この「仕事場からの声」に2008年5月「出版インテリジェンス(PI)とビジネスインテリジェンス(BI)のあいだ」を掲載した。この部分をホームページの掲載位置から削除し、このテーマをここで再編集して連結しました。
インテリジェンスをどう把えるか、現在この書籍が概略を語っていると思いますが、思考の枠組み、「インテリジェンスの世界」について今回はテーマとします。みなさんは自由に思考を膨らませ、自分に適用されることを望みます。
業種、業界、各企業にインテリジェンスがあります。インテリジェンスはいわゆる暗黙知ではありません。きわめて各企業の各事業の、あるいは起業として出発する場合も意識された理性として気づきが戦略的に体系化されているもの、たとえばあなたの会社の営業を例にとりましょう。ここには経済活動の意味――そのすべてがある。
営業政策として理性として止揚され、営業マンとしての企業独自の研修システムで育成された営業マンという人材、それはきわめて理性として確立された営業政策という事業方針に基づき展開される戦略としての把握、それをここでは営業インテリジェンスとします。
防諜という意味ではありませんが、この書籍で取り上げられている各事業分野の独自のノウハウともいえるし、あるいは業界の一般的な傾向をインテリジェンスの土台として、その上に業界や企業の新しい動きなどをヒントに独自のわが営業部のインテリジェンスとして構築していくべきもの、インテリジェンスの大切な確信となるのは知識資産として蓄積している哲学的な土台から、この独自のインテリジェンスが構築されていくと、それは他社の真似のできない、発想の哲学的土台をブラックボックスとして、防諜されても他者に移転されないインテリジェンスとして確立できる。
国であれば民族性とその歴史の蓄積、文化として形成、民族の特有性と知恵から根ざしている。
例として、そこにはインテリジェンスの軍事インテリジェンスと国際協力のインテリジェンスの視点から見ると、最近までのアメリカ政府による軍事インテリジェンスの潮流と、かつて旧日本軍の「軍事インテリジェンス」の伝統が、わが国特有のインテリジェンスの傾向だとする。もちろん、こんにちでは国際協力においてわが国独自の文民による「治安の安定」に貢献する国際協力のあり方もあるだろう。インテリジェンスは国家インテリジェンスの国際戦略として21世紀アジアへの国家インテリジェンスとして構想しなければならないだろう。
ひと言余計だが、「同盟」共同幻想をもってアメリカ軍事インテリジェンスにくっついていくことが現実主義的であると政治学者が考える戦後政治学の潮流に、わが国の民族的な知恵のかたちとして独自のインテリジェンスをもってグローバルな世界で国連の立場を尊重し、わが国が世界から期待される国家インテリジェンスの創造が民族特有で伝統あるわが国の立場を創造し、政治学者が考えるかつてのものと異なった新現実主義的国家インテリジェンスのあり方に活路を見いだし、21世紀のグローバルな世界のあり方を求めて国際的な諸問題の解決に向けたパートナーシップを新現実主義的に捉え、国際協調の新しいあり方を創造する国家インテリジェンスの新たな創造を考えることにも、自由な発想があっていい。ここではインテリジェンスには自由な発想で創造的に取り組み、新興国や後進国との信頼を生み出す努力が必要だろう。
この一文は「インテリジェンスの世界観」というものを十分理解し、みずからの日常の仕事に活かすビジネスインテリジェンスとして真のわが国企業風土の新たな創造を提案している。今アメリカから輸入したビジネスインテリジェンスの直輸入は硬直した企業風土の知的貧困以外のなにものでもない。佐藤はここでわが国が陥っている思考停止症候群を危惧しているのだ。
この文章は本来なら十分な議論と推敲が必要だろう。佐藤が言いたい問題提起をご理解いただき、インテリジェンスに対する思い込みを取っ払うことが目的である。
みなさんの会社の営業の歴史から何を後輩に伝え、どのように訓練し、人材がどのように知恵や気づきからノウハウを生み出したか、表面を真似しても哲学が捨象されているため仏像つくって魂入れずの「力」になることはできない。力とは理念の働きだ。真の強さはこうした伝統の歴史と文化から生まれる。
こうした点でビジネスインテリジェンス(BI)は総合の科学といってもいい。
この書籍では「ビジネスインテリジェンスからナレッジサイエンスへ」と副題がついているが、ピーター・ドラッカー先生の著書を学んで思うことは、先生には哲学があり、インテリジェンスを「評論」しても「サイエンス」は一点突破の全面展開にはならない。
そういう意味でインテリジェンスは固有なものである。
多様な人間社会史の今を経過しているが、理性の高さはその人の固有な人格のように見えるし、真似もできない。職場に卓越した営業マンを事例として学ぶことができても、真似することはできないだろう。それは前記のノウハウにしかすぎない。哲学を真似することはできないからだ。
インテリジェンスを技術的に把えてはならない。数学的に把えてもならない。理念の力には倫理・哲学がある。顧客のこころの信頼を得るとはどういうことか?
前述の国家政策が経済合理性によって「商品政策」として政治が行われているが、近代経済学者は資本の論理といえる経済合理性で「顧客のこころの信頼を得る」ことができると思っている。政治に期待しているのは「各種商品」ではない。ここには理念というインテリジェンスは皆無である。早く気づくことだ。政治とは国家建設のビジョンであり、理念の総合の科学で市民(庶民)の一面的な経済活動の側面だけではない。政治と経済のあり方はどうあるべきか。政治のあり方まで近代経済学者が口出ししている近代経済学の本質が、経済システムと国民が望む政治システムとの乖離を示している。理念ある政治としての民主主義の実現と資本の本質が衝突しているのである。市民を犠牲にして資本の自由を求める社会的あり方に哲学的修正を政治が求めるということに独占資本の力の増大がその国の国家体制を巻き込んでいるところに現代政治の危機があるのだ。
この著書から概略を学び、思考を自由にして自分のワークプレイス(仕事の現場、生産現場)の知識を深め、武装していくことだ。つまり自分を知ることもインテリジェンス構築の核心部分だ。知恵は知識を生み出し、力を生み出す。
もう一度言うが、思考すべきインテリジェンスの本質、備わったその形式、そしてインテリジェンスの働きを戦略的(概念化)に求め、しっかりと目的に集中することだ。
よくある営業のくだらん研修会は中学校か高校の教師の授業と同じだ。
営業において自分のこころが正直・率直・誠実、個性をもってのびのびと常に学び、多くの営業研修を否定してそこに自分の生き方(生き様)である自分の営業のあり方を自己体系化することからあなたの営業インテリジェンスは生まれる。それはその分野の自己知識の戦略的自己体系化なのである。組織と個の関係は「仕組み」(律法)として止揚していく。ソフトノミックス(ソフト化経済)とはいわゆる暗黙知によるアイディア商品とは全く異なる。理念から生まれる科学技術による商品化といえる。
現実的・歴史的本質である生産現場での気づきを理論的本質(科学的知見、あるべき姿)の検証によって生み出され実践的本質(実証・新事実・目標)として生み出される。科学的知見を発展させる。組織においても個人においても「引用」は単なる評論にすぎない。組織も自己も現実的・歴史的本質から「自己の論理の発展」が生み出されることのほうが多い。一般的に自分たちと、働く自己の現場を学べ! と言うことだ。
インテリジェンスは「感想」の日常性からは生まれない。その通り意識せる理性から生まれる。哲学的には自己完結だ。佐藤にとっては人生とは禅の生き方だ。生き様だ。
場をかえて、と思っていますが、世間では死生観と考えているようだが、佐藤にとっては生き様だ。法案を審議する国会議員のドナー提供者が「予約」されている。自分の生き様を示してみろ。
佐藤の「希望の原理」は禅の生き様だ。
戦前、母だった高齢者も自らの子を失った悲しみを抱えて生きてきただろう。失った兄弟姉妹もいるだろう。忘れることはできない人生だったろう。アフリカの母の悲しみも想像できる。ベットの上の親や兄弟姉妹、子どももいるだろう。でもそれは、いま人間の生き様を語っている。
悲しみを抱えた母は語らない。西欧哲学と禅は対話しなければならない。禅は生き様をとおして自己完結する。日本精神の中にこの禅の生き様がある。
日刊工業新聞に連載された「危機を乗り切る知識情報戦略」が平成21年5月12日第1回連載が開始された。「インテリジェンス」の枠組みが描かれた。
日刊工業新聞 平成21年6月9日(火)
情報重視経営の推進を中長期的に戦略策定
危機を乗り切る知識情報戦略⑤
新ビジネス創出と情報活用
■理論と実例
最終回の今回は世界金融・経済危機下、激化しつつある国内外の競争に対処するためにビジネスインテリジェンス(高度経済・経営情報)を新ビジネス創出にいかに活用すべきか。理論と実例を参照しながら論じる。
ビジネス開拓のためには高付加価値情報のビジネスインテリジェンスをどのように分析・活用するか。それには日ごろから内外の関連情報に対する感度を研ぎ澄まし、情報収集のためのアンテナを張り巡らし、入手した情報を迅速に効果的に活用することだ。以下、情報の質を高めるためのインテリジェンスサイクルの手法を紹介する。
①まず情報収集の戦略目標を定める②戦略・戦術策定に必要な政府、産業、先端技術、競争相手の情報を収集する③収集した情報を評価、加工、編集する④これらの過程を経て情報の価値を高めたインテリジェンスを徹底的に分析する⑤この付加価値を付けた高度経済・経営情報・ビジネスインテリジェンスの分析の成果を戦略決定者に迅速に伝達する―。以上の5段階をサイクルさせることにより、さらにインテリジェンスの有効性と効果を増大させる。
情報は①公開情報(Open Information)(新聞、TV、インターネット、書籍、資料など)②私的・人的情報(Human Information)③秘密情報(Secret Information)の三つに分類される。このうち、ビジネスにおいては①と②を活用する。③の機密情報には決して手を染めてはならない。企業倫理上もコンプライアンス、企業の社会的責任(CSR)上も企業機密を盗むことは厳禁すべきだ。筆者の30数年の商社時代の経験を基に公開情報と人的情報活用で新規ビジネス開拓に成功した事例を以下参考までに例示したい。
■人脈を開拓
(1)アジアに駐在時代、現地の新聞で医薬品原料が足りなくなっているとの情報を入手した。早速、日本本社化学品部に連絡。他社に先駆け、ペニシリン、ストレプトマイシン、ビタミンAの原料を現地輸入公団にオファー。日本製医薬品原料の大量初輸出に成功した。このビジネスはその後、長期にわたり継続した。上記の情報活用のケースは現地新聞の公開情報を活用して成功した事例だ。何げない日々の新聞情報も、鋭敏に収集し、迅速に活用すれば大きな商権に成長する好例である。
(2)南米駐在時代、得意先が南米のある国で近く乗用車輸入を解禁するとの情報を持ち込んだ。直ちにこの情報を本社自動車部に通報。1年の交渉後、4万台という日本車初の南米向け大量成約に結びついた。このケースは私的・人的情報を迅速に本社に通報。得意先情報を有効に活用した事例である。人的情報を得るためには日ごろから、人脈をマメに開拓。有効情報の入手に努力することだ。
この二つの事例では新規ビジネス開拓には特別な秘策があるわけではない。日ごろから、地味にこつこつと人脈を構築すること。併せて新聞、テレビなどからもビジネス関連情報を集めること。情報を迅速にビジネスにつなげる感性と意欲が大切なことを物語っている。
■世界を制す
情報分類としては、ほかにも戦略策定に活用される「戦略インテリジェンス」。戦術確立に有効な「戦術インテリジェンス」。さらに「マーケティング・インテリジェンス」。「ファイナンシャル・インテリジェンス」。「技術・パテントインテリジェンス」。カナダの情報研究者が考え出した「イベント・インテリジェンス」。米国の中央情報局(CIA)の手法をビジネスに応用した競争情報「コンペティティブ・インテリジェンス」。ぼう(ぼう争)ちよう(ちよう))を主とする「防御的インテリジェンス」。戦略的、戦術的に情報を活用する「攻撃的インテリジェンス」などがある。
元米国情報評議会副議長ハーバート・マイヤーは情報を加工し、活用する「情報製油所理論」と、それらの高付加価値情報を基に企業経営を行う「情報レーダー・コックピット論」を唱えている。これに対して、筆者は情報の付加価値を高め、効率を増大させる「情報水力発電所理論」を提言。「グローバル企業の情報組織戦略」(筆者共訳)の著者ベン・ギラード博士は情報を濃縮する「情報濾過理論」と情報の価値、効用を監査する「情報監査」の重要性を強調している。彼は「パソコン、インターネットに象徴される21世紀のIT、情報時代は、一面で情報洪水の時代でもある。だが真のインテリジェンスは砂漠の状態にある。だからビジネスに役立つ情報の収集、インテリジェンスの活用が21世紀の情報革命時代の企業の死命を制する」と喝破している。
知識主導の世紀を迎え、しれつ(しれつ導)な巨大グローバル競争を生き延びるためにはビジネスインテリジェンス、知識情報の活用と実践が強く望まれる。かかる情報戦略の時代に対応すべく企業組織に設置した国際諮問委員会や国際戦略研究部門、経営企画部、業務部、さらに情報企画部、リスクマネジメント部などを全社的に強化している日本企業もある。これらの組織を通じ、経済、産業調査、さらに激変する国内外の環境変化の迅速な調査・分析を行い、その結果を経営陣、営業グループトップに伝達。中長期的な経営戦略策定に役立てている。
激烈な国際商戦はつまるところ国際情報戦でもある。グローバル競争を勝ち抜くために、なお一層の情報重視経営を進めること。これこそが今次の世界金融・経済危機を乗り切り、企業が生き残るための知識情報戦略だ。今まさに情報を制するものがビジネスを制し、世界を制する時代が到来している。
(おわり)
中川十郎
日本ビジネスインテリジェンス協会会長、日本大学大学院グローバルビジネス研究科兼任講師、元東京経済大学教授
出版インテリジェンス(PI)
とビジネスインテリジェンス(BI)のあいだ
出版インテリジェンスの手法
voice-transcriptionをDNA(デオキシリボ核酸)になぞって、それを物象化(科学的連想)して考えてみると、発現(expression)して初めて意味をもつという。発現には転写(transcription)と翻訳(translation)の二段階があるらしい。
voice-transcriptionは第一稿・草稿の意味にしかすぎない。DNAだけでは情報の塊(プログラムなど)としてしか存在意義はないが、状況に応じて必要なものを選び、それを適当なかたち(from: 姿として現れ出る=outwardされる=RNAを経てタンパク質として)としてoutputすることで意味をもつようになる。この転写後の過程をスプライシングsplicing(もともと「フィルムやテープを編集する」「より継ぎをする」などの意味)と呼ぶらしい。成文や作品にもなる。もちろん母系の遺伝子ミトコンドリア(mt)といえるディクテーター(談話者)の転写されたテクニカルタームやコーパスcorpus=collection of written or spoken textsは、独自のDNAそのものといえないか? 著書の遺伝子が正確に転写される。voice-transcriptionはそれ自身をどのように発展させていくか、コーパスから何を選びどのようにoutwardするかはプログラムされておらず、それ自身が非常に重要な意味をもつ、と。ある意味で身体の組織は社会システムの体系として物象化している一面もある。そして偶然のアイデアや思いつきはトランスクリプションのすばらしいヒントを含んだ本質なのだから。DNAの理論に基づいた可能性を生み出す意味で翻訳よりも転写が重要で、その本質は二段階なのだ。
この文章はホームページの「ごあいさつ」に使用しました。
2003年(平成15年)宣伝会議の『マスコミ電話帳』の広告内容として執筆したものですが、平成14年の8月頃に書いたものです。これはインテリジェンスに関する理論的背景の正当性を証明します。
出版インテリジェンスは出版企画に基づく編集者の短期間の集中取材によってコンテンツ(書籍や雑誌記事)としてまとめられ編集されている。
最近では佐藤 優先生の『インテリジェンス 武器なき戦争』(手嶋龍一・佐藤優 幻冬舎)があり、インテリジェンスとして扱われました。
アメリカにおいてビジネスインテリジェンスとして主にIT業界で活用され、日本に上陸し、大企業の7割が導入されているようですが、その活用が十分ではないというのが課題となっているようです。
ここではインテリジェンスを一般的に概念として把握し、それをどのようにBIとして適用していくか、また出版業界における出版インテリジェンスというべき取材方法などのドウハウを参考にビジネス分野でどのように活用していくか。特に一部企業の活用の積極性を評価しながらビジネスで、企業内部でどのような活用のあり方が望まれるか、ビジネス創造の方法として考えてみたいと思います。
それはディクテーションの活用で社内会議などに適用することにより、自社の企業目的をビジネスのインテリジェンスの創造に結びつけるものです。自社の業務(部門の働き・機能)を列挙し、その働きに結びつけて整理してみるのです。
これは佐藤のメモですが、
(マネジメントの)インテリジェンスの本質とは最新知識の創造であり、企業戦略や戦術の創造です。
一般的にはインテリジェンスの形式として機関(知識装置)、大学、研究所、出版社、エージェンシー(部や課)
インテリジェンスの要素として理解できる力、思考する力、気づきの力が現象(モノ)の働きを生み出す(思考する)
そしてインテリジェンスの目的
日刊工業新聞の報道で知ったのですが、産業技術総合研究所の打ち出したシンセシオロジー(構成学)の新概念の発想は、60年安保闘争のときの問題意識と同等と考える。
しかし、日本人のいわゆる特異性から脱出することができるのか。スピノザの『エチカ』――論理学――から出発できる哲学者が必要だ。いわゆる構成学は「第2の科学」でもなんでもない。それは人間の哲学に基づいていなければならないだろう。技術と人間の二元論は日本人の特異性を特徴づける。ここに技術者の頭の中に技術哲学と論理がないのだ。どこからモノづくりの発想が出てくるのか? 特異性はここから生まれる。しかし、問題意識が近づいてきた。そして「気づきの力」とは縦横に飛ぶ思考の反射だ。
本質・形式・要素(働き)・目的をヨコ軸に分析項目をタテ軸にとり、情報の集積からビジネスインテリジェンスを抽出できるよう整理してみよう。「本質」でも「要素(働き)」でも英語で考え、英語のこのことばの働きをヒントに具体的に考えてみよう(「放送リポーティングの進め方」参照)。
BIはどのような立場から情報を収集するかによって、部門の働きの目的が描けます。
既存情報(情報収集)を整理しても物質的な力の働きを新しい目的として活用しきれない。ここではコンプライアンスが重視される。それが活用されていない原因でもある。
みんなと同じことをした「情報の集積」はみんなと同じ結果になりやすい。傾向が似かよってくる。他の分野への適用がありうるかもしれないが。
みんなと異なる「情報の集積」は異なる結果が系統的に収集され、ここから抽出されるインテリジェンスにより異なった発展が期待される。
出版企画においては、企画目的を前提に著者から情報を収集し、その取材によって得られる情報のいくつかの要素が目的への働きを生み出す。こうしてコンテンツとして成立していく。どのように取材するかは編集者の現象に対する理解できる力、思考する力、気づきの力が取材という働きの「性能」で品質が決まる。そこには情報(インテリジェンス)のもつ種類(形式)としてどんな分野か、その分野で働きとしてどのような要素(力)があるか、インテリジェンスはどんな目的をもっているか。
最近の出版物のつくり方に気づきの力を与える書き方の工夫が必要だと感じる。考える力や気づきの力をヒントとして与えない文章の書き方となっているのではないかと思うときがある。佐藤にも声なき声として噛みくだいてやさしく――それは思考の停止を前提としているかのように、そうしなければ現代日本人には伝わっていかない思考停止症候群になっているのではないか。ひと言いわなければ「わからない」日本人が多くなっている。
ビジネスインテリジェンスの手法
大企業の7割が導入しているといわれるビジネスインテリジェンス(BI)は企業データ(顧客情報の集積)の分析と活用のことで――企業システム、webシステムを活用して顧客の実態を調査し、商品開発や営業でいかに活用していくか、その知識(インテリジェンス)をいかに生み出していくか。
先日ある大手銀行の、いわゆるBIが個人情報保護法に違反するのではないかということを本局はみなさんにweb「営業情報」でいいました。それはアンケート調査の域を出ないものでした。しかし、アンケート調査として公開していない企業内部の個人のデータに基づくものであった。手法として問題のあることを指摘している。
ドラッカー先生のマネジメントの新しい活用の方法を考えてみます。
本局でもお客に役に立つマネジメントを考える必要があると思いました。
これはまだ試論の段階ですが、みなさんに佐藤の問題意識を出してみたいと思います。
ドラッカー先生のマネジメントの基本は、マネジメントとは務め、責任、実践、それがマネジメントの本質だといっています。
佐藤の考えたドラッカー先生のマネジメントの起源は、パートナーシップの起源と同じだと思います。夫婦で、務め、責任、実践を役割分担していく姿です。
人間社会の歴史の商品生産の起源は、当時は食べていけることに基本があったと思いますが、知恵や気づきの力をもって商品の価値を生み出していかねばならない人間社会の歴史でした。
商品価値が高まれば貨幣とより多く交換でき、またそれは所得の増大に結びつきました。
マネジメントの起源とはここにあると思います。夫婦が協力し合って所得の増大を目指していく経済活動に焦点をしぼったのが、企業の始まりです。手工業から工業化へと進みました。何人か、あるいは集団で経済活動を進めていくことの効率を求めて成果を上げようとしてきた歴史(延長の永続性)です。
こんにちでは知識産業社会を目指して本局ではパートナーシップによる効果を求めて成果を生み出そうと努力しています。この全体をマネジメントといいます。
社会の多様な組織(病院・自治体・NPOなど)にマネジメントの形式(種類)があります。
経済活動にしぼったマネジメントとは企業の特性です。
しかし、企業の個人的な思いがwebの情報を利用するというのは企業自体の利己的な活用であって、真に顧客の役に立つインテリジェンスと言えた時に、顧客との共有ができます。どのように顧客に奉仕していくか、そこにインテリジェンスの真価がなければならないと思います。
企業のインテリジェンスの「精神」は花咲かじいさんになっているか、意地悪じいさんになっているか、「社員」の活用が十分でない理由は社員の良心が原因のように思います。
顧客をカモ扱いにして利用しようとする考えは、否定されなければなりません。顧客に真にお役に立った時、顧客から支持されるインテリジェンスでなければ真のBIといえません。たとえば買わせるように仕向けるとか、企業の勝手な独断はマネジメントではありません。
web上のデータを共有して、真に私の仕事は顧客に役立っているか? 誠実さがあるか。仕事に対する考え方がこんにち、資本の論理によるゆがめられた考え方として広がっていると思います。
それでは顧客とのパートナーシップの信頼をえることはできません。
どこか佐藤の考え方と違うものを感じるのです。夫婦二人の家庭が、あるいは家族が、周り(地域)から信頼をどのように獲得するかという視点がずれているように感じるのです。
長い目でみると、信用を得ることはできません。
マネジメントの原理、ドラッカー先生をいくら読んでも理解できない人が多いと思います。ここでは企業の経済活動、豊かな社会、市民社会にあっては、その前に人間としての生命活動があって、そのひとつが経済活動です。しかし、経済活動の原理がちょっと佐藤と違うのです。市民社会を構成する一つに企業社会があると考えるのが、佐藤の立場です。
極言すれば儲けることが先にあるのではなく、信用をいただくことが基本でなければ会社としての永続性は失われます。それがマネジメントの目的です。最近では知識の深さや正確さが顧客(編集者)の信頼を得て、仕事がその人にくっついてこなければ、その人は信用(マネジメントの働き)をいただいているとはいえません。
パートナーシップは個人に分解されます。自分は会社の一員で、自分の間違いは次工程の誰かが負担してくれると考えたら、あなたに仕事はくっついていきません。
夫婦の努力もお互いに認め合ったら、対等な立場になるでしょう。パートナーシップの原理は本来対等であることです。その上で次工程はお客様です。
全員、平等です。しかし、こんにちマネジメントはパートナーシップに更に時代性と現代性をもつ概念になったように思います。市民社会における企業としての役割が大きく深くなったからです。顧客がより便利となるよう最新の技術を取り入れ、経済活動に務めて責任と実践を繰り返して価値を更に生み出していかねばなりません。ここに使命であるマネジメントの目的が永続性を生み出していくのです。
こう考えると、BIは他社の概念とはまったく反対の概念になります。
務めるということの顧客に対する誠実さがあってこそ、務めは再生産へとつながっていきます。
たまにみなさんの仕事が再生産へつながっていかないこともあるかもしれません。本局では長い目でチャンスをつくりたいと思っています。それはこの円高・材料高で仕事が不況で減少し、競争は激しくなっています。ベテラントランスクライバーに仕事が集中していますが、拡大再生産へとどう結びつけるか、こうした中で、仕事のチャンスをつくっていかねばなりません。
みなさんの気づきが実はBIのもっとも大切なインテリジェンスです。
心のないIT技術はかえって企業のインテリジェンスにとってマイナスです。
コンプライアンスを無視したマネジメントは企業として信用を失っていくことになるからです。
ビジネスインテリジェンスはマネジメントのあり方、企業の個性を出していかねばなりません。
(2008年(平成20年)4月24日「営業情報」に投稿、それに加筆、訂正しました)
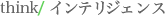
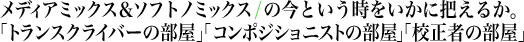
山へ登るスタートの道はいくつもあると思う。
しかし、佐藤は「正道以外安易に人様の真似はするな」と考えている。
自分の立つ線路はどこを目指しているのか、ここに添って気づきを工夫・実行してみよう。自らの知で「道のない道を生み出して」いくのだ。論理的に組み立てていくには方法論がある。弁証法と論理表現形式を活用して構成していく。みなさんは知識労働者としてこれを意識し、知の創出が組織の力となって全員で共有してこそ、それは知識と技術を伝承していく力を生み出すことにつながる。人づくりこそ企業の力となっていく。人づくりこそ企業の生命力だ。けして「利潤最大化」や「規模の拡大」ではない。スタッフ全員の誠実な努力による知の創出によって原稿の品質の向上により、自分にとって仕事はくっついてくるものだ。仕事がくっついてくればお金もくっついてくる。自然と企業は成長していく。会社設立以来「相変わらず」だ。小社も社会の風潮の考え方の影響を受けているのは例外ではない。分かってもらうよう努力している。
佐藤は学生時代の経験として、学生運動において早稲田型の大衆運動を目指しているのではなく、つまりある優秀なリーダーが大衆を動かすのではなく、思い込みを排し、普通の気づきで東大のクラス討議型による全員で討議し共有できる知の集積を通して、ある一定の論理的で理論的な成果を求めている。そういう意味で組織の歴史の知であり、みなさんがここに集まり散じていくとしても、これを常に意識した前進の成果を勝ち取っていく姿を考えている。それは線路の終着駅を見ているのではない。ひと駅ひと駅のプロセスを経て終着駅へたどりつく。仕事という一品料理にこころを込めて、それを毎回続けて仕事は自分にくっついてくる。
そういう意味でこの線路はそのルールに従い、正なる鏡を常に学び、吸収し、自分と照合し、その目指すべき正道を切り拓いていけと思っている。思い込みを拒否する。自分で考える「あるべき姿」に忠実であれば個性ある普遍的な理論として発展できる。
常に学ぶということの習慣は原則に従う、いろいろな場面に出会うだろう。頭の中を弁証法で整理して作家や著者の雑誌記事や文芸、その他の成果として、それを「事例」(見本)として現実的・歴史的に把え、そして次に理論的側面で、一般入門書というか、あるいは例として中学生の教科書を参考に各専門職の骨格を描き、枠組を再構成し、内容は骨格をつくる意味で瑣末(さまつ)なことだ。多くの人は誤解している。瑣末なことを思想としての骨格を描くことは、単なる遊びの知識で身につかない物知りとなってしまう。専門書の入門書を基本テキスト(教科書)で概論として学ぶ。
一般企業の労働者と異なるところは、マニュアルを知れば自分の仕事ができると思い込んでいる思考停止症候群に陥っている。気づきや工夫や改善のこころを失ってしまう。
常に歴史とは人間の気づきや生きる知恵で未踏の知識を開発することである。
知を再構成していくには、まずこうした土台を持ち骨格を求める。そして、その骨格に合わせて知や肉としてこの骨格を豊かにしていく。
自分たちの道である軌道をつくって、それはいろいろな書から学び、経験し、体現して学び修正し、正道を求めていく。
そして、もうひとつ大切な視角として、ヒューマンエラーの歯止めを組み込む形式の確立が必要だ。
今朝(平成21年5月6日)日本経済新聞は「ウォール街は感染症のような貪欲(どんよく)」(グリーンスパン前米連邦準備理事会議長)で暴走し、……必要なのはアニマルスピリットと自己規律をバランスさせる知恵でもある」。奇妙な性悪説と性善説のモザイク論理だ。エコノミストに解決できるだけの頭に論理性はない。「正しい利益」をこうしてバランスで求めるのか? 小沢一郎氏の検察のあり方に民主党は企業献金の法規制を提案している。このモザイク「論理」では資本の懲りない暴走が再燃するだろう。19世紀の商人の生き方ではなく、ルネサンス(人間復興)で学んだ人間(こころ)性豊かな、知識が道具ではなく、こころが伴った知識で、このモザイク「論理」のバランス思考ではけしてないことに気づくべきだ。知性のあり方に行政も裁判にも注視している。
論理は一貫していなければならない。モザイク思考は論理(法哲学=形式)とは言わない。こういうのをめちゃくちゃというのだ。自己(社会)分裂をおこすだろう。思考には原理・原則・基礎・基本・ルール・手順・順序がある。こうして法の精神である律法が生まれる。資本の暴走が再発されるだろう。社会正義のない民族と国家は亡びる。論理とは人間の知の力(働き)だ。
ここには学ぶということに対する愛――学ぶということにもし退屈があるなら、佐藤の存在は無益な存在だといえる。これは学校教育や職場教育でのいわゆる教師や技能者にも通ずる。企業の社会的存在としての社会への貢献へのこころがここにある。
佐藤にとっていわゆる専門職大学院は無益な存在である。マニュアル社会でしか生きていけない社会を描くことは人間の生きる知恵を捨象した社会の停滞と閉塞感を生み出すだけで、歴史は長期停滞を発現し、それは広くいえば、人を育てることもできないし、新たな知を生み出すこともできない。ぼくたちは未踏の分野の知を生み出していこう。そして、人を育てるために学ぶことの愛をもとう。企業のイノベーション(革新)はこうして生まれる。逆説的な正と負のコペルニクス的転回が必要だ。知に対する愛でもある。
メディアミックス&ソフトノミックス/とは知を生み出す現場にいる。物質(マテール)としての現実的歴史的な現実、現物、現場の3現にいて、すべてを受け入れ、すべてがここから出る。仕事は入って出て行くが、蓄積しているのはカネではない。湧き出る気づきであり、学ぶことに対する愛だ。談話(ことば)と執筆(論理)の「時代の元番地」にいる。
それを丹念に収穫しよう。知をいっぱい蓄積し、形ないものに論理を与え、集まり散じたとしても、後輩に伝えていこう。それは何人も自己の成長である生きることの真の生産的価値である。企業のゴーイングコンサーン(企業の永続性)はここから生まれる。
ぼくたちはこの毎日の仕事としての現実・現物・現場から学び、ここがぼくたちの常なる出発点である。生産的労働の常なる出発点である。
佐藤もできるだけみなさんの投稿に気づきをもって成果を王道に導いていきたい。
こんにちの大企業の企業組織では正なる知の創出は絶望的だ。だが、みなさんの学んでいくことに対する愛、多くは無償の愛になっているが、評価をみなさんの生産的労働に結びつけていきたい。知とはもっとも尊い、評価されなくてはならないもので、お金のことは一般社会のようには関心はないが、みなさんには適時的確に評価していきたいと思っています。
仕事とは本来、マニュアルだけで行われるものではない。アメリカの企業社会は誤解していないだろうか。知もトップダウン型で佐藤は否定的な見解をもっている。
前述したように、マニュアル社会というか、いわゆる専門職大学院も含めて、それは知の長期停滞を生み出し、社会の閉塞感を生み出し、いいことは何もない。
ぼくたちはこのマスコミ出版業界でマニュアル社会を破壊し、知を生み出す現実的で歴史的な本質である現実、現物、現場の3現に依拠し、すべてを受け入れ、すべてを出して、その気づきを成果として、いくつもの原稿から原稿づくりを事例として出し、それをみんなで学び、方法論として実践的に適用し、知(知識と技術)を蓄積して、そして知識産業社会の建設へ向けて、ぼくたちの精神(知識・技能)であるこころと、その組織文化を豊かにしていこう。顧客のために何ができるか生産的価値をつくり出していこう。
最近、音声ファイルとカセットテープでの入稿の傾向を示しています。時に録音機能付ケータイ電話、デジタルビデオカメラ(DVD)もあり、クラウドコンピューティングを適用した原稿づくりへと進化しています。メディア媒体の多様化にも対応しています。
本局のキャスティング(担当者の指名)の失敗による不良品の発生は担当者を変更し、校正して再納品致します。
音声ファイル入稿に対しては、「ディクテ・コンストラクション」をお願いしておりますが、カセットテープでの入稿について、いかなる対応ができるか検討中です。納品時の電子メールで「ディクテ・コンストラクション」を添付致します。
パートナーシップはこうして前進する。
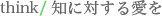
(この原稿は日本編集制作協会『会員ガイド2009―2010』の原稿として書きました。しかし、予定の字数を超え、読みやすくホームページにも投稿することにしました。
先輩の注意があり、他メディア共用の原稿やイラストなど新鮮さがなくなるというアドバイスもあって、反省からそうだなぁと思いましたが、原稿の完成には予定よりも字数がオーバーしてしまいました)
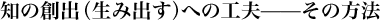
日刊工業新聞 平成21年3月10日
学生がベテラン職人を取材
東大阪・高井田 モノづくり体験報告
【東大阪】高井田まちづくり協議会(大阪府東大阪市、林泰孝会長、06・6781・3380)は、第1回高井田モノづくり体験塾フォーラムを、東大阪市内で開いた。全国有数の中小製造業が集積する東大阪・高井田地区の活性化を狙う、イベントの一環。高校生を中心に、計13人の若者がモノづくり職人を取材した成果を報告した。
体験塾は、08年11月に作家の塩野米松氏が「聞き書き」と呼ぶ取材手法を、高校生ら参加者に伝授して始動した。
13人の若者は個々にモノづくり職人を訪ねて質問をぶつけた対話を録音し、約2カ月間かけて発言内容をまとめた。最終的に13人のモノづくり職人らの生々しい証言を記録した、作品集を完成させた。
指導した塩野氏は「作品集を読むと、高井田のモノづくりの大きな力が伝わってくる」と評価。金型修理業を1人で営む企業を取材した高校1年生は「今回の体験を今後に生かしたい」とし、鉄道用の架線金具メーカーのベテラン職人を取材した大学院生は「誇りを持って仕事をする大切さが分かった」と振り返った。同塾は今後も継続開催を目指していく。
本題に入る前に「気づき」を「いかに生み出すか」。それについてひと言。
1960年(昭和35年)安保闘争のときの佐藤の学生としての問題意識(気づき)は、当時左翼一般に抱えていた「既成概念」に対する認識だった。自分の頭で考えたことではなく国際的にもわが国においても「左翼一般がもつ思い込み――それは恐ろしいドグマが渦まいていた」。20歳になった佐藤正明は人間として自分の頭で考え、こうしたドグマと決別することであった。こうした単なる「心情」にすぎないことかもしれなかったが、仲間の学生同士で議論することにより自分と仲間と社会に立ち向かった。
そうして安保闘争の敗北は共産主義者同盟(ブンド)の崩壊をもって個の所属した組織の分解というか、佐藤自身の深い精神的挫折であり、学ぶべき精神的土台の喪失でもあった。
学ぶべき目標を失った。佐藤の人生は前へ進むことができなかった。
前回、ホームページ「会社概要」の「経営理念」へ投稿したが、『マティールから出発せよ』は、佐藤自身が新しい世界を獲得することであり、それは重い荷物だったのである。
こうした挫折から立ち直り、佐藤の自己精神の活動として欧米の論理表現形式をみつけてそこに到達した。自己精神のすべてを否定したかというと、日常生活のもつ生活感情は残っていた。中学生の「社会科」で学ぶ、家族と家族愛、家族と社会――個人の尊厳と両性の本質的平等、性的役割分業観、個人の尊厳と自立、自主独立の人生、そして人権思想、ヨーロッパにおける市民革命のもたらした人々の権利、人権保障と憲法、ヨーロッパのルネサンス、そこにある理性の光こそ人間社会史の発展の原動力であることを確認し、どのように生きていくか、佐藤は再びここから知を再構成し出発した。
すべての「既成概念」を否定した佐藤の精神活動の再起動の出発点は自身の精神活動からすべてを「生み出す」ことであった。ことばにおける「生み出す」とは、こうした精神活動の背景がもたらす「ことば」なのである。
1970年代も1980年代の、たとえば国際政治学者の論旨を掲載した総合誌や各紙新聞記事も「わが国外交政策の選択」という主題に象徴されるように学者も国民一人ひとりも国家政策ばかりでなく、人々の生き方もそれは進むべき道を「選択」することでしかなかった悲しい時代だった。いま振り返って現実主義的であったと総括しようとしている。
そして選択しなければ生きていけない日本社会だったのである。
この「生み出す」ということばはいまわが国社会へ広くひろがっている。日本社会の「閉塞感」を打ち破っていくことができるだろうか。
「気づき」とは精神の無限連鎖のひろがりであり、つながりだ。しかし、個と他は屈折して思考の光は反射する。
本題に戻るが、一般に形あるものを生み出すには、ディクテーション(談話筆記)のようによく話を聞く習慣をつけることだ。
それは受動ではなく能動の、こちらから出かけて話をし、聞きだし、学ぶことだ。
こうして形あるものに気づく。論理表現形式はこの精神活動の方法をみつけたにすぎない。単なる思考の箱である。
一般に出版業界において、カセットテープレコーダーの発明以来、ソフトウエア(利用技術)として記者の取材に使われてきた。文字化すると聞き落としや聞き漏らしを防げる。また文字化による文脈(コンテキスト)は談話という思考のひろがりや飛翔が思いがけない気づきを生む。
カセットテープレコーダーによる取材の録音が思考のデコボコを修正し、文脈(コンテキスト)として思考のあり方も発見できる。まだいろいろ気づきもあるだろう。
この取材の録音という優れた方法はソフトウエアの輝きを生み出す。
わが国におけるマスコミ出版業界の可能性はここにある。
「知」の創出は産業社会へとひろがっていくことを望む。
そして、ぼくたちは「知」のこの「現場」にいるが、「テキスト相互連関性」とは知の創出の文脈(コンテキスト)であり、日本人性を超えていくには、「ことば」が非哲学的な自己流ではなく、正しい概念が生み出す知の拡大連鎖であり、それは概念の未来への可能性の発展であり、それは概念の発展と言う自己運動の完成を目指した概念の論理的な知の集積になっていく。科学技術の発展とはお行儀のよい理性としての知の発展なのである。
こうした点で人間の意識下の感情と感傷の自己の表現とは「区別」される。しかし、この感情と感傷の自己表現は「特別」に守られていかねばならない。
テキスト相互連関性が知を創出する形だが、ぼくたちは「ディクテノート」「コンポージィングノート」「校正ノート」を持っている。それは「知の触媒」といえるかもしれないが、知識の相互の交換のもたらす可能性で知への創造性を生み出す。仕事が入って出ていくが、私の精神活動のもたらす働きとは、こうしたテキスト相互連関性に新しい「気づき」を生み出し、社会的に共有できる知識創造(価値創造)の方法でもある。
そして、すでに出版社の編集部で実践されているが、精神の内面を描写するインタビューの重要な立場とは、インタビューイーに対するこの分野の専門性に精通した内面描写の豊かさであり広がりと深さがそれを主導する。インタビューイーの「内的独白」として表現され描写される。成果物としてのコンテンツの品質となる。
出版社では過去からの常識となっている。
出版社においての取材の形式はインタビューがもっとも多い。「知」創出(生み出す)のデッサンにすぎないが、参考にしていただきたい。「知」を創出する生み出すことに携わるトランスクライバーへ採用時に渡すテキストに『インタビュー術』(永江 朗著 講談社現代新書)がある。
コンテキストと内的独白の概念としての広がりと深さを学び、自分の気づきとして個性をもってことばを把握する。内的独白はことばの内容を取材のヒントにし、内面描写のあり方を学ぼう。
コンテキスト
Context(英)、Contexte(仏)。【原義】ラテン語のcontextus(結合)から出たことばで、文脈とか、意味をもって完結している、文学作品の断片をいう。【解説】完結した意味は、その全体の文脈を構成する語句によって導き出される。その単位がコンテキストである。したがって、このメカニズムを裏がえせば、難解な語句がある場合に、その語句を含むコンテキストから推定し理解し解説することが可能となる。その意味においてコンテキストを構成する語句とコンテキストの関係は濃い血脈で結合する。ゆえに、語句がコンテキストから独立して抽出された場合に、その血脈関係を喪失して、異なった意味で把握されることがありうる。(長谷川 泉 学習院大学講師)
内的独白 ないてきどくはく
Monologue intérieur(仏)、Interior Monologue(英)、現代小説の手法のひとつ。【類語】内的独白の状態を、とくに<意識の流れ>(Stream of consciousness)と称し、ふたつの語は切れない関係にある。【原義】小説において、個人の心理の内部に切れ目なく連続しておこる種々雑多で複雑多岐な、観念・情緒・心象・記憶・連想などの姿を、そのなまなましい生起の姿のままに描写し、言語に定着せんとする手法のことをさす。つまり、意識の流れの生の言語的描写のことを言う。実作品としては、1887年にフランスのデュジャルダンが「月桂樹は切られた」(Dujardin: Les Lauriers sont coupés)のなかでつかったのが最初とされ、理論上は、アメリカのプラグマティズム哲学者ウィリアム・ジェームズが大著『心理学原理』のなかで、1890年に、人間の意識の内的な直接の姿を<思考の流れ>または<意識の流れ>という切れ目のない流動として把握したのが、最初とされる。またフランスの哲学者アンリ・ベルグソンが1889年に「意識に直接に与えられたもの」において、物理的時間に対立する真の内的時間は、異質的多様な持続であるとしたこと、また1896年の「物質と記憶」において、意識を不断の持続とし、忘却なき記憶であると説いたことは、ジェームズとの親交もあって、重要な同時代的精神風土の一致を示す事柄であった。このような生の内的直接様相を意識の流れとし、その言語的表現を内的独白に見ることは、もとよりそれ以前の時代にも発見できることであり、たとえばイギリス18世紀のロレンス・スターンの奇書『トリスタラム・シャンディの生活と意見』(1760〜67)のなかに、その先駆を認めることも可能である。またドストエフスキーや、さきのウィリアム・ジェームズの弟であった大小説家ヘンリー・ジェームズの作品などには、蜿々たる回想部などに、時たま、内的独白の本能的実践を認めることも十分可能である。しかしこの手法がいかに意識の正確な再現であると言われようとも、感覚、知覚、情感、思考の様相はすべて非言語的なものである以上、作家はこれらの非言語的なものを言語に転じなければならないのは自明のことであり、言語体系そのものがはらんでいる制約の範囲内での直写にすぎない。ドロシー・リチャードスン、ヴァージニア・ウルフ、ウィリアム・フォークナーはこの手法を善用し、ジェームズ・ジョイスはこの雄であった。(由良 君美 東京大学教授)
一般にトランスクライバーの専門性を発揮できる出版社からの入稿で、なかなか文芸的なセンスが弱い人もいる。インタビューは談話で行われる。わかるように表現すると談話は「春の小川がサラサラ流がる」ように談話は文脈(コンテキスト)として「流暢」に流れていく。日本語で表現される。トランスクライバーとして経験が浅いと、発話の音をことばやコンテキストとしてとらえる。しかし、わかるようにいえば、「つっかかって」「断続的に」文脈としてサラサラ流れていないトランスクリプションに出会う。トランスクライバーがことばをつかもうと傾注しているのがわかるが、これではトランスクリプションとしての文脈(コンテキスト)として読みにくい。悪い例だが、ヘタな原稿のつくり方といえる。
1分間に遅い人で700字程度の談話のスピーキングスピードだが、速い人で早口にカタカナ語をまじえて話していく。
実は、談話とは一面で国語学のディクテーター(専権をもつ発話者)の力(知識と教養)にトランスクライバーは追いついていかねばならない。専門的であったり、言い回しがこまかったり、一般に専門性の立場から性別や年齢、教養の深さ、地域柄、職業柄、その人の個性、発声・発音ばかりでなく、発話の速度、ことばの語形などディクテーターはどんなテーマで、誰に向って、何のために、何をどういうことばで、どんなふうに、話しているか、トランスクライバーは話しの内容という「話の筋」を頭の中で整理できないで、ただ漫然と原稿に向っているのであれば、そこに話の筋が、読む人にとって「なんだ、これは」というような場面のもつ原稿になってしまう。インタビュアーは少し長い内容のものでも、話の筋をよく整理して聞き、順序立ててインタビューしている。
やはりインタビュアーの質問がなぜ行われて、それがどのような文脈となって話されているか、展開として話がどちらの筋へと運ぶように行われているか、それがわからなくてはトランスクライバーは一級のトランスクライバーとはいえない。
この項の主題ではないが、「気づき」の多くはこうした「話しの筋」と「文脈」から生まれる。「話し合う」とか「討論・討議」の中から「気づき」は形となって現れていく場合が多い。
佐藤は中学、高校でディクテーション教育が必要だと考えているのは、こうした一般的にコミュニケーション能力とよばれるものの力量について教育の大切さを言っている。自分で考え、学習していく力はここから生まれる。
日本語の力量とは、自分が話すことよりも、よく話を聞き理解できる自分の力だといえる。それがしっかりとわかっていないトランスクライバーもいた。
日本語も英語も、他の外国語も語学の力とはこのような上記の総合力であって、娘や息子も小学5年生から英語を塾で学ばせたが、一般に何か誤解していないか。
話は少し転ずるが、日本語の力量が外国語の力量といえる。日本語の大切さを言いたいのだ。
語彙の説明としてコンテキストと内的独白は文芸用語だが、知識の広がりと深さを学び、ただ学ぶことではなく、日々の仕事に活かし、実践し、知識への好奇心をもてるこの仕事の楽しさと喜びを発見してもらいたいと思う。
佐藤はよく「忠実に、正確に、丁寧に」と言っている。まさしく日本人的な表現にすぎないが、このことばの内容と意味は、このようなことなのである。
2009年3月1日日本経済新聞「私の履歴書」女優香川京子さんの連載第1回が始まった。新聞に発表されたが、文芸として把らえ日本の文化としての日本語による文芸の表現らしさの「歴史」をここから学ぼう。トランスクリプション(録音再生原稿)の談話のもつ「春の小川のサラサラ流がる」側面としてライターさんの執筆原稿との「境目」をトランスクライバーは気づきをもって感じ取らなくてはならない。「談話と執筆」のもつ相違がどのように「整文」となったか。私のつくるトランスクリプションはどうあるべきか。私のトランスクリプションのつくり方に個性を求めよう。日本語による文芸のあり方は、文芸の歴史となった漢字文化でもある。ここに気持ちを置いてライターさんに「これでいいよ」と言われるような原稿づくりを目指そう。
ようするに、日本語を使って「書く」という行為の土台は文芸(日本語国語学)から学ぶ。いろいろな分野の「書く」という行為全般の土台は文芸の歴史の知識と自分の知識である国語学に基づく。ここから自分は何を、いかに学ぶか、問題意識をもって毎日配達される新聞からでも学びはじめることはたくさんある。テレビを観ていても頭の中でアナウンス原稿のトランスクライビィング(談話筆記)をしたり、ラジオを聴いても勉強する姿勢が大事だ。ニュースが参考になると思うのは、新聞から知る時事用語でもある。
日本経済新聞 2009年(平成21年)3月1日
私の履歴書
香川京子 第1回
巨匠たちと映画120本に
今も元気に仕事、ただ感謝
女優生活60周年
私が映画界に入って、今年はちょうど六十周年を迎える。その年に生まれた赤ちゃんが還暦を迎える歳月だが、こんなに長い間、仕事ができるとはまったく思っていなかった。今でも元気で仕事をさせていただいているのは、ただただ感謝である。
デビューして間もないころ、成瀬巳喜男監督との対談で、「京ちゃんはオバアサンになるまでやるんですか」と聞かれたのを今になって思い出す。「どうせ始めたんですから、やれるまでやります」と答えた。その時点では正直、質問への実感がわかず、「ああそうですか」という心持ちで聞いていたけれど、今になってみると、成瀬監督に訊ねられた通りになった。
しかし、女優というのは待っている仕事だから、出演の依頼がこなければそれきりである。昨年秋に公開された「東南角部屋二階の女」で、私は古い二階建てアパートを所有し、近くで居酒屋を営む年配の女性、藤子を演じた。婚約者が戦死し、その兄でアパートの地主の老人(高橋昌也さん)の世話をしている。
アパートに人生の岐路に立つ若者三人が転がり込み、人生の先輩である藤子らとの出会いを通して少しずつ変わっていく。現実の社会が余裕を失って来ているので、少しほっとさせられる話である。
出演の声をかけてくださったのは、この映画が監督デビュー作となった池田千尋さんという女性監督。二十代後半とお若いが、自分の考えを落ち着いてはっきり言う方で、そのしっかりした印象は最後まで変わらず、楽しく仕事ができた。自分に向く作品なら、若い人たちと仕事をするのはワクワクする。
六十年間に私が少しでも出た映画を数えると、ざっと百二十本になる。成瀬監督をはじめ小津安二郎監督、溝口健二監督、黒沢明監督など巨匠と呼ばれる監督とも仕事をさせていただいた。このため「監督荒らし」などと言われたこともあるが、自分としては、そんな実感は少しもない。私自身、未熟な自分のことに夢中で周りが見えず、何もよくわからないでやっていた。
また「女優らしくない」とも言われる。それは私の性格のせいで、映画界に入ったのも、女優になりたいというより「自分の仕事」をしたいという気持ちが強かった。若い時からマイペースで、仕事以外のことでも自分のことは自分で決めたい性格である。
家に帰るとまったくの主婦であり、仕事と自分の生活は別という考え方は、ずっと変わらない。ブランド品にも興味がない。他人と同じものを持つのは嫌で、自分で気に入ったものを使いたい性分だ。他人から見ると変わっていると思われるだろう。
昨年は黒沢監督の没後十年ということで、テレビやラジオのほか、いろいろなところからお招きをいただいて話す機会が多かった。映画祭や上映会で「黒沢組はこうだった」などと話すと、映画好きの若い人たちが喜んでくれたのがうれしかった。
本欄「私の履歴書」の過去の執筆者の中には、田中絹代さん、杉村春子さん、笠智衆さんなど私が女優の仕事を始めたころに共演させていただいた方々のお名前がある。私がそのような大先輩たちに並ぶべくもないが、私の俳優人生を語ることで映画の面白さ、喜びを伝えることができれば幸いである。(女優)
毎日の仕事で気になった、気づいた些細なことでも報告書(ノート)に記録し、論理としての働き(機能)をみんなに公開し、それを議論してその成果を「形(かたち)」にしていくことだ。「東大型クラス討議」による知の集成が行われる。佐藤は共創造に関心をもつ。思い込みを排除した討議の自由なあり方から理性の光が形として見えてくる。論理表現形式を参考に思考をなぞり、つなげていく。それは組織の知として形成され共有されていく。
佐藤が求めてきたのは知を生み出す方法論であった。
「成功事例」を例示しても「類(たぐい)の模倣」を超えることができるだろうか?
自己の精神から生み出すか、あるいはこの思考が欠落していれば、それは欧米からの技術導入であってもその原型は民族特有の「外からの形式と内からの内容の衝突」という変形――よい意味で民族特有に土着化していくかもしれないが、論理的な自己運動としての発見、ないしは論理による延長をもたらすことはできないだろう。過去の日本産業資本主義の、それは悲しい経済文化であった。企業の成長と発展には正しい論理性が必要だ。
日刊工業新聞 2009年(平成21年)3月27日
従業員の創造性向上
人材育成プログラム
千葉工大 事例解析し体系化
【千葉】創造性を科学的に解析―。千葉工業大学社会システム科学部の佐野利男教授らの研究グループは、従業員の創造性を高める企業向け人材育成プログラムの開発にめどをつけた。事例から創造プロセスを解明して体系化することで、創造力を引き上げる教育プログラムをつくる。今年中にもパイロット版のビデオ教材を制作する予定。従業員の創造性を高めることにより、企業全体の活性化につなげてもらう狙いがある。
人づくり
佐野教授らは、創造性を「既知情報と、既知情報の結果生産される新情報」と定義。07年4月から習志野商工会議所(千葉県習志野市)の会員企業8社の協力を得て従業員からヒアリング調査を行い、約300件の実証研究を実施してきた。
収集した事例を解析し創造性事例が起こるプロセスを解明することで、創造性を高める教育プログラムの開発を進めている。同プログラムは、07年度に文部科学省の私立大学学術研究高度化推進事業に認定される。
ヒアリングでは新情報(N)は、きっかけとなる情報(K)によって、既知情報(A)と既知情報(B)が統合された結果、生産されるという仮説を立て調査を実施。K・A・B・Nの四つの要素に分解し、従業員に対して個別に聞き取り調査した。制作するビデオ教材はケーススタディー方式を採り、収集事例を4要素に分けて解説する予定だ。
竹林のたけのこでなければいい。論理には科学性と普遍性がある。安易な「論理」ではないか。こっちとあっちをくっつけても「統合」という論理にはならない。いわゆる「アイディア」だろう。
戦後、高度経済成長期のたまげたものしか生まれない。論理が貧困だ。
たけのこ生産と真のモノづくりは違う。本物は生まれないだろう。「ああいえば上佑」の屁理屈製品が生まれるだろう。
日本経済新聞 平成21年3月10日
米住宅ローン 焦げ付き拡大
延滞・差し押さえ率最高10-12月
雇用環境悪化響く
金利改定 追い打ちも
【ニューヨーク=山下茂行】米金融危機の発生源の住宅ローンの焦げ付き問題が一段と深刻になってきた。実体経済の悪化で2008年10-12月期の延滞、差し押さえ率は過去最高を更新。米政府は公的資金750億ドル(約7兆3500億円)を投じる差し押さえ防止策をまとめたが、延滞や差し押さえは年明け以降も高水準で推移しているもようだ。変動金利型ローンの約3割はこれから金利改定に伴い返済負担が増加する時期を迎えるだけに、追加対策を迫られる可能性もある。
米抵当銀行協会(MBA)によれば、10-12月期の住宅ローンの延滞率(季節調整値)は7.88%、担保不動産の差し押さえ率は3.30%。返済負担が重い変動金利型の信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)は、延滞率が24.22%、差し押さえ率が22.18%に上り、半分近くの返済が行き詰った計算だ。
住宅の値下がりが止まらずに返済余力が低下しているうえ「雇用環境が急速に悪化している」(MBAのエコノミスト、ブリンクマン氏)ことが背景。ニューヨークの場合、証券大手リーマン・ブラザーズが破綻し、大手金融機関が人員削減に動き始めた昨年後半から住宅市況が急速に悪化。著名人などが住む高級コンドミニアムでも「差し押さえ物件が競売にかけられるケースが増えている」(中堅不動産)。
当初設定の金利から一定期間後に割高な金利に移行する「リセット」と呼ばれる融資条件の見直しに伴い、住宅ローンの焦げ付きはさらに増える公算が大きい。米連邦準備理事会(FRB)によると、サブプライムよりもやや信用力の高い「オルトA」の変動金利型ローンの場合、残高の約15%が今後2年以内、同約38%が3年目以降にリセットの時期を迎える。
変動金利型サブプライムローンはリセットのヤマ場を越えるとされるが、それでも残高の約3割はまだリセットの時期を迎えていない。「オプションARM」と呼ばれるよりリスクが高いローンでリセットが本格化するのは10年以降とされる。
リセット後は金利が一気に10数%まで高まるケースも珍しくない。
住宅市況の冷え込みを映し、1月時点の中古住宅の在庫件数は月間販売の9・6カ月分に相当する360万戸と高水準。市場に放出された差し押さえ住宅が市場価格のさらなる下押し要因となり、一段の契機悪化につながる恐れもある。
米政府は公的資金を使った住宅ローンの返済支援策を打ち出したが、細かな制限があり実際の適用は一部に限られるという。契機悪化が続けば住宅ローン問題への対処はより難しい。
ヒラリー・クリントン国務長官はロシアの外相と「リセット」について両国対話を提案した。サブプライムローンの高金利で家を失う低所得者を守るために米国では「住宅ローン返済支援策」が打ち出されたようだが、どんな支援策なのか内容はわからない。
2009年3月27日日本経済新聞朝刊は、ガイトナー米財務長官が26日発表した「最大500万世帯に低利ローンの借り換え条件を緩和」「750億ドルの公的資金で住宅差し押さえに直面する最大400万世帯を支援する内容」
この「リセット」にいかに対応するのか。国際金融危機の同時大不況下の国際政策協調が行われているが、米民主党は2009年この金融危機に対して政治的国際潮流の「リセット」の思想を提案している。
「銀行だけでなく、証券、保険、ノンバンクでも連邦の単一当局が集中監視する仕組みをつくり、システム危機のリスクを減少する」ようだ。米国とEUでは認識の相違がある。
資本の自由に対する考え方の相違だ。影響が大きい資本の自由と一人ひとりの国民の自由が「屈折」している。ここに人間の理性を担保できるか。
21世紀になっても資本の「自由放任主義」の動物社会が続いてきた。近代経済学は資本の自由放任主義こそ人間社会史と区別された「動物社会」として「人間社会」を把える。
18世紀から歴史の針が止まったままであった。けして「人間社会史」と把えることはなかった。歴史の発展のためには法規制が有効か?
人間の理性の光と「自由」の思想の動物性との衝突なのである。近代経済学の思想の挫折だ。それは「リセット」の歴史的意味である。
国際同時金融危機への国際政策協調への各国の現状の「思い」を「リセット」からスタートしようと願っているのだろう。
米国の新自由主義がもたらした「現実的疲弊」を「リセット」すること。
「リセット」は新しい歴史的転換の「政治思想」なのである。人間の理性の光による社会史の史的集積が、18世紀の歴史を超えていく歴史的瞬間なのである。
わが国における国家の再生も正しく「リセット」の対応策で前進しなければならない。
ぼくたちの「気づき」も世界へとつながっている。
佐藤も18世紀の西ヨーロッパの歴史の総括から知識産業社会へと胎動の歴史が始まっていくとは思っていなかった。
近代経済学と歴史(人間の理性の光)との衝突なのである。アダム・スミス以来、思考を停止している。数理で人間社会の歴史を解明できないことを実証した。「人間社会」は「人間社会史」として把え、把えなければならないということを21世紀の歴史は「今」教えている。
思想的にはわが国高度経済成長期の産業資本主義からバブル経済崩壊がもたらした「失われた10数年」を経て、わが国国民も「選択する」道を失ってもいる。立ち止まって進むべき道を失っている。
「リセット」は一方、規制という名の新しいスタート(再生)を国際政策協調の「思い」をもって新生グローバリズムとして新しい政治思想として歩むだろう。
21世紀の新しい自由の建設である。
「選択」から「創出(生み出す)」へこの大不況は同時再生の意味であり、選択する日本人から気づきを形にして創出する(生み出す)日本人の新生という意味でもある。
今朝、2009年3月29日 特別に加筆することにしました。
本局では3年前から認識がありましたが、「利潤最大化」の考え方を持たず、すなわち利潤追求の考え方をもたず本局の経営にあたってきました。これまでの経済システムに対する本局の考えであり姿勢ですが、この考えのもつ「枠組み」が未来の経済になるという経済思想に基づく経営をしてきました。
3年前の佐藤の「気づき」でした。もちろん現下の不況は「失われた10数年」になるかもしれない、と危惧している。現下の資本主義は完全に経済成長の自生力を失っており、エコノミストの関心は経済財政政策に移っている。
中国やインドやその他新興国は産業資本主義の段階にあり、経済成長の自生力をもっているだろう。経済財政政策はその自生力を刺激することはできる。
先進国資本主義はわが国において近代経済学が「官庁経済学」として戦後出発した。
産業資本主義発展の自生力は経済財政政策の刺激で経済成長が可能であった。
いまや先進国経済は自生力を完全に失っており、経済システムを枠組みとして描いて「型」(制度設計など)を発明し、巨大企業の資本の運動をその主要な要素とし、経済成長が可能であるという幻想をこの型に向って描くことができると考えているのかどうか、そして国民の生活には道徳があり、あるいは宗教に基づいた質素で節約を合理的な生活を支えることにバランスをとるというか、賢明な庶民の生活の姿勢など、こうした「普通の生活」を常識と考える実生活を一般的にいえば「美徳」とする常識に対して、ある時都内のタクシーに乗って、タクシーの運転士さんが「カネを使ってもらわなければ、景気は良くならない」と言うとか、ある大臣が「銀行さん、儲かってますか」とか等々、経済システムの持つ「反社会性」「反モラル性」「犯罪性?」この老獪な経済システムに裁判所は国民にモラルとして「バランス思考」を押しつけている。
おかしくないか? 最悪の経済システムだが、最善の経済システムだろうか?
国の政策と善良な国民のこころが麻生自公政権と乖離しはじめている。
「善良な国民のこころ」が国家指導者によって「壊されていく」。子どものこころも「壊されている」。高齢者のこころも、真面目に働こうと思うこころも「壊されていく」。社会の閉塞感はニッチもサッチもいかない。希望のもてない社会になってしまった。
裁判も検察の価値観もバランスなのか、そこに真理や正義が見えない。法の精神はどうなっているのか! 理性の光はどこへいったのか、現実社会はこれでいいのか?
経済財政政策が国家政策であることは、まぁ一般的にいえば経済の対称性をエコノミストの多くは全的に予測できず、それはひと言でいえば時間がもつ歴史的結果での国民の悲劇でエコノミストからこの不況に対して反省のことばはあまり聞かれない。
庶民はどうやって生きていけばいいのか。わが国政治はいま岐路に立たされている。
佐藤はいま余裕をもって言っている。近代経済学者に少しはこころに良心をもて! と言いたいのだ。
こうしたことがメディアミックス&ソフトノミックス/は3年前に「利潤最大化」の思想を放棄した。
祥子が入社した翌年の新年の元旦祈祷を終えて、町田で「利潤最大化」の経済原理をめぐる大論争を佐藤とした。そのとき佐藤は「どうやって生きていくか」それはSOHOとしてゴーイングコンサーン(企業の永続性)に対する佐藤の本能的な反応であった。この経済環境で社会生態学的な佐藤の生き方を求めるものであった。
新聞などで経営学者の「経営書」を「学ぶ」が、佐藤は本能的危機を感じたこともあった。経営者として会社経営を経験したことがあるのかどうか分からないが、倒産の原因となる経営書が多い。新聞による経済の動きは長期展望のヒントになる。株価勉強会の講演を聞いてどのような経済の動きとなっているか、佐藤は資産運用には一切関心をもたない。
もちろん株にも関心はない。こうした電話が会社に1日何度も入ってきたこともあった。
けがらわしくてガチャと電話を切る。
経営は、というよりも経営者はと言ったほうがいいかもしれない。それは個人的な、余りにも個人的な自己実現へ向っていく生き方といっていい。それは社会生態学として近代経済学者の動物的な「人間社会」でどう生きるか、ということと社会科学としての「あるべき姿」に自分のミッションを定め、従い、社会へ貢献する生き方を通して学校で学んできた真理や科学や親の教えやそうした家庭、地域社会で育てられた社会の中で自分の生き方を発見し、そこに自分の仕事としての役割を見いだし、自分の生きる理念をもってどのように社会をみていくか、そこに佐藤の生き方を定めている。
たった数行にすぎないことだが佐藤は人間の良心にもとづく「気づき」や「生きる知恵」をここから発想している。この社会を動物社会として統治概念は、かつての東大安田講堂闘争の深淵な問題意識だった。佐藤は海外でこのニュースを数カ月後に日本の新聞を読んで知ったが、この問題提起が今日の公務員改革の問題になる。ある意味で東大法学部の解体という東大民営化の意見もあるだろう。
ちょっと脱線したが、近代経済学にもし「良心」を入れることができたら、社会は大きく変わっていくだろう。
「官庁経済学」として出発した近代経済学の、それなりの遺産は「政策立案能力」といっていい。対案を出さない反対派のままでは日本に進歩はない。政府に対し全面的な対案を準備するとすれば、政権与党の資金力に対して野党の弱さを引きずるだろう。だが小沢民主党の一本道はわが国政治の生まれいづる胎動なのである。
ガキの20歳の経験だが、早稲田の学生運動は東大と違って大衆運動だが、学生諸君に他の政治分派に対する抜きん出た全面的な対案を用意することによって、学生諸君の支持を獲得することができた。これは政治のイロハだ。
小沢一郎氏の今回の検察のあり方はわが国政治の未来の政治的危機なのである。
本題からそれてしまったが、メディアミックス&ソフトノミックス/はこの20年間相変わらず何の変化もない。原理・原則・基礎・基本・ルール・手順・順序の経営の原理に従い、スタッフとともに対等のパートナーシップで「顧客のために何ができるか」、それがぼくたちの生きる生き方である。
多くのホームページの訪問者もある種の「予感」を感じている人もいるだろう。
それは企業が「規模の拡大」、「利潤最大化(利潤追求)」だけがゴーイングコンサーンではけしてないことに「気づく」べきだ。経済規制はどのような経過をたどるだろうか。
いま世界の動きに注目している。ぼくたちはわが国出版社と日本語がすべての知識の源泉であり、文化の原動力であることを確信している。ぼくたちの仕事がわが国の知識産業社会の建設へ向けて片隅で生息する生態学から学ぶ品性ある生き方を求めている。
それはSOHOといえども1960年代の北欧、英国が栄えたそこにある先進の企業の品性を新しい21世紀のマイクロビジネスの先進国らしい品性をもつ「スモールグレイトカンパニー」を目指している。
そして現下の最悪の経済システムの重荷を背負って、今後歩むことになる。
佐藤の人生は背中に荷物がいっぱいだった。降ろしたかと思えば、また背負う。
スタッフを守っていかなければならない。
そして、やはり生きていくことばは、「相変わらず」な生き方でしかない。
追伸
自分に都合の悪いことばのすべてを拒絶する今の一握りの人々の性向は想像できる。
だが、謙虚なこころがあなたに残っているだろうか。
この不況は勉強には十分な時間がある。
佐藤にはアメリカのサブプライム景気から次はBRICs景気という幻想に関心はない。
国家資本主義間の闘争が激化するだろう。資本のグローバリズムの「規制と節度」は政治の力が高まるだろう。衆院選が政治の力を生み出す。
NHK総合テレビの報道番組の輝きに学ぶ――論理表現形式をどのように自分のもうひとつの表現として活かしていくか。
NHK報道局の気持ちがわからないわけではない。わが国「知」の創出へのいまだからこそ、その必要性に歴史の時計の針を止めてはならないと佐藤は考える。
しかし、嫌がっている気持ちもよくわかる。問題意識は佐藤のほうが少しは早かったと思っているのも正直な気持ちだ。
アジアの新興国や後進国へ放送技術として指導していく立場にあることもよくわかる。
佐藤はNHKの報道取材番組を注意して視聴していれば家庭で学ぶこともできると思う。NHKの報道取材番組の放送文化は先進国なみになっている。NHK報道局の職員に対するガバナンスもひじょうに厳しく行われていることも外からわかる。
NHK報道番組にまずわが国で「導入」され、わが国マスコミをリードしている。
NHK報道番組一般に広がって、まずNHKラジオから出発し、テレビ報道取材番組へと広がってきたご努力を学ぶ。
佐藤はNHK報道番組をおもに視聴している。ニュースの視点もそこが知りたいひと言の広がりと深さを感じ、視聴者の求めているものに応えてくれているし、視聴者は企業経営者も企業幹部も、わが国社会の指導的立場の人も視聴している。報道番組の影響はそのニュース性において他の媒体においても無視することはできない。アナウンス原稿のひと言(コンテキスト)も世論を誘導してはならない。公正であるべきだ。
NHK報道局がもしこの佐藤のいう論理表現形式の、なんというか、こなれた、そして庶民の日常性へと吸収し、自然に、境目のない文脈として表現されていることに、佐藤は学んだ。これまでの伝統の表現形式(起承転結)を活かして洗練されている。
わが国がもつ知識文化の広がりと深さを先進の文化の水準として定着していくのは、ごく一部の層であろう。
佐藤は知識産業社会がマスコミこそがその指導的な立場にあり、佐藤も青年時代からの背負ってきた重い荷物をおろして、酒を飲みながら味わうのは知的な喜びである。茶の間でみているマルチメディアの文化を享受できることの喜びは大きい。
関心あるホームページの訪問者にも、この喜びを伝えたい。佐藤は個人的に享受したいと思っているのではない。優れた先進文化をリードしているのは、これまでのわが国表現文化の伝統と共に、これはわが国固有の伝統文化であるが、もうひとつのこの論理表現形式をもつ二本としてわが国は固有な文化として未来の知識産業社会を獲得していきたいという思いである。
再び強調する。NHK報道番組の午前中の「いっ都ろっけん」などもおもしろい。関東の放送局から報告される報道取材番組――関東1都6県のNHK地方放送局のアナウンサーへと層が広がっている。報道局で制作される報道取材番組は最近ではこなれたというか、これまでのわが国固有の伝統の表現形式を活かした、うまいというか、表現がなめらかになって論理表現形式との境目をアナウンサーは放送現場でこなれたうまさを出して自分らしさの表現を獲得している。洗練されてきた。文化として吸収できることを実証した。だが、かつて日本人は外からの文化を吸収してきたが、「思考の光」は屈折して反射する。
何度もいうように「外からの形式と内からの内容との衝突」に思考においては欧米の知性を尊重し、そうした思考の品性に留意しよう。論理表現形式を哲学的に批判し、もし自己の「哲学的立場」を確立した変形であるなら、それはそれでいい。だが、哲学は文学ではない。論理を持ち込む意味で我流を排す。科学に対する尊重のこころが未来のアジアを指導することができるだろう。明治以降の日本人の土着文化に対する反省の視点があって、今こそわが国がこのグローバルな世界へ羽ばたく世界の中の日本として「生み出す」知識産業社会が広がりをもって幕開けする。
意識下の文芸とは区別される。その通り知の科学と区別される。
ホームページの訪問者はNHK報道番組を「録音」して「文字化」し、なぞっていくことにより番組を研究してほしいと思う。アナウンサーの語りを「談話」として再文字化すると文脈(コンテキスト)として思考の筋が現れて気づきが思考として整理ができる。学校で手とり足とり教えてもらうことに慣れているのかどうか、学習はこの現実社会こそ完成された姿として知が表出している。
論理的であればあるほど、対象に対して自己の精神の中で形を描くことができて、自分の表現形式として学ぶことが毎日のようにできる。NHK報道番組は大学卒業後の質の高い優れた講師だと思う。仕事に活かしていってこそ本当の自分の実力だといえる。
最後にNHK報道局アナウンサーのレベルが高いことに佐藤は気づき、民間放送局は遠くの小島で生息しているように見える。NHK報道局の先進の水準を学ぶことの意味はわが国におけるマスコミ媒体の真の実力となる時代が来るだろう。
自分(会社)をマーケティングする
前回のホームページ(会社概要 経営理念)と同じP.F.ドラッカー先生の著書『未来への決断』84頁、「自分をマーケティングする」を参考にする。
先生は「私には昔の教え子から毎日のように履歴書が送られてくる。しかし、そのほとんどは、単に過去の職歴を列挙している。それらのうち、あるものは職を書いてある。しかし何を立派に行なってきたか、何を立派に行なうことができるかについて書いてあるものは少ない。自分を雇うならば、自分から何を期待できるか、何を期待すべきかについて書いてあるものはさらに少ない。言い換えるならば、自らをマーケティングすべきものとして見ている者は、まだほとんどいないということである」。
メディアミックス&ソフトノミックス/に履歴書が送られてくる。ふつう800字の作文をお願いしている。作文のテーマは、「仕事に対する私の考え」である。
自分は「仕事に対して」どんな「あるべき姿」をもっているか? ひと言でいえば、こういうことだ。仕事に対する意識の高さを測定している。
しかし、多くの応募者は、会社のどの部署でどんな仕事の担当だったか、「自分が一所懸命取り組み、そして報酬を生活の糧にしたい」という内容が多い。
一般に就職時のマニュアルの様式を参考にしているのかどうか、「自己紹介カード」のようなものだ。
しかし、採用したいと思う気持ちに応えていない。
自分のこれまでの「生き様」を吐露し、それは短いストーリーとして自分がどのように生き、挑戦し、どのように仕事と取り組んできたか、そして伝えやすくいえば、NHKの「プロジェクトX」のように自分の仕事と向き合い、自分はどのような考えで仕事と取り組んだか、最低でもこの程度の内容が書かれなければ、人材としての魅力は薄い。
あなたが「どんな人間か、どんな仕事をするか、どんな成果をあげるか」、採用者はあなたのここを見ている。
一般社会での一般的傾向だと思うが、ダラダラと書かないで――採用者は忙しいのかどうかはわからないが、採用には「運」があると考えているのかどうか、わからないが、一般に自分がその会社に入社したいと思えば、いまの人(採用者)には短い作文(ストーリー)で描くことだ。
仕事の達成能力に期待をもたせるような、けして誇張することなく、誠実な自分自身がそこに描かれていれば、あなたは入社できる。
■星野卓也著『30分で5億売った男の買ってもらう技法』(インデックス・コミュニケーションズ 2004年7月15日初版発行 1400円+税)ストーリー(物語)はどんなビジネスの背景から生まれたのか、それをこの本で学ぼう。ストーリーという“今日的意味”を学ぼう。
先生はさらに「パートナーシップにおいては命令することはできない。信頼を得ることしかできない。ということは、具体的には、もはや「自分は何をしたいか」からスタートしてはならないということである。
正しい問いは、「彼らは何をしたいか。彼らの目的は何か。彼らの価値は何か。彼らのスタイルは何か」でなければならない。必要とされているものはマーケティングの考えである。マーケティングでは、製品からではなく、顧客からスタートする」。
この先生のいう「正しい問い」は、佐藤は顧客に対して自分の仕事(使命)とは何かを考えることだ、と考える。
自分をマーケティングする、ことに慣れていないのかどうかはわからないが、多くは企業社会において製品についてのマーケティングが多い。
会社へ応募するときは自分をマーケティングする。職場ではチームワークが求められ協働が求められる。まず転職のキーワードは自分をマーケティングすることである。
転職市場の変革はここから生まれる。新しい時代の政治家も自分をマーケティングすることの意味は大きい。
メディアミックス&ソフトノミックス/はパートナーシップを推し進めている。パートナーシップは「製品からではなく、顧客からスタートする」と先生は言っている。
メディアミックス&ソフトノミックス/は創業から2000年にいたる約10年間、宣伝会議の『マスコミ電話帖』へ広告を出稿してきたが、ここでいう佐藤の「自分とは」会社をマーケティングすることであった。
今でも会社をマーケティングしている広告に出会うことはあまりない。
「製品」のマーケティングが主流である。一般向けにはやさしいことばで象徴的に描くのがいいと思われがちだが、佐藤は企業としての理念を前面に出した。ぼくたちはマイクロビジネスでありSOHOである。それは自分をマーケティングすることだ。
出版社の編集者へ、いかにぼくたちの声を届けるか、それがマーケティングの本質である。ここには、ぼくたちの「生き方、働き方、日々の暮らし」で求めている生活感(生活の糧)というよりも仕事に対する少しだけ次元の高い感傷の空気としてスタッフ全員と共有したいメロディーであり、リズム、ハーモニーであるかもしれない。
少し大げさかもしれないが、書籍(文学)に描かれる現実とはいえない空想のフィクションではなく、現実のぼくたちの仕事に求めている精神の青春(挑戦)を感じるコンテキストの音楽なのかもしれない。それは叙情の詩(うた)かもしれない。
わかりにくいこの一文だが、誰でもが文学に接して感じる心地よさ、恋愛ならドキドキするこころの動き、日常性を超えたコンテキストの世界――それはどんな時代の、どんなこの時代に生きて、知の社会的トレンドの風をとらえ、ことばにのせて、それは生きる喜び、ちょっとした気づき、ちょっとした勇気、サラサラ流れる小川のような自分のことばに生きて自分の今を語り――そのいまの時代の歌をうたえ! テキストに心地よいメロディーをのせて。TPOを使って、そんなことを佐藤は言いたいのだ。ただ架空のおいしそうなお菓子を食べることよりも、現実の実労働で感じる労働の現実的な感傷的喜びを求めている(ノンフィクション)といってもいいだろう。
コンピュータやIT機器と技術がもたらした生産的労働(所得)の生々しい生の現実を求めている。「中間生産品」の気楽さと、もちろん品質の責任を感じるが編集権を持たない生き方、働き方のたのしみ方かもしれない。
いろいろな出版社からいろいろな分野のお仕事がきている。
自分をマーケティングするということはこのような一面もある。自分の青春の叙情詩でもある。
毎月、宣伝会議の『広報会議』(旧『PRIR』)を創刊以来購読してきたが、小社のそれは「広報戦略」(PR戦略)といえるかもしれない。
ホームページへの訪問者がなんとなく思っているのは、製品のマーケティングではなく顧客に対するパートナーシップのぼくたちの姿勢である。
本来ならやさしいことばでストーリーにして訴求すべきことかもしれない。
しかし、それはぼくたちの思いをことばで表現するとPR戦略といえるだろう。
会社設立が1988年8月の末だった。設立3年後の1991年(平成3年)8月30日、日本編集制作会社協会発行の『マスコミを動かす編集プロダクション』で、小社は「パートナーシップ宣言」の最初のことばを使った。以来、相変わらずのこころで2009年現下の不況下でも相変わらずだ。
ぼくたちの仕事は「常に未完」であると思う。仕事に対し、工夫・改善の視点で究めようと思っている。
そして、仕事の本質(ミッション)とは「社会に対する貢献」のこころだと思う。
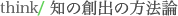
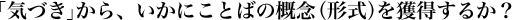
知の創出について、現状を考えてみます。
佐藤はみなさんに「気づき」の大切さについて言ってきました。
工夫・改善と、ただ繰り返し言ってきました。
中学校社会科用の『新編 新しい社会 歴史』東京書籍発行 P165(平成9年2月10日発行)
「理性の光と民衆文化」
アメリカの独立に先立って18世紀の西ヨーロッパには,理性の光に照らして因習や偏見を批判する啓蒙思想が広まっていた。ロックは人民が政府をつくる権利(社会契約説)を,モンテスキューは三権分立を説いた。
ルソーは自然への回帰と人民主義を唱えた。アダム・スミスは,「諸国民の富」で国家による管理に反対して経済の自由放任を主張した。また,ニュートンの物理学など自然科学の基礎ができ,実用技術も開発された。
啓蒙の時代の人々は,地球上のすべてのものごとを合理的にとらえようとした。フランスの「百科全書」には,こうした知識が集大成されている。自然に対する文明の優位という意識は,このころの西ヨーロッパから始まった。
18世紀のパリやロンドンは,百万都市江戸にもおよばないが,人口50〜70万に成長し,人々は祭り,スポーツ,芝居,そして喫茶店,居酒屋での語らいを楽しんだ。安い本,雑誌,新聞が発行され,民衆も物語,ニュースや政治評論に親しんでいた。
(わが国義務教育の社会科は、文科省の公式見解というか、国民の義務的共通認識ともいえるだろう。かつて糸川英夫先生の六本木の事務所に訪ねたことがあった。
先生の書棚には、中学校の教科書が並んでいた。佐藤も以前から春になると、学校の指定書店で購入の機会をつくっていた。息子の高卒時に高校教科書を譲り受けている。
みなさんも子供の教科書をチェックしておくべきだろう。「知の成果とは、教科書を書く力」でもある。わが国の文化や知性の水準を測定するいい機会にしよう)
わが国において21世紀の思考の構築として、新しい『百科全書』の書き方が必要だ。
各人の気づきを工夫や改善をもって考え、みなさんが生み出したその気づきによって書き込まれた成果を事例として抽出し、こうした事例創出活動・運動をみなさんに示し、これは一般にウェブにおいて行うべきだと思うが、全員が共有できることが大切で、その事例を知る・学ぶ、そしてわたしもやってみてわかる、学習と訓練の教育的意味。次にわたしにもできる適応へ、こうして事例をみんなで共有していく。
たとえば、官僚が「下ふる」支配の構造からみんなの「気づき」や「知恵」を求めて、理念の基に構築していく新しい文化(社会パートナーシップ)の創造へ!
特にいまならわが国医療分野において、社会実験ができるだろう。
コンポジショニストの、いくつかの手づくりマュニアルはこうしてウェブから生まれた。そして、知を工作する論理によって構成された。
ウェブはみんなが見ている。毎日、仕事での気づきへの感受性が事例を生み出す。
(アイデアと事例とは異なる。違いについてしっかりと区別して考えよう)
日本人にとって話すことは、書くことよりもよくわかる場合も多い。
「こんな書類が当局から届いた」が、よくわからないので直接話しを聞きに行きたい、そういうこころが動くこともよくあるだろう。
一方では日本語の「言の葉」の綴りでは、内容がなんとなくわかるが、書き方としてみた場合、概念化されていない場合が多い。内容をよく知っているのだが、概念化ということばを形式として生み出させない。思考が停止して、更に発展できない。
日本人の、というよりも日本語の特徴なのである。
広辞苑などのことばと現代科学の用語とは違う。辞書とは国語辞典だと思いこんでいる人もいる。だが、「用語」には本質・形式・要素(働き)・目的が必要だ。日本語は古代・中世人の思考方法を模倣しようとするが、現代という、生きている日本語に対応できないでいる。日本語の歴史を学ぶことは必要だ。しかし現代に対応できていない。グローバル化する世界へ向けて日本人性の思考の変容が求められる。
佐藤はよく言っている。「英語で考えろ 日本語で考えるな」。日本語を頭の中で翻訳するな。多くは、その日本語は変な英語になる。
佐藤はたまに本局に電話がかかってくる件(くだん)のひとつに、裁判ごとでの日本語の英語への翻訳はお断りしている。親切で、正当な理由だ、と思っている。
佐藤はよく本質・形式・要素(働き)・目的によって論理展開するように希望している。
『百科全書』は論理学者によって書かれたとピーター・ドラッカー先生の著書から知った。
ある出版社の編集者も認めて、哲学者と自称する「学者」が書いた「哲学」は、インターネット時代以前の辞典の丸写しだった。今ならコピペする「哲学者」というべきで、「学者」なのである。ある大学の教授だ。哲学する人ではない。文学する人でもない。俳人でもない。詩人でもない。学者の評論なのである。よくいる「おっさん」が哲学について語っている。編集者も哲学とは何であるか、知っている人は少ない。大学で「哲学の概論」を勉強することは、哲学とは一切関係ない。大学教授のように物知りになるかもしれない。
みんながわかるように言えば、ぼくたちのディクテマシンは道具(トランスクライバーがコンピュータへ接続してトランスクライビィングをする時に利用するプロの道具)にしかすぎない。
道具をどのように上手に使いこなすか、その道具を知ることにより、使う人も、トランスクライバーも、道具がどのように改良されて使いやすさを生み出すか。大工さんは道具の使い方をよく知っている。「からくり」(組成)の原理が論理に基づいていなければならない。
技術の開発は進歩し、発展する。情報化社会を迎えて、モノラルからデジタルへの転換でも本質は普遍だ。ことばではトランスクライビィングという。
「テープ起こし」というのは俗語で概念ではない。出版社の編集工程から1960年代から1970年代に編集者の取材の工夫から生まれた。電子機器やコンピュータを適用した編集の革命でもあった。同時に速記者は速記記号にこだわっていた者は社会的存在から排除され所得を失ってしまった。速記も本質的にはショートハンドの性格をもっている。俗語は今やモノラルの深淵な落とし穴から抜け出せない。本質に対して衰退する知(古い知)は時代の科学技術の発展に逆行している。
無限の発展とは「もの」の本質(概念)から改善による改革で、やがて音声認識装置も登場するかもしれない。
使いこなす技術は気づき・工夫・改良にしかすぎない。イノベーション(技術改革)という。
まず思考の前提はことばの本質を求め、そこから始める。こうして思索は発展していく。論理的知識として概念化される。本質は形式を与えて存在を認識することができる。
道具を上手に使いこなす思考とは、快適(感覚)が改善を生み出す。欲求は無限だ。技術の永続的改良・改善の思想はトロツキーの永続革命が起源である。
気づきとは知の創造と知の生産の中間にある。産業化しているぼくたちの知の生産と良心による知の創造の中間にある。知とは本来コスト(商品)ではない。現実社会では人間性と産業化された商品(コスト)との受苦としての「バランス」において人間性の優位を無限に求めていく良心との葛藤の中にある。コストによる資本の支配を拒否する時もあるだろう。生き方に誠実なプロフェッショナルであれ!
だが、ここでは両方の知識が求められる。快適な環境といえる狭義としての媒体、原稿が自己精神において知として惜しみなく与える(放出)ことができる環境の構築を目指してきた。
自己の良心に従って仕事と向き合うことができることだ。それは正直・率直・誠実・個性を求めた。商人(プロ)の考え方とは異なる。
それからもうひとつは、中国が世界の工場となって、佐藤もジャパンブランドの中国製下着を購入している。聞くところによると、中国製下着は一般的に下着のゴムがきつい。ゴムがきつくて下腹部がゴムのきつさでしめつけられる。中国の人の下着は洗濯する度にゴムがのびてゆるんでズリ落ちそうになってくる、というのだ。コストの面でか、品質(生産技術)が悪いのか。
中国の女子工場労働者の歴史的で社会的な商品感は、「洗濯してもズリ落ちないようにゴムの弾力を強めにしめる」と思いこんでいる社会的常識、商品の品質に根ざしていると考えられる。品質(Q)とコスト(C)を意識している、といってもいいか?
資本主義の発展過程は大衆商品群を通して、それら商品群の品質が、人々の気づきも、その国の知恵として反映していく。「気づき」の歴史的発展過程なのであろうか? これは佐藤の高校2年生の時の問題意識から見た。
新宿で下着一枚1500円程度だが、半年ぐらいで買い替えている。しめつけられるのは快適とはいえない。閣下の下着は中国製なのだろうか?
人民の暮らしの知恵と知識が日本へ輸出されている。「気づき」はこうして満足感、生活感、社会的意識、経済の発展段階etc、経済的背景の意識の反映だと思っている。
ワコールが女性下着で中国へ進出した。中国の女性は美しくなるだろう。それとも中国製の下着か? 世界はデジタル化されて品質は劣化している。文化とコストの衝突なのである。
この一線を越える優位性を求めて、みなさんへコストの資本による支配に敏感に反応したい。
「バランス」の日本人性から、どうやって脱出するかも思考の前提になる。それは知の探求という哲学が求められるからだ。
本質・形式・要素(働き)・目的は新しい百科全書の別冊の登場がまたれる。
自分の気づきを発展させて事例を生み出し、みんなで共有し、この論理にしたがって論理展開ができるようになることだ。知の創出へつながるだろう。事例の創出は知識労働者の人材教育につながる。知の構築を多様化し、知識産業社会の知識資本の集積へ向けていかねばならない。
ホームページ『放送リポーティングの進め方』形式とは何か? について学べ。「気づいた価値は百万両」(松下幸之助先生)だ。
資本の哲学的本質はバランス思考(市場)からは生まれない。世界経済システムの破綻を目前にしたが、資本と当局のいたちごっこのゲームになるだろう。「人様に迷惑をかけないように」と言うべきときに、あなたは「危ないから気をつけてね」と言うか! バランスのコペルニクス的転回が必要だ。
弁証法的には資本の矛盾(市場)の矛盾を生み出し繰り返すだけだ。バランスとは俗世間の処世訓にしかすぎない俗語だ。哲学とは相容れない。資本はふたたび矛盾を露呈するだろう。
米欧資本主義のサブプライムローン関連の世界の不良債権額は3000兆円を超えるだろう。2009年秋には金融恐慌へと突入するかもしれない。現下の景気後退はだんだんと深化していく。それゆえ、わが国政治の本格政権の登場がまたれる。政局の現状認識を見誤ってはならない。わが国の行・財政の革命的改革が必要だ。
ひと言、わが国バブル経済崩壊による不良債権処理は地方においてはいまだ解決されていない。
国家による統制――中国国家資本主義(国家市場主義)も混乱をもたらすだけである。
英語で考えろ! 資本の集積は量から質へと変容する。変容の本質とは平成20年11月30日、テレビ朝日am10時オンエアーの自民党の細田幹事長と民主党の鳩山幹事長との対談で、自民党の「矛盾」のようだ。自民党は「ニッチもサッチもいかない」。やがて形式と内容の衝突へと直面する。質的変容とはこのような本質になる。
企業コラボレーションから社会パートナーシップへと発展させなければならない。
資本の持つ哲学的本質を社会パートナーシップへと止揚すること。
協業(相互互恵)から協働へと歴史は発展していく。
知識産業社会は情報化社会として進展し、知識資本の集積による教育の世紀で教育は一大産業になるだろう。
教育は多様な文化性をもつだろう。
テレビ・新聞・雑誌は「テレビ大学」「新聞大学」「出版大学」「企業大学」となり、大学は人材育成と先端科学研究の多様な文化性を発揮するだろう。
社会的パートナーシップの歴史的な進歩と文化性が開花する。
人間の満足感と欲求の歴史的変化と進歩は、日欧米の先進国でパラダイムの変化が起きるだろう。
(平成20年11月29日 web「営業情報」へ投稿、加筆修正しました)
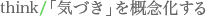
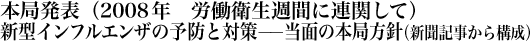
日本経済新聞 平成20年11月30日
新型インフル大流行時
最大40%が欠勤
厚労省指針 企業に対策求める
厚生労働省は29日、発生が懸念される新型インフルエンザに備えて民間企業が事業を継続するための注意事項を盛り込んだガイドラインを公表した。パンデミック(大流行)時には従業員の最大40%が欠勤すると想定。従業員の安全や需要の減少などに対応した事業計画をつくるよう求めた。(関連記事を社会面に)
同省は昨年3月に新型インフルエンザ対策のガイドラインを策定したが、企業が事業を続けるのに役立つ具体的な記述に乏しく、不満の声が出ていた。このため同省はガイドラインを改定、30日に開く専門家会議などを経て正式決定する。
公表したガイドラインは新型インフルエンザが海外で発生した場合から国内で大流行するまでの4段階を想定。流行の各段階における企業への影響を盛り込んだほか、職場の感染防止策や事業所への立ち入り制限、従業員の配置計画などの注意点を示した。
人員計画では、国内で感染者が出た初期段階では従業員の欠勤は数%にとどまるものの、流行時は20−40%の従業員が数週間にわたり欠勤すると予想。従業員を在宅勤務や時差出勤にして、従業員が感染するリスクを減らすよう求めた。
事業の縮小も検討するよう指摘。従業員の確保や取引業者の営業活動が難しくなる恐れがあり、各企業は混乱を避けるため、あらかじめ縮小する事業を決めておくべきだとした。また鉄道や病院といった社会機能の維持に欠かせない業種は、大流行時でも業務を続けられるよう求めた。
政府は新型インフルエンザが国内で発生した場合、最大3千200万人が発症、64万人が死亡する可能性があると試算。感染者の入国防止や医療関係者らを対象としたワクチン事前接種などの対策を打ち出した。しかしワクチンなどの効果には限界があり、大流行を織り込んだ対策づくりが課題となっていた。
日刊工業新聞 2008年(平成20年)11月28日 企画編集(広告)特集より
感染拡大を防げ!
職場のインフルエンザ
予防と対策を
病原性の高い新型インフルエンザの発生が懸念されている。先日は感染拡大の早期防止に向けた国の対策指針見直し案がまとまった。さらに、寒気が強まるとともに季節性インフルエンザの警戒も必要となっている。個人レベルでの治療や感染防止は難しくとも、予防による被害減少は不可能ではない。低コストですぐ実行に移せる対策・予防策を紹介する。
基本はうがい・手洗いの励行
“休まない”が患者増の原因に
新型インフルエンザ
新型インフルエンザとは毎年冬に流行する季節性インフルエンザとは異なり、数十年周期で大発生する疾病を指す。1918年のスペインインフルエンザ(スペイン風邪)は全世界で4千万人が死亡したと言われる。現在世界規模で発生している高病原性鳥インフルエンザウイルスは、元は鳥類のもので、まれに人に感染する。さらに、人の間で広がる高致死性ウイルスへ変異の可能性がある。これが新型インフルエンザ発生の原因になると警戒されている。
世界保健機構(WHO)によれば、新型インフルエンザの流行段階は現在フェーズ3。4になれば新型発生で、6でパンデミック(感染爆発)とされる。流行の時期・規模は予測しづらいがスペイン風邪(致死率2%)と同等なら入院患者は全国で約200万人、死亡者数は最大約64万人と政府では推計する。
季節性インフルエンザにも要注意
厚生労働省の新型インフルエンザ専門家会議は昨年、「職場や事業所での対策ガイドライン案」を提示。先ごろは1人でも感染者が確認された段階で学級閉鎖や映画館などの営業自粛を求めていく方針が明らかになった。しかし、企業単位の取り組みには温度差がある。東京商工会議所が9月に行った調査では、対策を実行した中小企業は1割強にとどまった。一方、季節性インフルエンザも流行の兆しを見せている。ウイルスは低温低湿な環境を好む。とりわけ12月と1月は罹患(りかん)者が無理をして出勤した結果、疾病が広まることが多い。予防接種は有効だが体内に抗体ができるまで2週間を要する。ましてや体力増強は急にできない。
すぐできる予防
明日から実施可能な予防策もある。新型インフルエンザ専門会議が示す予防策のうち即実行できるのが手洗い・うがいの励行とマスク着用である。感染は、唾液などと一緒に飛散したウイルスの吸入で起こる。マスクは最も手軽な飛散防止対策であり、同会議では買い置きを勧めている。ウイルスは極微小なためマスクによる吸引防止は難しいとされてきたが、最近、抗ウイルス素材を使った感染予防マスクが登場している。
帰社・帰宅時に忘れてはならないのが、うがいと手洗い。のどはウイルスが増殖をはじめる代表的な場所で、まめにうがい薬で洗浄すれば感染防止に役立つ。また、ある医療関係者は「人は無意識に目や口を触る。ドアノブや吊り革を持った手から感染する例は極めて多い」と油断を戒める。帰るなり手づかみで食べるのもリスキーな行為だ。うがい薬や除菌液、洗剤の常備は予防の第一歩と言える。
学校や病院での集団感染も要注意。これまでは手洗い励行やアルコール清掃などが具体策な方策とされてきた。先頃抗ウイルス機能を持つ壁紙や塗料が国内メーカーから相次ぎ発表された。鳥インフルエンザにも効果を発揮するという。施工に費用と時間を要しても完成すればその日から効き目が期待できる。
有力各社の製品紹介
関西ペイント
関西ペイントの「アレスシックイ」は、高病原性インフルエンザH5N1ウイルスの感染力を30分間で99.6%以上低減する漆喰コーティング材を原料に開発した。ローラー施工も可能で、新型インフルエンザのパンデミックを抑止し得る塗料として注目される。
また、通常のインフルエンザ(A型H1N1)に対しても優れた抑止力を発揮。集団感染の危険性がある病院・老人ホームなどの医療関係機関や学校・幼稚園といった教育機関に向けた予防策として高い有効性を持つ。
鈴木油脂工業
鈴木油脂工業は工業用手洗い洗剤、クリーナーなどケミカル製品の製造・販売を行う。代表的な製品に「SYKローヤルエース」と「オフィスソープ」がある。どちらも洗浄だけでなく殺菌効果のあるインフルエンザ予防に有効な手洗い洗剤だ。ローヤルエースは指紋の中まで洗浄する滅菌・消毒を得意とする強力洗浄剤。手肌にやさしい洗浄成分とアロエエキスを配合し、手荒れに配慮している。オフィスソープもアロエエキスの保湿剤を組み合わせ、泡状になって液だれしない性質を持つ。
http://www.syknet.com/products/washstand/sykroyalace.html
ダイワボウポリテック
ダイワボウポリテックは原綿から不織布までの一貫生産体制を持つスパンレース(SL)不織布の大手メーカーとして、コスメや衛生材料向けなどに重点展開している。最近では、京都産業大学(鳥インフルエンザ研究センター)との産学共同研究開発による抗ウイルス不織布を使用したサージカルマスク「プロテクシールド」の販売を企業向けに開始した。これはインフルエンザ感染予防に特化した商品であり、販売は好調にスタート。引き続き感染予防商品の開発および拡販を図る。
http://www.daiwabo.co.jp/ir/pdf/2008_1027a.pdf
明治製菓
明治製菓は発売25周年を迎えた「イソジンうがい薬」に新フレーバーを追加。おなじみの「カバくん」のキャラクターで、ポビドンヨードが細菌・ウイルスに幅広く殺菌力を持つことを明確に伝えるデザインに、パッケージをリニューアルした。
「イソジンうがい薬P」は、味が苦手な女性や子どもを含むファミリー層向け。のどの殺菌・消毒のほか、口臭除去にも効果がある。
かぜ、インフルエンザ予防として、うがい・手洗いを習慣づけて、家族の健康を維持しよう。
http://www.meiji.co.jp/drug/isodine/products/index.html
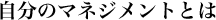
■読売新聞 平成20年10月5日
オンの才人 オフの達人 リーダーの仕事学
女性社員に経験伝えたい
資生堂副社長 岩田 喜美枝さん 上
労働省(当時)で男女雇用機会均等法(均等法)や育児・介護休業法の制定・改正などに取り組み、自ら仕事と育児を両立させながら、働く女性を支援してきた。2003年に厚労省を退職後、「民間企業で頑張りたい」と、資生堂に入社。背景には、民間企業で働くことへの強い思いと、学生時代からの職業観があったという。
職業観は「生涯仕事を」
1971年に大学を卒業したころ、「生涯仕事を続けたい」というのが私の職業観でした。しかし、当時の日本企業に大卒女性を公募する企業はほとんどありませんでした。「女性は結婚して仕事を辞める」のが前提で、就職したら女性は補助的な仕事に従事して、2、3年で寿退職するのが当然。今のような、女性の登用や育成とは無縁な世界でした。
そんな私の職業観を満たしてくれたのは公務員だけでした。女性を採らない省庁がほとんどで、労働省だけが毎年コンスタントに1人だけ採用していたのです。32年の間、色々な経験をさせてもらい、そこで働けたことは本当に良かったと思います。
「ぜひ民間へ」と再就職
中央省庁では退職勧奨が早く、60歳の定年前に次の職場を打診されます。私にも次の仕事の話が来ましたが、「大学を卒業したころは民間企業へ行けなかったけれど、今なら働ける。ぜひ民間で仕事をしてみたい」と思い、その話は断りました。
そこから、私の再就職活動が始まりました。自分が働きたい会社、私を雇っていただける会社はどこか、を考え、その第一希望が資生堂でした。CSR(企業の社会的責任)という言葉が出始めたばかりのころから「社会性の強い会社」というイメージがあり、多くの女性が活躍し、お客様の大多数が女性。「ここだったら私を雇ってくれるのでは」と、当時の池田守男社長に資生堂で働きたいと気持ちを伝えたのです。
今年、副社長に就任してから特に、社員に話をする機会が増えました。圧倒的に女性社員が多い会社ですし、自分自身の仕事と家庭の両立を経験談として話し、「あなたたちも両立は絶対にできるから」と伝えています。省庁時代、様々な家庭環境に置かれた先輩女性たちが、仕事と家庭を両立する姿を見てきたことは、私の参考になりました。今、この会社でも、自分の経験が社員たちの参考になれば幸せです。
私の「生涯仕事を続けたい」という職業観は、母親からの影響です。母は小学校の先生でした。育児のため退職し、専業主婦になりましたが、高校教師をしていた父がもし倒れたら、母は3人の子どもを抱えて路頭に迷うことを心配していました。私には「経済的に自立してほしい。そのために、自分はいくらでも手伝うから」と言ってくれ、実際、子育てではたくさん手伝ってもらいました。
労働行政に携わりながら娘2人を育て、地方への単身赴任も2度経験できたのは、夫や家族のサポートに加え、自分自身も意志を強く持ち続けたから。これまで、仕事を辞めようと思ったことは一度もありません。仕事が面白くて仕方なく、私の仕事好きのにおいは、周囲に幅広く伝わっていることでしょう。(続く)
いわた・きみえ さん
1947年香川県生まれ。東京大学教養学部卒。71年労働省入省。2003年、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長を最後に退官し、資生堂に入社。取締役執行役員、同常務を経て、現在、代表取締役副社長。政府審議会委員なども務めている。
資生堂
1872年創業。化粧品、シャンプー、医薬品などの製造販売、輸出入を手がける。コーポレートメッセージ「一瞬も 一生も 美しく」のもと、2008年度からの3か年計画では、アジアを代表するグローバルプレーヤーとして、世界に通用する経営品質の確立を目指す。08年3月期の売上高は連結ベースで7235億円。
■読売新聞 平成20年10月5日
オンの才人 オフの達人
「大人」の可能性広げたい
プロデューサー 残間 里江子さん
「それでいいのか蕎麦(そば)打ち男」などの著書で、団塊世代に、定年後の新しい生き方を提案してきた。従来の中高年イメージを脱した大人像を作り出し、若さと可能性を感じさせる「シーン」と「役割」を提供しようと、会員組織「club willbe」の設立準備に奔走しており、10日からメンバー募集を開始する。
死ぬまでできる仕事を
小中学校時代、それぞれ半分しか学校に行けないほど病弱で入院生活が長く、他の入院患者が亡くなるところも目の当たりにするなど、生と死が一枚の皮膜で遮られているような環境で育ちました。そのためか、「動けるうちは倒れるまで」と頑張りきるのが習いになり、「この仕事が終わったら次はこれ」と、これまでに数多くの仕事をこなしてきました。
しかし昨年、友人で東京五輪の競泳選手だった木原光知子さんが亡くなるなど、同世代の人たちの訃報(ふほう)に接する機会が増え、自分が、もう死んでもおかしくない年なんだと思い、死ぬまでできるような継続的な仕事をしたいと考えるようになりました。
北欧が長い時間をかけて、高齢化社会になったのに対し、日本は「団塊」という人数が突出した世代がいて、高齢化が急激に進んでいます。まだそんなに年を取っていないが、確たる居場所もない彼らは、何かやろうと思っていても、半身ひるんでいる状態。約5500万人いる50歳以上の大人が、何もしないまま衰えていくのは、国にとっても問題だし、本人たちも未練が残るのでは。
来年1月に会員組織
2007年問題は、65歳まで働く人が増えて、2012年問題に先送りされた形になっていますが、2012年から何かやるというのでは絶対に遅い。「アラ5、アラ6」(50、60歳前後)世代はいろんなことをやる、という意識が2010年には世間に定着していないとまずいと思い、今年の春から企画書を作ったり、約100人の文化人に賛助会員の承諾書をもらったりし、8月は企業の社長らに協賛をお願いする手紙をひたすら書いて、来年1月からスタートできるよう準備を進めています。
クラブでは、セミナーやパーティー、コンサートなどを通じてコミュニケーションの場を提供するのですが、賛助会員にナビケート役を務めてもらうなどして、肩書を越えた付き合いができるようにしたいと思っています。ただ、「有名文化人カルチャーセンター」のようにするつもりはなく、企画は会員と一緒に考えます。例えば旅行なら、どういう旅行がしたいかを会員から聞き、旅行会社に提案して、既存の団体旅行の枠を破るようなものにしたいし、賛助会員の取材旅行に同行させてもらうことなども考えています。
50歳代以上を主な対象にしていますが、30、40歳代の方の参加も歓迎しています。大人世代は、下の世代の面倒見もよくて、あっさりしている人が多いです。いろんな経験や知恵を、頑(かたく)なにならずにいえる最初の世代だと思うので、「大人の見本帳」として最大限に活用してほしいと思います。
オフがあまりないせいか、家の中にいるのが、非日常になっています。昼間3時間以上、家にいられたら、うれしくなってしまいます(笑)。家にいる時は、唯一仕事と関係のない洗濯や料理など家事をしていますが、ここだけはしがらみがないので、気持ちが休まります。(談)
ざんま・りえこ さん
1950年宮城県生まれ。静岡放送アナウンサー、雑誌記者などを経て、80年にキャンディッド・コミュニケーションズを設立。出版プロデュースや文化イベントなどを多数企画・開催している。昨年、静岡県で開かれた「ユニバーサル技能五輪国際大会」では総合プロデューサーを務め、成功に導いた。club willbeのメンバー登録は、http://www.club-willbe.jp/info3.htmlへ。
大学を卒業してすぐに起業することはよくない。ビジネス社会で「仕事とはなんであるか」をいちから勉強し、心構えを学び、仕事の知識と技術(ビジネスインテリジェンス)の原理・原則・基礎・基本をからだで覚え、前向きな工夫や改善の姿勢を学び、そこにどのような「仕事の思想」を身につけ、独立・起業できるようになるのは普通40歳を過ぎた頃だ。
報道をとおして多くの人の「仕事観」を学んだが、あまり自己の内的論理を知ることはなかった。
ぼくたちは在宅ワーカー・独立自営業者である。本質的に雇用労働者と異なる。
メディアミックス&ソフトノミックス/は今年【「自分らしくを生きる」生き方】を求めた。ここには自己の論理が貫徹していなければならない。自分の生き方は自分で考えることだ。多くの人は自己の生き方も仕事も自分に「都合のいい方便」になっている人が多い。
仮の生き方ではなく、自分の求める生き方を持てないでいる。仕事と自分の関係が「方便」になってしまって、「会社の命令と報告」が自分らしくを出し切れないでいる。自由が「出せ」ないのだ。チャレンジしたい精神と仕事の質にバランスを失っている。
自己の生きる内的論理が貫徹できない。自己の精神活動の遠いところに「打たれ強さ」を強制されて、多くは「雇用労働者」の「精神」として仮に演じて(妥協)いないか、会社のいわゆる社員の実像だ。
「権力による“ああ言えば、上祐”の世界」だ。沈黙による「方便」という自己の良心(素直になれない、抵抗)をみつめる。社会の矛盾なのである。自己の有とは「身の丈大」の自己の力でしかない。社会的存在における自己の力をみつめる。良心のあり方とは方便という「社会的バランス」でしかない。ここをいかに、どうやって越えていくのか?
自己の思想的営為はこうした「方便」と紙一重の境界をこえて広がる自己の希望の世界なのである。教育と学習をへてつかむ知恵の力で生きている。あいまいな日本語による表現だが自分らしく英語で考えてみよう。知は細分化する。
PHP研究所からたぶん2000年に発行された読売新聞社校閲部著の「日本語を英語でいかに表現するか」の書籍(ハンドブック)があるが、このハンドブックの思考をヒントに自己の精神活動をみつめてはいかがか。佐藤にとって逆説的だが……。
みなさんは仕事が快適であると感じていると思うが、本局では事業目的にマスコミ業界を選んで求めてきたのは、佐藤の深い思いがここにある。自己実現にもっとも近いころに仕事を求めた。これは仕事の環境のひとつといえるだろう。自分に自然な「正直・率直・誠実・個性」でありたい。
少なくても75歳を過ぎるまで現役でお仕事ができる環境にある。自己の経済活動に対する自由な意志決定権をもっている。
しかし、政府も省庁も「年寄りじいさん」の感覚で社会労働環境政策をつくっている。
ぼくたちは新しい21世紀の社会労働環境が生まれることを求めている。働き方いろいろといって、けっきょく雇用労働者中心の考え方から抜け出す気概もない。人間的生き方の個性を無視した政府は金太郎飴人生を描いている。バブル経済の崩壊でこの構図は破綻した。人間として自由に生きていくにはどんな施策が必要か? 頭が硬直している。
上記の新聞記事は小見出しだけに中身がある。
みなさんは戦後生まれである。
明治、大正、昭和戦前生まれの人たちとは戦後生まれの生き方は異なる。多様な生き方、働き方ができるような社会の到来を待っている。
【「自分らしくを生きる」生き方】に希望の原理と自己の内的論理をつくり出していかねばならない。
在宅ワーカー・SOHO独立自営業者は現実的、歴史的には1990年に生まれた在宅で情報機器を操作し生業とする半分労働者的意識と半分自営業者的意識をもった知識労働者である。ここに新しい生き方と働き方の現実が現れている。2008年、歴史的・社会的存在となっている。けっきょく政府は企業の人件費抑制を狙い、いわゆる「女の税制の壁」という隘路を働く者にいまなお強制している。
21世紀の知識産業社会へ発展すべき「政府の施策」が知的女性労働の生産性向上の阻害要因にもなっている。行財政の構造改革は道半ばである。
いわゆる『在宅ワーク』に関する雑誌記事や書籍を「拝読」しても政府の「人件費抑制政策」に迎合する視点で、本質にせまった分析ができないでいる。自分も大学の「雇用労働者」だ。未知の世界(未体験ゾーン)のことで分析の発想すらもてないでいる。硬直した「知の貧困」の根は深い。
確か立教大学の社会学研究に外から組織の中に入って「組織」を体験し、分析する「学科」があることを10年近くも前に知った。会社のOBもよいが企業内論理だけでは知識は貧困だ。硬直している。知識労働にはふむきだ。報告書ふうの統計学もよいが、研究成果を個性と自分のこころを持って意図を「伝え、伝わる」ことが大切だ。学問への豊かな良心だと思う。すべてが、反面教師の研究成果でしかない。「学問としての研究」の視点が欠落しているのである。
この豊かな良心は研究の方法論に立脚していなければならない。研究そのものの真価だ。
政府の施策に反映できない。思い込みの頭が、政策に弾力性を失っている。
人材と「賃労働」、資本の関係は人間の良心によって半分は解決できる。21世紀の方向である。こまわりのきく中小企業こそが未来への光である。人間らしい未来を考えると大企業の時代は終わる。
ゲーリー・ベッカー教授の「人的資本」の人間を商品と考えるイデオロギーからの袂別が大切だろう。本局はいわゆる「職場の論理」を「家庭」に持ち込まない。
人間の多様な生命活動のひとつに経済活動があるが、人間の生命活動のすべてではない。
人間は生きていくうえで多様な生命活動をもって生きている。その多様性(生命活動の諸相)を否定する、いわゆるベッカー経済学に死を! ノーベル賞は経済学に口出ししないほうがいい。生活(家庭という場)と労働(職場という場)が自分主導で調和している在宅就業こそ大切にしよう。
行財政改革の本道をしっかり定め、働く者の精神の解放と充足を拒否し続けたわが国高度経済成長に対するキャピタリストのホラと美化に迎合する団塊の世代も、それに気づき、逆説的な反撃にまもなくあうだろう。
そして、新しい21世紀知識産業社会はあくまで企業間競争の「産業社会」で、資本の論理と「賃労働」の論理の「衝突」のなかで「こころのあり方といえる快適な環境」――共同の作業――チームワークが求められる職場とちがって、知識労働者の立場から働く者を特定の場に囲い込む職場を否定せよ――を優先し、働く者が尊重される仕組みを求めていくことだ。
ソーシャリストのドグマ――物質的向上だけ――に依拠して人間の精神的解放を逆に抑圧してきた歴史はいま「どこを走っているのか?」、現在地を正しく定めることから各人の精神的活動が始まる。希望の原理を求めて「自分らしくを生きる」こころの時代の政治・経済のあり方と社会的な意識・文化的変化を必要としている。
『人間の満足感と欲求の歴史的変化と進歩』という作文は佐藤の高校生時代のサークル活動の習作だが、社会の文化的受容と個人的な文化的意識の生活の場の創造であって生活の文化的意識へ還元されていく。ソフトノミックスの文化がここから生まれてくる。それは文化的生活の創造の眼(気づき)がここから生まれる。
画一化を打ち破る思想だ。生活と労働の融合がもたらす文化の創造とは働くことの世界の広がりを更に求めていくことだ。多様な個性が事業の原動力なのである。
戦後体制から新しい時代へ!
かくして市場原理主義は破綻した。自民党には「責任はない」とは言えない。新しい時代をむかえて、わが国政治的民主主義の政治的モラルを確立すべきときだ。真の構造改革がスタートする。行・財政の大変革である。
青年・若者が自由に活躍できる時代の幕開けである。
パラダイムの世界的な転換の時でもある。
自己責任のことばについて言いたいことがあるが、いまは自由主義(市場原理主義)に対し「あれもだめ、これもだめ」の新しい真の人類の平和な未来を願っている。
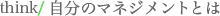
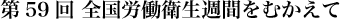
2008年(平成20年)10月1日〜7日
スローガン「あなたが主役 明るい職場と健康づくり」
全国労働衛生週間は、働く人の健康の確保、増進を図り、また、快適に働くことができる職場づくりに取り組む週間です。
昭和25年に第1回が実施されて以来、本年で第59回を迎えます。
この機会に自主的な労働衛生管理活動の大切さを見直し、積極的に健康づくりに取り組んでみましょう。
本局では今年、新型インフルエンザに対する各人の自主的な取り組みについて、その概要を発表します。新型インフルエンザは風邪をひくという一般的なことではなく、感染症の一種でインフルエンザウィルスによる飛沫(ひまつ)感染、接触感染による感染症です。この冬インフルエンザの大流行がもしあったとしたら、そのリスクについて予知する対策です。
電車での通勤のリスク、学校封鎖、職場封鎖、工場封鎖など予測され、インフルエンザウィルスによって家族が感染するという事態が発生するかもしれません。
企業では「在宅勤務」が有効な対策として考えられていますが、本局ではぼくたち本来の在宅ワーク、SOHO独立自営業者としてどのように自主的に取り組むか、それが今年の課題となります。
このリスク管理は厚労省のヒット作となるかどうかは別として、わが国が取り巻く地政学的な立場からも、アジア諸国がわが国の厚労省のリーダーシップのもとに外交的にも国家政策に対応するものです。
かつて世界的な流行の疾病などありましたが、今は世界がグローバルになり、船舶交通によってばかりでなく飛行機で海外が身近に結ばれるようになりました。
今年のテーマは世界的なインフルエンザの大流行に対して、食料等食品消費財の輸出入に携わる人々のリスクも予測され、インフラが寸断されマヒされる事態も予測されます。
こうした事態は食の危機も流通によってもたらされたり、職場のマヒも予測され、社会全般に広がっていくリスクをもっています。
新型インフルエンザの大流行に対して各人の取り組み、まず家庭の防衛と食の防衛、予知されるリスクに対する対応も必要かと思われます。
この電子文書はみなさんの予知、気づきによる家庭の防衛と仕事の防衛を一致させ、それへの取り組みを喚起するものです。
また今年はみなさんの充分な睡眠に対する心がけも健康を維持していくうえで大切なことだと考えています。できれば規則正しい生活が望まれますが、ご主人の職場環境にも影響されます。家庭は社会を構成する最小単位ですが、家庭を経営するみなさんにとっては充分な危険を予知し、みなさんの気づきによる取り組みがどんなに大切なことであるか、ことしの労働衛生週間は在宅ワーカー、SOHO独立自営業者として取り組みられるよう希望します。
新型インフルエンザに対する何かのリスクに対する気づきがあれば本局の労働衛生として取り組んでいきたいと考えております。気づきをお寄せ下さい。
この電子文書は新聞記事から構成されます。
まずインフルエンザの大流行に対する現実的な視角
インフルエンザに対するあるべき危険予知
インフルエンザに対する各人の心構えと対策
大きくこの3点に分けて自分の考え方を整理し取り組んでいただけますようお願いいたします。
(平成20年9月29日「本局発表」に投稿、「第59回労働衛生週間へ向けて」新聞記事から構成されています)
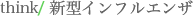
日本経済新聞 平成20年7月31日
新型インフル流行に備えを
企業にリスク対策促す
厚労省が指針改定案
厚生労働省は30日、新型インフルエンザ専門家会議を開き「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」の改定案を承認した。改定案では企業が直面するリスクの全体像や、事業活動を継続、縮小・休止するために留意すべき点を具体的に盛り込んだ。一般からの意見募集を経て、9月に正式決定する。
職場ガイドラインは07年3月に策定され、今回の改定は新型インフルエンザ発生時の社会経済状況の想定を提示することで、事業者の共通認識を図り、事業継続計画の策定を推進することが狙い。具体的には新型インフルエンザ発生時は、欠勤率は20―40%、欠勤日数は10日間程度が見込まれるため、あらかじめ人員計画や重要業務の継続を検討しなければ、事業継続が危ぶまれる事態になりうる点を明示した。
また事業者が対策を検討するために必要な感染予防の知識を拡充するため、感染経路や飛沫(ひまつ)感染・接触感染に対する具体的な予防策の詳細を示した。新型インフルエンザ行動計画の立案を促進するため、必要な項目を提示した。具体的には①職場における感染リスク評価の方法やリスクを低減する方法の例示②新型インフルエンザの特徴として長期戦に備えなければならないことや他地域からの救援の見込みがない―ことを盛り込んだ。さらに新型インフルエンザ発生時の業務量の時系列イメージ、人員計画を例示し、従業員の計画的な自宅待機や班交代制の検討などを示した。
新型インフルエンザが発生した場合、事業者には感染拡大スピードを抑えるため、不要不急事業の自粛や社会機能維持にかかわる事業者は感染予防策を講じつつ、重要業務を継続することが要請される。各企業では対策に取り組む機運は高まっているものの、現時点で新型インフルエンザ対策を実施している企業は1割程度とされる。厚労省は8月上旬にホームページで改定版を公表し、企業の新型インフルエンザ行動計画の策定を促す。
日本経済新聞社広告局 平成20年8月27日
シンポジウム 採録
いま、企業に求められる新型インフルエンザ対策
新型インフルエンザが世界的に流行する可能性が強く指摘されている。国家はもとより、企業も、危機管理の観点から新型インフルエンザ対策を構築しておく必要がある。そうした緊迫した状況をにらみ、「いま、企業に求められる新型インフルエンザ対策」と題するシンポジウムが、8月6日、専門家4氏を招いて経団連ホール(東京・千代田)で開かれた(主催=日本経済新聞社広告局、特別協賛=東京海上日動リスクコンサルティング、サラヤ、シスコシステムズ)。会場は満席となり、新型インフルエンザに対する関心の高さをうかがわせた。
基調講演 新型インフルエンザの脅威と被害予測
国立感染症研究所ウイルス第3部長 田代 眞人氏
大流行は必至、ワクチン接種に国は十分な説明を
高病原性(強毒型)の鳥インフルエンザが、ヒトの新型インフルエンザに変異し、世界で大流行を起こすことが危惧されています。現在問題になっているH5N1型という鳥のウイルスは、世界中で猛威を振るい、大量の鳥を殺しています。しかも強い病原性を持っており、トラやネコなどのさまざまな哺乳(ほにゅう)動物にも感染して殺しています。ヒトについても、感染のリスクは低いものの、すでに400人を超える患者が確認されています。
ほとんどの鳥インフルエンザウイルスは弱毒型のウイルスですが、H5とH7のうちの一部が強毒型に変化しています。強毒型ウイルスは、ニワトリでは血液に入って全身感染を起こし、数日以内に100%殺してしまいます。ヒトの場合でも、いったん感染を受けると重症となり、63%の患者が死亡しています。適切に治療しなかった場合にはほぼ100%が死亡します。
さらに大きな問題は、現在はまだ鳥の間で流行する鳥型のウイルスですが、これが遺伝子の突然変異によって、ヒトからヒトに効率よく感染伝播(でんぱ)が広がるヒト型の新型インフルエンザに変化する危険があることです。しかも、これまでの新型インフルエンザが、鳥の弱毒型ウイルスに由来していたのに対して、いま問題視されているH5Nlは強毒型のウイルスなのです。世界中のほとんどの人が、この新型ウイルスの感染をうけて重症化する可能性もあり、大流行による健康被害は膨大なものになることが懸念されています。
新型インフルエンザの大流行は本当に起きるのか、ということが議論されていますが、これは必ず起こります。過去の120年の間に5回の新型インフルエンザ大流行が起きているのです。いつ新型が出てきてもおかしくないという現状です。H5型以外の弱毒型の可能性もありますが、従来のインフルエンザと異なる強い病原性を持ったH5型の新型インフルエンザ大流行が、世界同時に起こることが、最悪のシナリオとして心配されているのです。
多くの人が同時に感染発症すると、社会機能へも大きな影響がでてきます。まず医療サービスは過度の負荷が生じて破綻するかもしれません。食糧供給などのライフライン、エネルギー供給、物流、交通など、社会のインフラ機能が一斉に停滞・停止することも考えられます。行政サービスなども止まる可能性があり、そうなれば社会の安全保障、治安維持も大きな問題となります。カナダの経済団体や世界銀行などによる試算では、新型インフルエンザ大流行の際には、1929年の世界大恐慌を上回る経済破綻が起こると推定されています。新型インフルエンザの大流行は、世界規模の危機管理の問題であり、単なる医療問題ではないのです。
20世紀最悪の新型インフルエンザ大流行は1918―19年のスペイン風邪でした。当時の世界人口18億人のうち4000万〜1億人ぐらいが死亡したと推定されていますが、現在は3倍以上の67億人が地球上で暮らしています。それだけ人口密度が高くなっているので、主に飛沫(ひまつ)感染で広がるインフルエンザにとっては非常に都合の良い状況です。しかも当時の交通手段は鉄道と船であり、ウイルスが地球を1周するのに1年近くかかりました。これに対して2003年に流行した重症急性呼吸器症候群(SARS)は1週間で世界中に広がりました。同じようなことが次の新型インフルエンザでも起こると予想され、その影響は過去に例を見ないものとなるでしょう。
問題は、そのときになってワクチンの開発とか、抗ウイルス剤の増産、医療の確保などを開始しても到底間に合わないということです。最悪のシナリオが現実化することを前提に、十分な事前準備をしておかなければ対応できないのです。
対策の基本戦略は、鳥の間での流行をコントロールすること、鳥からヒトへの感染伝播を阻止すること、どこかで新型インフルエンザが発生したら、その局所で早期に封じ込めることです。さらに、国内への侵入を遅らせ、流行規模を低く抑えて、健康被害を最小限にとどめるための準備を出来る限り実施しておくことです。これには、隔離や外出制限などの行動規制や、医療サービスの確保、抗ウイルス剤やワクチン政策が含まれます。これらの公衆衛生学的あるいは医学的な対応を、いかに早く、かつ徹底して行うかが重要なのです。さらに、二次的に起こる社会・経済活動の麻痺(まひ)や崩壊を防ぐために、各部署における事前準備計画と緊急対応計画の作成とその実施が不可欠となります。
事前にワクチンを製造・備蓄しておけば、緊急時の製造時間を大幅に短縮できます。日本では今年度末までに3000万人分のH5型事前ワクチンの備蓄をする予定です。事前ワクチンの効果は完ぺきではありませんが、H5型ウイルスの流行に対しては、交差免疫によって、重症化や死亡を低減する効果が期待されます。その使用方法については今後十分な検討が必要ですし、これを誰から接種するかというのも大きな問題です。また緊急時に作るワクチンでは早急に接種を行う必要があるので、十分な有効性と安全性を確認するために時間を割くことは難しいでしょう。従って、ワクチン接種による健康被害はある程度は許容せざるを得ません。これらについて、事前に国民に十分に説明し、理解と合意を得ておくことは、行政に課せられた大きな責任であると思います。
特別講演①
新型インフルエンザ・パンデミックに対する企業の事業継続戦略
東京海上日動リスクコンサルティング
BCMコンサルティング第1グループ
グループリーダー 青地 忠浩氏
企業のBCM構築が不可欠
定期的な教育・訓練が重要
全身感染、重症疾患を生じるH5Nl亜型ウイルスがパンデミック(大流行)を起こせば、事業・業務の縮小や停止を避けることは難しく、企業の存続すら危ぶまれる事態が考えられます。各企業が適切に対応しなければ、社内外に感染を拡大させ、社会機能や医療体制の破綻から死亡者数の増加、経済的な混乱を助長する可能性があります。
各企業の取り組み状況を見ると、パンデミックは企業の「事業継続」の問題という認識が不足していると見受けられます。企業が「何もしない」という選択肢はないはずです。すべての企業が取り組むべき問題だと認識すべきです。
対策を促進するために、事業継続マネジメント(BCM)の構築手順やアプローチを、新型インフルエンザ対策にも適用することを推奨します。各企業のBCMの目的・目標を達成するための方法、つまり事業継続戦略は、実現可能でかつ費用対効果の高い方法を経営者が選択します。パンデミックに対しては、①社内外への感染を抑止するために、早い段階で積極的に事業・業務(製品・サービス・オペレーション)を縮小・停止させること②社会機能の維持とそのサポートにかかわる業務、会社の存続に必要な重要な事業・業務については、十分な感染抑止対策を施した上で継続させること――この二つを事前に計画し、実行できる体制を整備することが基本的な戦略になります。「流行を遅延させ、流行のピークにおける患者発生数および死亡者数を可能な限り抑制し、医療体制や社会機能の破綻を阻止する」という国家戦略との整合を図りながら、企業に課せられた役割、社会的責任を果たすことが求められます。
BCMでは、経営者や事務局のリーダーシップが欠かせません。社員の安全を確保しながら、どの範囲で事業・業務を継続させるか、いつ業務の縮小・停止、再開を行うかという経営的な判断が求められます。業種や業態、業務プロセスを考慮した分析と検討を、経営者と現場が一体となって行うことがポイントです。
危機対応力向上のために、発生前から情報収集と分析、準備や調整に努めること、感染拡大の状況に対応できるように計画に柔軟性を持たせること、対応計画と行動要領を“見える化”することが有効です。何よりも重要なのは、経営者を含む対策本部のメンバー、事業部門、従業員を対象とした教育・訓練を定期的に行うことです。従業員に対する基礎教育や、対策本部メンバーの意思決定訓練などの基本から入ることをお勧めします。
特別講演②
企業が行う感染対策と事例
サラヤ 代表取締役社長 更家 悠介氏
できることから確実に実施
衛生予防策でQOLの改善も
感染というのは付着、侵入、定着、増殖と進むことで起きるのですが、鳥インフルエンザの場合は非常に強毒性なので、付着とか侵入のところでも、もう起こったのと同じくらいのリスクがあると思います。ですから付着をやめさせる、感染経路を断つことが予防の原則となります。感染と標準予防策ということでいえば、何といっても予防は治療に勝るのです。
社会的に影響力のある企業はともかく率先して、いまからできることは確実にやっていただきたいと思っています。世界的な感染などの大事件が起こってからではなかなか間に合わないからで、常日ごろからの備えがとにかく大切だからです。鳥インフルエンザの事例で見ても、やはり治療よりも予防のほうがコストも安いのです。病気にならないということは、クオリティー・オブ・ライフ(QOL)という意味からも重要です。
具体的には標準予防策、例えば手指の衛生、個人防護具の活用、せきエチケット、物品環境の洗浄消毒など、それぞれのカテゴリーにおいて企業は準備を進めるべきです。これらをガイドラインとしてまとめるだけではなく、日ごろから従業員に徹底することによって、いざというときにもちゃんとした動作がとれるということになるわけです。
まずは教育研修の一環として、衛生にまつわる教育ツール、マニュアル、講習会などを各企業の中で整備をしていくことが大事だと思います。周知徹底という意味からも、ポスターやステッカーの作成、活用などから始めたり、自社のホームページに衛生コーナーを設けて、手の洗い方などを掲載するのも効果的です。
特に高頻度でヒトへの感染が起こっているアジア地域にオペレーションのある企業はきちんとした衛生知識と対応が不可欠で、また、品質の確かな衛生物品の手当ても重要なことです。出張などで海外に行かれる社員のために石けんやうがい薬の入った衛生対策キットなどを作り、清潔習慣を徹底するのも有効だと思います。そのためにも、いかに現場の方に理解していただけるかがポイントになるでしょう。
うがい器や手洗い設備を設置するとなると、どうしても初期投資はかかります。しかし、予防的なコストは必ずアメニティー、QOLの改善、病気の予防にもつながりますので、そういった意味からも衛生予防策を検討いただければと思います。
特別講演③
パンデミック対応のリスクマネジメント
シスコシステムズ インターネット ビジネス ソリューションズ グループ(IBSG)パートナー 石井 延幸氏
経済的損失を数字で把握
テレワークも視野に具体策を
今日の日本社会や企業活動は中国をはじめとするアジアとのかかわりなしに持続することは難しくなっており、海外で新型インフルエンザが発生し、パンデミックが起きた場合には日本企業の活動に大きな影響が出ることは必至と考えられます。新型インフルエンザが発生した場合、社員が職場にいて業務をすることが前提となっている、従来型の事業継続計画(BCP)では対応できなくなっています。
数年前にアジアで発生したSARSの流行時、シスコのアジアパシフィック支社ではテレワーク(ITを駆使した在宅勤務)を最大限利活用することで業務の継続を実践しています。当然すべての業務を在宅勤務でこなすことは不可能ですが、ホワイトカラーを中心としたデスクワークの大半にテレワークを適用できることは弊社グループで実践済みです。企業リスクマネジメントの観点からは不測事態の発生に際し、何を守っておくべきかという絞り込みが重要ですが、それにはまず、パンデミックによる自社の経済的インパクトを把握することから始める必要があります。例えば、業務が1時間停止するといくら売り上げが落ちるのか、あるいはいくらコストが上がるのかなどといったことをきちんと数字で把握しておくことが重要です。しかし、企業の存続には経済的にインパクトの大きな業務だけを守ればすむというものではありません。例えば研究開発(R&D)などを競争力の源泉とする企業でさえ、その重要度を経済的なインパクトだけで図ることは不可能だからです。このため目に見える定量的な影響と共に、企業戦略上の重要度を考慮することで本来、企業が生き残る為に必要な業務や財を絞り込むことが出来ます。
限りある予算枠の中で、どの業務を継続の対象にするのか、どの事業は継続にはそれほどお金を掛けず、むしろリカバリーをスムーズに行える環境を整えておくのかといった優先順位はここで議論する必要があります。特にリカバリー対策を検討する場合には、目に見える財だけでなく、知財やブランドといった目に見えない財(インタンジブルアセット)も含めアセットの管理が重要なポイントになります。
また、少し異なる観点として、企業が社会市民としての役割を果たすことも求められ始めており、コミュニティーとの連携や国・自治体との平時からの情報共有化が重要になっています。
日刊工業新聞 平成20年8月4日
中堅・中小・ベンチャー
新型インフルエンザ対策 中小に警戒感希薄
企業存続の危機認識を
新型インフルエンザ大流行の警戒感が国際的に高まる中で、中小企業は対策への意識が依然として希薄だ。燃料や資材の高騰が直撃し、経営を切り盛りしていくことで手いっぱいの企業が少なくない。だが、新型インフルエンザが広がった際に予測される被害はきわめて深刻だ。中小企業は大企業に比べ、資金や人員など経営資源が乏しく、大流行ともなれば、企業存続そのものが危うい状況になりかねない。中小企業経営者の悩みは尽きない。(碩靖俊)
◆大きな経済損失
「(新型インフルエンザは)近い将来、必ず発生する」―。東北大学大学院医学研究科の押谷仁教授は警鐘を鳴らす。これまでの新型インフルエンザ発生の歴史を見ても「20、30年に一回発生し、大流行につながっている」と指摘し、今後、いつ発生しても不思議ではないと説明する。
大流行により、国内でも3000万―4000万人が発症するとの予測がある。間接被害としても、医療機関や社会機能のまひをはじめ、大きな経済損失が危倶されている。厚生労働省が7月末に公表したガイドラインは、流行時、従業員の最大40%が数週間にわたり欠勤すると想定した。
◆ゆとりなく
こうした事態に対し、産業界も手をこまねいているわけではない。7月29日に東京商工会議所が開いた「新型インフルエンザ対策セミナー」には、定員の3倍となる600人の申し込みが殺到した。東商は急きょ座席を拡充して対応したが、150人がセミナーに参加できないという盛況ぶりだった。
ところが、参加者のうち「多ければ7割程度が大手企業もしくは、大手企業のグループ会社」(東商地域振興部)で、中小企業関係者は一部にとどまった。実際、中小企業は燃料や資材の高騰が直撃する中で「まだ起こっていない事態に備えるほどゆとりがない」(都内機械部品製造業経営者)と、新型インフルエンザ対策への意識は決して高くない。
◆早急に着手を
根底には「大変なことになるらしいということは分かっていても、その詳細は知らない中小経営者が多い」(押谷教授)という事情が潜む。そのため、東商は09年3月末に事前対策を進めるマニュアルを整備するほか、危機感醸成に向けて、各支部を中心に新型インフルエンザ対策に関するセミナーを順次開く。
NPO法人事業継続推進機構の細坪信二理事兼事務局長は「中小は人材でビジネスを保っている」と事前対策の重要性を説く。中小企業は一人ひとりが即戦力だけに、早急な対策着手が求められる。危機感の醸成に向けては商工会議所のみならず、商工会や中央会などの中小企業団体が一体となった呼びかけも必要になりそうだ。
日刊工業新聞 平成20年8月5日
新型インフル、企業も対策を
リスクコンサル会社が懸念
中小企業の経営者に新型インフルエンザの脅威が浸透していない―。新型インフル対策のコンサルティングを手がけるリスクコンサルティング会社は懸念を示す。「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」の改正案が厚生労働省に承認され、企業は具体的な対策が立てやすくなったものの、経営者が新型インフルの脅威を受け止めないことには効果的な対策につながらない。コンサル各社は経営者の新型インフルに対する認識不足を案じている。(池田勝敏)
わずか1割
政府など各機関が新型インフルの人的・経済的被害予測は多々公表されているがその脅威を自社の企業活動と関連づけ対策を実施している企業は今のところ多くはない。
インターリスク総研(東京都千代田区)が5―6月に国内全上場企業に対して行った新型インフル対策の実態調査(回答率11.3%)によると対策を実施している企業が約1割と低水準であることがわかった。
さらに詳細を見ると連結従業員数3000人以上の実施している企業は21.8%であった。企業規模が小さい方が対策を実施していない傾向が見られる。中小企業ともなると新型インフルへの積極的な備えは期待できない。実際「大企業に取り組みが見られ始めたが、中小企業での取り組みはほとんど見られない」(損保ジャパン・リスクマネジメントの山本雅司取締役)との声もある。
中小企業に打撃
こうした事態は新型インフルの知識が十分に浸透していないことが背景にある。「新型インフルヘの備えに関する基本知識が有効な“ワクチン”となる。経営者に正しい知識がないと企業として対策はたてにくい」(インターリスク総研の本田茂樹主席コンサルタント)と指摘する。
さまざまなノウハウがトップに集中することが多い中小企業では、トップが新型インフルに冒された際の経営への衝撃は大きい。「財務体力面からも倒産に追い込まれる可能性は高い。企業存続の面では大企業よりむしろ対策の必要性は高い」(山本氏)との声もある。
できることから
知識を得ても対策を講じるには制約がつきまとう。下請け企業は納入先の対策方針や被害状況によって自社の対応が変わることなどサプライチェーン上の問題があげられる。「対策グッズなどの備蓄スペースの確保や対策資金の工面も壁になっている」(東京海上日動リスクコンサルティングの八田恒治主任研究員)との指摘もある。
企業の新型インフル対策は課題が山積しているが、まずは脅威を認識し「できることから手を付けていくことが重要」(山本氏)だ。未知の脅威にどのように立ち向かうか。経営者の手腕が問われる。
日刊工業新聞 平成20年8月8日
新型インフル対策中小向け指針
業容で企業3分類
対策作り促す
ライフライン・食料→継続
大規模商業施設→停止
その他→最低人員で継続
東京商工会議所は来年3月末までに、中小企業向けの新型インフルエンザ対策の指針を策定する。企業を3タイプに分け、発生時などの対応マニュアルを示し、会員企業の事業継続計画づくりを支援する。国内で大流行すると従業員の欠勤や物流の停滞で、企業活動に大きな影響が出ると予想される。遅れ気味の中小企業の計画策定を促し、被害を最小限に抑える。
東商が設置した新型インフルエンザ専門委員会(委員長、押谷仁・東北大学教授)では秋に指針の中間報告をまとめる。来年3月までに正式に決定する。
指針には、新型インフルエンザについての基礎知識や治療薬の効用、備蓄方法など事前の準備から、発生した場合の対応例などを盛り込む方針。例えば、従業員に感染者が出た場合の搬送や消毒の方法、被害状況に応じた従業員の配置や、事業を継続するか否かの判断基準、情報収集の仕方など対応策を示す方向で検討する。
事業継続の社会的な必要性および感染拡大を最小限にとどめる双方の観点から企業を3種類に分けて対応を示す。
電気・水道などライフラインに関連する事業者や、食料を供給する流通業は社会機能の維持に欠かせない業種と位置づけ事業継続を優先する対策を促す。一方、不特定多数の人が集まる大規模商業施設などは感染拡大防止のため早期の事業停止を要請する。その他の一般企業は、優先する業務を絞り、最低人員での事業継続を促す。
新型インフルエンザは、鳥インフルエンザウイルスが、人から人に感染するタイプに変異すると発生する。政府は国内で3200万人が感染し、最悪64万人が死亡すると推計。東京都の被害想定では都内の死者数は1万4000人に達する。
新型インフルエンザが大流行すると、社会活動の停滞を招く恐れがある。特に従業員の少ない中小企業では、従業員のほとんどが感染して事業継続が不可能になる懸念がある。資金繰りの悪化に伴う給与支払いの遅延など雇用への悪影響も考えられる。
厚生労働者が公表した民間企業の事業継続の指針では、海外で発生してから国内で大流行するまでの四段階を想定。各段階における企業への影響や従業員の感染防止策の注意点を示した。東商はより具体的で、中小企業の実態に即した対策を示す考えだ。
新型インフルエンザの指針に盛り込む内容
①基礎知識や治療薬の効用・備蓄方法
②従業員や家族に患者が出た場合の対応
③事業継続の判断基準
④情報入手の方法
読売新聞 平成20年8月13日
新型インフル流行したら……企業が対策
泊まり込み 通勤回数減
家族が38度超 出社自粛
新型インフルエンザ*の発生に備え、企業が対策マニュアルを作り始めた。流行時に、社員を感染から守るため、マスクなど衛生用具を備蓄したり、勤務態勢を見直したり。企業と家庭の連携が欠かせないことから、家族の啓発に力を入れる企業もある。
流通大手のイオン(千葉市)は、2年前から新型インフルエンザ対策を開始した。担当者の長尾博昭さんは「食料品や日用品は市民生活に欠かせない。従業員の安全を守りながら可能な限り販売したい」と話す。
同社のスーパー「ジャスコ」の各店舗では、患者が地元で発生すると、子ども用品コーナーなどから売り場を順次閉鎖。店内での感染を防ぐため、最終的には屋外にワゴン台を並べる店頭販売に切り替える手順になっている。
従業員はマスクやゴーグルを着用して接客する。こうした従業員用の対策セット(マスク1万5000枚、ゴーグル500個、専用せっけん500個、うがい薬500本)を計12セット用意。流行が始まった地域にすぐ配送できる態勢をとる。また、従業員全員に、感染防止の基礎知識を記したパンフレットを配布した。
東京ガス(東京)は、国内で流行が始まったら、工場やガス管の維持・管理関係の社員約2600人について、工場などに2週間ずつ泊まり込み、交代で作業してもらう方針。通勤する回数を減らし、感染リスクを低くする狙いだ。「通勤時に自家用車を使うよう呼びかける」と担当者。これに対し、接客や販売などその他の約6000人の社員は自宅待機にする方針で、この秋までに具体的にマニュアルで定める。
NEC(東京)は、社員が自宅にいても、カメラ付きパソコンの前に座れば、インターネットを通じて会議に参加できるシステムを作っており、「社員同士が接触する機会を減らせる」という。社員の感染を防ぐには、家族ぐるみで取り組むことが欠かせないとして、手洗いの仕方などをまとめた家庭用マニュアルを9月に配布。さらに将来の流行時には、毎朝社員が家族全員で体温を測り、家族の誰かが38度を超えていたら出社を自粛する取り決めにしたいという。
三井住友海上グループのインターリスク総研(東京)は今年6月、国内の上場企業の新型インフルエンザ対策を調査した。回答のあった448社のうち、対策を立てているところは約10%だった。
企業の取り組みを進めようと、厚生労働省も先月末に事業者・職場向けの新しい「対策ガイドライン」案を公表した。ガイドライン案では、電気・ガスや、食料品の製造販売など生活に欠かせない分野の企業などには、新型インフルエンザの発生時にも事業を続けるよう要請。一方で、感染拡大を防ぐため、重要業務以外は可能な限り縮小することを求めている。
インターリスク総研の主席コンサルタント本田茂樹さんは「企業も少しずつ対策を取り始めているが、社員やその家族も新型インフルエンザについて正しく理解しておくことが必要だ」と話している。
〈新型インフルエンザ発生時の企業の感染予防策の例〉
(厚労省のガイドライン案から作成)
▼満員電車などでの感染を避けるため、時差出勤を採用し、自家用車での通勤を認める
▼在宅勤務を進める
▼出張や会議を中止する
▼従業員の出勤時、体温測定や問診をする
▼社員食堂を利用するときに時差をつけたり一時閉鎖したりする
▼マスク着用、手洗いの励行
▼毎日職場の消毒・清掃を行う。特にドアノブやトイレ
▼「病気を押して出勤すること」を評価するような職場文化を普段からなくし、「症状がある時は自宅療養」という基本ルールを浸透させる
*新型インフルエンザ
鳥類などのインフルエンザウイルスが変異し、人から人へ感染しやすくなったもの。いつ発生してもおかしくない状況と言われる。人には免疫がないため、世界的な流行になるとみられる。厚労省は、海外で発生してから日本国内に入るまで2〜4週間程度と想定。社員自身の感染や家族の看病のため、職場を休む人が最大40%になる可能性があるとしている。
日刊工業新聞 平成20年9月24日
リスク管理
職場の新型インフルエンザ対策①
感染症流行、経営上の危機
総合的な対処が不可欠
濱田 篤郎
労働者健康福祉機構 海外勤務健康管理センター所長代理
【略歴】81年(昭56)東京慈恵会医科大学卒業後、米国に留学し感染症、トラベルメディスンを修得。東京慈恵会医大講師を経て、04年から現職。今年9月に新型インフルエンザをテーマにした「世界一病気に狙われている日本人」(講談社+α新書)を出版。
社会全体が新型インフルエンザで騒がしくなっている。今年の4月に政府は感染症法を改正し、新型インフルエンザをエボラ出血熱、ペストなどの危険性が極めて高い一類感染症並みに対応ができる重要疾患に規定した。また今年になり自民党のプロジェクトチームや経団連などが、政府の新型インフルエンザ対策について提言を発表している。さらに7月末には、厚生労働省が「職場や事業所での対策ガイドライン案」を提示し、現在、パブリックコメントを募集しているところである。このように新型インフルエンザの脅威は日増しに高まっており、職場でもその対策を準備する時期にきているようだ。そこでこの連載では、企業側がとるべき対策について5回連続で解説していきたい。まずは新型インフルエンザとはどういう病気なのかを説明しよう。
総論
■死亡者増加
インフルエンザは毎年冬に流行するウイルス性の病気である。通常は発熱や風邪の症状がみられ1週間程で回復するが、数十年ごとに大流行を起こし、多くの死亡者を出すことがある。これは、新しいインフルエンザのウイルス(新型ウイルス)が出現することが原因になっている。新型ウイルスに対して我々は全く抵抗力がないため、多くの患者が発生するだけでなく、死亡者の数も増加するのである。これが新型インフルエンザという病気だ。
こうした新型インフルエンザの流行は20世紀に3回発生している(表1)。この中でも、1918年のスペイン風邪の流行の際には全世界で5億人以上が発病し、4000万人が死亡するという大惨事になった。当時は第一次大戦の渦中だったが、新型の死亡者は大戦の戦死者850万人よりも遥(はる)かに多かったのである。
この新型流行の危機が最近とくに高まっているようだが、その理由の一つは最後の香港風邪の流行から40年が経過し、そろそろ次の流行が起きても不思議でない時期にきているからである。さらにそれを暗示させる不吉な出来事が近頃(ごろ)発生している。それは鳥インフルエンザの流行である。
■爆発的に
03年よりアジアを中心に、ニワトリなどの間で鳥インフルエンザの流行が発生している。この病気には人間も偶発的に感染することがあり、08年9月までに世界15カ国で387人の患者が確認され、うち245人が死亡した。
この鳥インフルエンザ自体も大変に恐ろしい病気であるが、さらに怖いのは、鳥インフルエンザのウイルスが新型ウイルスに変化する可能性があるからだ。20世紀に流行した新型ウイルスは、いずれも鳥のウイルスに起因することが明らかになっている。現時点で鳥のウイルスは鳥から人に時々かかる状況であるが、これが人から人に感染するようになると、その時点で新型ウイルスの発生となり、人間の世界で爆発的な流行を起こすことになる。
世界保健機構(WHO)は新型インフルエンザの流行段階を六つに分けているが(表2)、現在はフェーズ3。これがフェーズ4(人から人にウイルスが感染する)になるとWHOは新型の発生を宣言する。まさに今は流行の一歩手前で、新型発生のカウントダウンがすでに始まっている状況なのである。
もし新型インフルエンザの流行が発生したら、どれだけの被害が生じるのだろうか。日本政府が05年冬に発表した行動計画によれば、国民の25%が発病し、最大で64万人が死亡するという予測をしている。この死亡者は通常のインフルエンザの約100倍の数にあたる。これだけの被害が生じるとすれば、それは一つの感染症の流行ではなく、特大の自然災害と言ってもいいだろう。そして、その時期が目前に迫っている。だからこそ、政府や自治体も急ピッチで新型対策を進めているわけだ。
さらに、人的被害だけでなく経済的にも甚大な被害が予想されている。これは、従業員の欠勤や原料の供給停止などにより、事業が継続できなくなるためである。また消費の落ち込みもあるだろう。その結果、たとえば世界銀行では、新型インフルエンザの流行により全世界で1兆5000億ドルの被害額が生じると予測している。また日本だけでも20〜30兆円の損失が出るとの推計もある。
ここで企業の立場として新型インフルエンザの流行を眺めてみると、それは従業員の健康管理上の問題であるとともに、経営上の危機としても対処すべき問題であることが明らかになってくる。従来の健康管理スタッフだけでなく、経営責任者、危機管理担当者など社内の幅広い人材を集めて、総合的な対策を立てることが必要になるのである。それには、どのような方法があるのか。これを次回以降に説明していこう。
表1.20世紀に起こった新型インフルエンザの世界的流行
| |
流行年 |
発生地域 |
死亡者数 |
| スペイン風邪 |
1918年 |
米国? |
4000万人 |
| アジア風邪 |
1957年 |
中国南部 |
200万人 |
| 香港風邪 |
1968年 |
中国南部 |
100万人 |
|
表2.新型インフルエンザの流行段階※(WHO・05年)
| |
フェーズ |
状 態 |
| 流行間期 |
1/2 |
ヒト感染の可能性のあるウイルスが鳥に出現 |
| 警戒期 |
3 |
鳥よりヒトにウイルスが感染 |
| 4/5 |
限定的にヒト・ヒト間の感染(新型発生) |
| パンデミック期 |
6 |
広範囲にヒト・ヒト間の感染 |
|
※ 現在はフェーズ3である
日刊工業新聞 平成20年10月1日
リスク管理
職場の新型インフルエンザ対策②
企業に求められる対策とは
ウイルス感染経路遮断
マニュアル作成、予防徹底
濱田 篤郎
労働者健康福祉機構
海外勤務健康管理センター所長代理
職場の健康問題といえば、従来は産業医や衛生管理者などの健康管理スタッフが対処してきた。しかし、新型インフルエンザ対策となると全社を挙げた対応が必要になってくる。大手企業の中には、こうした準備をすでに始めている社もあるが、中小企業ではなかなか手が回らないのが現状のようだ。各企業がどこまで新型への対策を行わなければならないのか。今回は具体的な対策の内容について紹介しよう。
■多数が未整備
05年12月、日本政府は新型インフルエンザ対策の基本方針である行動計画を発表した。この中で政府は、新型の被害を最小限に抑える方法として、ワクチン接種が最も効果的であるという方針を示している。
この行動計画にもとづく具体的な対策が、07年3月に厚生労働省から発表された「新型インフルエンザ対策ガイドライン」に描かれている。このガイドラインの中では、職場での対策が社会全体の被害を軽減させるために必要であると強調されているが、どのような対策をとるかが明示されていない。このため、ガイドラインを読んだだけでは、企業側が対策を準備するのはなかなか困難だった。
たとえば、08年5月に三井住友海上グループのインターリスク総研が上場企業約4000社を対象に行った調査では、回答のあった企業のうち半数以上が、新型の対応は全く行っていないと答えている。その理由で一番多かったのが、「事態があまりにも重大すぎて企業の対応能力を超える」というものだった。こうした状況を改善するため、今年の7月に厚生労働省は「職場や事業所での対策ガイドライン案」を提示したところだ。
■二つの目的
このガイドラインによれば、職場での新型インフルエンザ対策は二つの大きな目的を持っている。一つは従業員を新型の感染から守るという目的で、これは企業側にとって従業員への安全配慮義務から求められる対応である。そして、もう一つは事業継続という目的。これは経営上の要請だけでなく、ライフライン関係の職種などでは社会的な使命からとられる対応である。通常の職場の健康問題であれば、従業員の健康を守るという目的だけで済むが、新型インフルエンザの対策にあたっては事業継続という観点からの対策も必要になるわけだ。
では、なぜ事業継続まで考えなければならないのか。その最大の理由は新型の流行にともない多くの欠勤者が発生するからである。厚生労働省では流行のピークに従業員の40%が欠勤し、その状態が2カ月間は続くと推計している。
これは、従業員が新型インフルエンザにかかって休むだけでなく、家族が発病した際の看病による欠勤も含まれる。また流行時には保育所の閉鎖も予想されるため、子どもの世話をするため欠勤する従業員もでるだろう。
こうした感染予防と事業継続という二つの対策を企業側では進めていく必要があるが、事業継続については第5回の連載で詳しく述べるので、ここでは感染予防について解説しておこう。
まず感染予防のためには、新型インフルエンザの感染経路を知っておくことが必要である、一つは、患者から排泄(はいせつ)されたウイルスを直接吸い込む飛沫(ひまつ)感染。もう一つは、机やドアノブに付着したウイルスを取り込む接触感染である。この二つの経路を遮断することが感染予防の方法になる。
次に自分達(たち)の職場の感染リスクを評価していただきたい。これは大きく三つに分けられる(表1)。高リスクは医療関係や海外の職場。中等リスクは人と接する機会の多い職場で、マーケットや学校などが該当する。こうしたリスクに応じて感染予防のレベルを決めるわけだ。
■発熱なら欠勤
そして具体的には表2に示す対策を行う。個人防御としては手洗いの励行やマスクを着用するなどの方法をとる。また自分がかかった時に、咳(せき)やクシャミが周囲に飛び散らないようにするマナー教育(咳エチケット)も大切である。
勤務形態の面でも工夫が必要になる。飛沫感染の予防には人ごみに出ないことが最も確実な方法であり、それには在宅勤務が理想である。そこまで出来なくても、時差通勤を奨励して満員電車に乗ることを避けたり、会議や出張を取りやめにするなどの方法を検討していただきたい。
さらに職場に新型インフルエンザを侵入させない対策も必要になってくる。従業員には欠勤規定を設け、たとえば毎朝検温をして熱があれば休むように指導する。今までの日本の職場では少々の熱でも出勤することが美徳とされてきたが、この考え方を修正する必要があるだろう。
現時点ではこうした感染予防のためのマニュアルを各職場で作成し、それを従業員に周知させること。そして、マスクや消毒液など必要な備品を揃(そろ)えておくこと。これが職場での対策の第一歩である。 (只今毎週水曜日連載中)
表1.職場における新型インフルエンザの危険度※
| |
職場の状態 |
職場の例 |
| 高リスク |
患者と接する機会の多い職場 |
医療関係、海外の職場 |
| 中等リスク |
人と接する機会の少ない職場 |
マーケット、学校 |
| 低リスク |
人と接する機会の少ない職場 |
オフィス |
|
※米国の労働省が発表するガイドラインを参考に一部改訂した
表2.職場での新型インフルエンザの感染予防策※
| 予防策の種類 |
具体的な予防策 |
全職場で実施すべき予防策 |
| 個人防御 |
手洗い、咳エチケット |
マーケット、学校 |
| マスクの着用 |
○ |
| 勤務形態 |
出張・会議の中止、時差通勤 |
- |
|
感染リスクの高い業務中止
在宅勤務
|
○ |
| 侵入防止 |
欠勤規定の作成、外来者の制限 |
- |
| 入場時の体温測定 |
○ |
| 環境対策 |
定期清掃 |
- |
|
職場や食堂の配置換え
窓口業務に防御ガラス設置
|
オフィス |
|
※米国の労働省が発表するガイドラインを参考に一部改訂した

日刊工業新聞(平成20年9月9日)
九大発VB
ネット情報分析サービス
テキストマイニング利用
九州大学発ベンチャー企業のLafla(ラフラ、福岡市西区、宥免達憲社長、092・400・4562)はインターネットなどを利用した情報収集・処理・分析提供サービスに乗り出した。九大の廣川左千男教授が開発した大量のテキストから有用な情報を抽出するテキストマイニング技術をもとに提供するサービスで、2011年度をめどに年商1億円を目指す。
同社は科学技術振興機構(JST)の産学連携事業の一環として、研究した成果をベースにこのほど設立。資本金400万円。
テキストマイニング技術は定型化されていない文書の集まりを自然言語解析の手法を使い、単語やフレーズに分割、それらの出現頻度や相関関係を分析して有用な情報を抽出。インターネット上のウェブページや企業内の文書など増加する情報について、その技術を使って分析する。
大量の文書情報を文書中の言葉のつながりによって表現し、閲覧者に対して情報の全体像をみせ、全体像の中から埋もれていた情報の発掘・露出効果を提供する。
同社は情報を複数の属性によって分類し、クリックだけで効果的に絞り込む技術の開発も進めている。文字入力の難しい携帯電話での情報検索用として、09年2月をめどに提供する予定。
http://www.lafla.co.jp/aboutus.html
■本局ではこのニュースに少し関心をもっております。こんにちではGoogleの検索機能も進化しています。
またホームページ上のコンテンツも多様化しています。ワンテーマで探るとすれば、これからデータの掘り起こしや狙いを新しいコンテンツとして生まれてくる可能性もあります。コンポジショニストのみなさんとライターのみなさんで、こうしたテキスト・マイニング(text mining)のニーズもあろうかと思います。マイニングとは採掘・採鉱というような意味です。OCRが使えるか使えないかは別として、『ディクテーティング研究』第5号(1995年4月)の○○総合研究所のキーワードのつくり方や、Google検索技術などを参考に使えば、テキストデータを出版企画として構成案のテキスト第一稿として整理することができます。どのような工夫が必要か、新しいビジネスとして可能です。こうした時代がやってくると考えております。
OCRのデジタルテキスト再生原稿からテキスト・マイニングによる再構成のニーズも出てくるのではないかと考えられます。
ぼくたちの工夫と気づきでデータの整理技術をどのように開発するか、『ディクテーティング研究』第5号のキーワード抽出の仕方などを参考にと考えています。
著者自身による直し・修正、加筆などおこない、新しいコンテンツとして新規企画に対応できるかもしれない。出版社編集者の企画構成案に基づき、第一稿の整理に挑戦してみたいとも考えています。本局ではテキスト・マイニングによる編集の知識と技術を学び、編集者の眼を重視したコンテンツの制作を、と考えています。九州大学とは異なった視点からのテキスト・マイニングに焦点を合わせます。
この九州大学のベンチャービジネスはBI(ビジネスインテリジェンス)を目的としているように思えます。本局では最新のBIの成果を吸収したPI(出版インテリジェンス)を目指しています。
九州大学の学内ベンチャーが来年から事業化するようです。
(平成20年9月9日「営業情報」に投稿、加筆・修正しました)

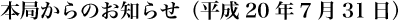
メディアミックス&ソフトノミックス/は現在、カセットテープ(標準、2倍速、3倍速)、MD、マイクロカセットテープなどを音声ファイルに転換してディクテしています。納期などでできないものもありますが、80%以上音声ファイルへ転換しています。
第20期が7月で終わり、新しい第21期へ8月からスタートします。
本局では現在、在庫として持っているソニー製BM-76(修理済み10台、製造停止、購入時7万5000円相当)一式(フットコントローラーFS-85含む)とBI-85Tのモノラル(機械式、フットコントローラー含む)一式5台、新品(8万円相当で購入)ディクテマシンを放出することにしました。
現在本局では事務所の第二期工事に入っており、在庫の場所がなくなって整理したいことと、トランスクライバーのみなさんも音声ファイルへ転換してディクテに入っている現状を考え、今後も使用しないだろうとの判断に基づいています。
まだ根強い人気があります。
それで社会貢献活動などしている個人、団体に無料でお譲りしようと考えております。
NHK総合テレビで拝見したのですが、老人の昔話を取材して原稿を書き起こしているボランティアの方などを対象にと考えております。
またスタッフでボランティア活動している方もおられますが、事務所にディクテマシンが必要な方はお申し出ください。送料は本局で負担いたします。
本局の第一期工事は2002年(平成14年)行われました。
東京・青山にあるドイツ系外資ip21(株)の家具メーカー システムパーツのオフィス取り付け家具の工事をしました。
6年後の2008年(平成20年)夏、第二期工事に着手、SOHOにとって宿命の「家庭の雰囲気」や「におい」を一掃、設立20年目に本局オフィスの設計を実現、メディアミックス&ソフトノミックス/は新しい21年目を8月迎えます。
工事を安くするためオフィス家具のLION 両開き書棚ケース5台を購入し、電機製品や音声ケーブル類、マニュアルである書籍、文書類を収納、真っ白に統一しました。
中央テーブルの正面にAQUOS47インチ液晶大画面(ディスプレイ、モニター)を設置、AQUOSコンピュータ(録画、再生、CD−R)と接続、インターネットと接続し、ホームページ、イントラネットを200倍に拡大して視ることができる。AQUOSコンピュータでディクテーション(談話筆記)システムが実現。拡大文字で表記でき書き綴ることができる。
今後どのようにインターネット環境でA4、B4サイズをOCRなどで画像を取り込みプレゼンテーションのディスプレイとして開発が課題である。また編集者からのFAX入稿の取材メモ、その他をOCRでスキャニングしてトランスクライバーへ電子メールで送り、宅配便を使用することもなくなり、CO2削減に一歩前進する。インターネットを利用することによるCO2削減量効果が期待できる。
お客様をお迎えするにあたり小学校の教室の黒板(ディスプレイ)にもなる。
テキストや映像、画像、写真(スチール)、音楽などを使ったディスプレイが実現できるか?
生活と労働が融合し、たとえば誕生日などのパフォーマンスを想像されるとお客様の本局でのお出迎えなどで、ソフトウェアの多様性の実現など仕事を楽しく演出することができる。
やっと21世紀SOHO知識労働者のオフィスが実現できるようになった。
お客様への基本的な業務案内、プレゼンテーション、お客様を神様としてお迎えする個別的な対応と商談の目的に合わせて企画提案を効果的にできるだろう。
そして、新入スタッフとの面接、面接の期待と喜び、仕事の楽しさ、キャリアデザインへの道、採用時にお渡しする書籍や文書の数々の案内――それとの相乗効果を実現する47インチのディスプレイでの演出、パフォーマンスの輝き。仕事が導く自己実現。テキストづくりは知の創出の身近な実感が自分を生きることにつながるだろう。
マルチメディアの力をつくり出していきたい。47インチディスプレイを使いこなす期待は山ほどある。
今秋には、ラジオ番組の制作と編集の仕事が始まる。モニターとしても活用していく。
(8月上旬にはトランスクライバーからの原稿を準備しております)
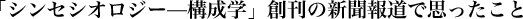
日刊工業新聞 平成20年6月24日
個の「知」から全の「知」へ─
そのシナリオの共有と蓄積について。
Synthesiology Symposium「シンセシオロジー─構成学」創刊記念シンポジウム
5月中旬、都内で「シンセシオロジー(構成学)」をテーマとするシンポジウム(主催 産業技術総合研究所、共催 日刊工業新聞社、時事通信社)が開かれた。シンセシオロジーは、シンセシス(構成)とロジー(学)をつなげた造語で、産総研が創刊した学術誌のタイトルでもあり、科学分野における統合・構成のプロセスを掘り下げようというものだ。シンポジウムでは、構成学とは何であって、なぜ今、構成学なのかを講演やパネルディスカッションを通して浮き彫りにした。
科学技術の
全分野を対象に
赤松 幹之氏
(産業技術総合研究所 人間福祉医工学研究部門長
シンセシオロジー編集委員会 編集幹事)
科学や技術に新しい領域ができ始めると、分派や研究会が生まれ学会誌を出す。それが、従来の科学ジャーナルであり、その結果として、それがどんどん細分化されていく。そうすると特定の分野の知識はためられるが全体をみることはできない。そこを排除したいということで、新ジャーナルはすべての分野を対象にする。本ジャーナルの目指す所は科学的知識の統合とか構成の方法論を確立することで、分野の特有性があるかどうかまだ分からない。そういう点を踏まえ、共通的方法論を見いだすという観点で科学技術の全分野を対象とする。
1960年代、佐藤の学生時代、赤松幹之氏とまったく同じ問題意識の中にあった。
行為や活動、運動は思考の方法に基づいて行われる。みんなの意見を集約しようと思えば「方法論」の立場になる。
人間が個として誕生し、存在していることが「矛盾」といい、ここから「矛盾」が生まれる。悲しい人間の存在なのである。
これまである社会的分野においての「矛盾」は社会的集積の「矛盾」として捉えることが多かった。「矛盾」の起源は個としての存在の誕生にある。
赤松幹之氏の孤立を怖れる。
再びふれることはないと思うが、60年安保の共産主義者同盟は内部論争で三派に分裂した。佐藤の問題意識も「なぜ分裂せざるをえなかったか?」、佐藤が追い求めたのはこの原因の原因に気づくことであった。佐藤がこだわってこのホームページで言及したのも、この存在の悲しい「矛盾」なのであり、ここから「矛盾」が生まれる。
すべての政治的な活動であれ、社会的な活動であれ、研究活動であれ、この「矛盾」の塊が一派を形成し、路線をめぐる論争など、人間社会はここから逃れられない。
マルクスもトロツキーもレーニンも存在論者ではなかった。
トロツキーは『文学と革命』の中で、あえていえば「人格」の変革を求めた。
レーニンは彼の著書の中で「純粋な民主主義」について論及した。「純粋な民主主義」と訳されたが、佐藤は「理論的民主主義」と解釈している。民主政治は、現実的な民主主義しか存在できない。いわゆる政治学者の「政治評論」を拝見していると、この「純粋な民主主義」、あえて佐藤は民主主義のあるべき姿と理解したい。政治学者がドロ沼の情感の政治抗争を「分析」する人間文学は現実的政治の政治的未熟を示している。悲しい政治的現実であった。
かつて母は「平和を求めているのに、なぜ平和な行動がとれないのか」と迫り、佐藤は答えなかった。
こうした政治の季節は終わって集団の亀裂は人間の悲しい存在に基づくものであることを知った。佐藤の人間経営経済学はここに土台をおく。「やってよいこと、悪いこと」がある。「人様に(こころに)迷惑をかけるな」と教えない。親も教師も「気をつけてね」と教える。政治家も経済、社会もそのように教える。
高度成長期時代からバブル経済時代は「お互い様」の時代で、「悪いこと」はお互い様だ。土足で人の「こころ」を踏みつけた。「人間の存在」は悪だ、と教えた。東大安田闘争は良心の哲学が求められた。だが、70年安保はこうした社会へ迎合していった。
社会の軸が変わってしまった。
赤松幹之氏が「方法論」から出発しようとするのは正しい。
佐藤は原則論者ではない。原則があるから非原則もある。非原則を受け入れて原則の内容は豊かになる。揚子江の「こちら岸」から、「あちら岸」まで距離がある。曖昧さの残滓のない非原則の良心を(測定)求める。
佐藤が小学生の5、6年生の頃に母から聞いた話だが、母が郵便局の電話交換をしていた昭和10年代、電話交換手はトランスクライバーと同じように声でその人を特定できる技術を持つ。
トランスクライバーはよく知られた著名なディクテーター(談話者)ならスタンバイノート(トランスクライバーが傍聴して発言順をメモする)、ノートがなくても鼎談などの発話の区別ができるように電話交換手も職業耳を持つ。
ある日、終業の5時、電話交換(共電双紐)が終了した直後、電話が入った。声から商品相場の男性だとわかった。いまのあなたならマニュアルに従って受け付けないか? 母は声から緊急さを感じて相手につないだ。マニュアル社会のいまならたぶん違法といわれるのだろう。母は電話をつないだことを子ども(佐藤)に話してくれた。
母の娘時代の話である。
佐藤のこころの中には原則と非原則の論理が歴然とある。これはひとつの事例かもしれないが、いまの佐藤なら母の行為を受け入れる。
ディクテーションの手法にも原則がある。よくトランスクライバーに言っている。
「わたしのディクテーション」の型を持て、と。大相撲の型と同じだ。だから相撲を教育しなければならない。「型」とは形式である。知が道具化していない良心から学べ。
茶道と華道、大相撲は違う。ゲーム理論になるが、人間形成の多様性の集成(21世紀の技術思想)なのである。
理論的な方法論を形成することはできないだろう。いつも行為のあとから「方法論」を追認していく。理論とはこうしてできるものだ。こうした点で科学の「実験」は正しい。
P・ドラッカー先生と意見は同じだ。
佐藤の思索は20代前半中断し、20代後半に佐藤の弁証法と一般的なものの働き・運動に一定の考えが出てきた。すでに35年前、本質・形式・要素・目的はこの時代に生まれた。
欧米では歴史ある古くからの論理だ。
ドラッカー先生もご著書の中で4・5行にわたって同じ論理を展開している。訳者が気づいていないというか、佐藤は「気づいた」。こうしたこの論理の使い方は説得力を持つ。
みなさんもヒントにしてほしい。(ホームページ「在宅ワークとSOHO」の理論的立脚点に関する発表、参照)
アメリカのいたずらというか、陰謀に気をつけなければならない。日本人科学者の知の再構築(インテリジェンス)が必要だ。わが国の過去の歴史を知らない若い研究者を信じて、ものしりの手品(フロシキ)を拒否して存在論者を気をつけなければならない。
存在論者の自分本位の器用さに頼っても本物(インターナショナル)は生まれない。
アメリカのいたずらを後世の日本人はアジアの発展途上国にしてはならないだろう。
現象と現象、存在と存在のいま境界に生きている。境界に法制度の壁が立ちはだかる。
いわゆる「構造改革」のいまのレベルだ。
赤松幹之氏の言っていることが、けして理解できない人もいる。共創造の立場に立てない人が多い。けっきょく排除していくことになるかもしれない。
赤松氏は佐藤と同質の人だと思う。しかし、妥協しているわけではないが、この境界に生きる「境界」のことばを記憶してほしい。けして混ざることはできない。エネルギーは分裂する。
これまでのわが国の歴史における「知のあり方」は、「現実を否定し、現実的に生きる」ことであった。いま生きていて呼吸がらくになっている。孤独から解放されてこの社会へ同化しようというこころの働きを見る。風向きが変わってきた。
佐藤の弁証法の「反」は理論的なあるべき姿でもある。芸術家も多くの人が日本語を操る「民族文化」や「民族作家」の精神の境界を超越すべきで、視野を広げ、「民族」のこだわりからを越えて、グローバルな立場に立って、日本語の伝統文化に翻訳し日本人らしい良心と思想の変容へと止揚(アウフヘーベン)するこだわりの必要性を感じている。平成の文明開化の時である。
佐藤のテーマでもある、いわゆる転向の問題は自己の哲学的な良心と思想の思索としての変容をこうして描くことでなければならない、と感じている。
21世紀初頭に生きる青年・若者を信じたい。そして、妥協すべき豊かさの発見が必要だ。政治は国民に良心を示すときがきた。国民とともに「共同の課題」へ向けて! 欧米と異なった先進国らしい「品性」が求められる。
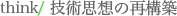
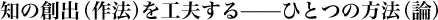
日刊工業新聞 平成20年6月5日
仙台市
連携フェローを増員
研究者の中小訪問を強化
【仙台】仙台市は大学研究者が地元中小製造業を訪問して技術支援などを行う「地域連携フェロー」活動のスタッフを拡充した。成功事例の輩出などで企業からの相談が急増していることに対応するもので、活動に従事する研究者「地域連携フェロー」を08年度から4人に倍増、活動をコーディネートする「ビジネス開発ディレクター」も1人から2人に増員した。
地元で活躍する研究者を仙台市が嘱託職員に採用し、企業の悩みを聞いて回るこの活動は、研究者側から企業側へと積極的に働きかける「ご用聞き型」の産学官連携として、全国的にも注目されている。07年度は東北大学大学院工学研究科の堀切川一男教授と、同研究科の青木秀之准教授の2人体制で、年間約50社の企業を支援。これまでに、22件もの製品や技術を支援活動によって実用化している。
08年度は、青木准教授がフェローを退任し、東北大多元物質科学研究所所長の齋藤文良教授、宮城大学食産業学部の大久保範教授、東北学院大学工学部の熊谷正朗准教授の3人が新たに就任。専門領域が広がったことから、仙台市は「年間100社の支援を目指したい」としている。
また同市は、支援活動に貢献した研究者を表彰する制度を創設。フェローを2年間務め、今回退任した青木准教授を「仙台市産学連携功労者」として表彰した。
佐藤がホームページで使った一般的に「ビジネス(生産)インテリジェンス(知識)」とは、ひと言でいえば、その企業や産業の「どんなふうにつくるのか」といえる知識と技術といえる。
産業界にはいろいろな事業をする企業があって、企業独自の「ものづくり技術」の知識がある。それをビジネス(生産)インテリジェンスといっている。
インテリジェンス intelligence には論理的な思考力という戦略的な意味も含まれる。この意味は「いかに行為するか」を理解できる能力が求められる。その能力とは「首尾よく、都合よく、そして有利に、巧妙に、よい所で」、組織の事業(サービス、エージェンシー)として行われる。
一方、ナレッジ knowledge には英語のことばの働きに本質、形式、要素(機能・働き)、目的があるが、この要素(機能・働き)に相当する。サービスオフィスやエージェンシーで働く知識労働者の現実的な仕事として位置づけられる。
事実・事柄などを知って(分かって)いる状態。知のいろいろな領域や蓄積された知識体系に明るい。学問や技術分野の実情や事実を知り、気づく力、理解する力があること。そうした業務に携わる技術者やその他の専門的知識労働者(ナレッジワーカー)をさす。
(情況の)直観力、イマジネーション、スキルなどの教育的経験をもつ。
これら日本語で表現される「知識」の意味は、英語ではインテリジェンスとナレッジの相違といえる。
最近では日本語の表現においてもこうした英語の知識が必要で、論理構造を求める意味で佐藤は英語で考えて日本語で考えるな、とスタッフに言っているが、次世代日本文化の創造という意味において試行錯誤に取り組んでいこうと思っているにすぎない。
日本語が悪いのではなく、日本人に論理性が欠けていて、近代「知」は、より細分化される方向にあるが、この細分化こそ論理性が求められる。日本語が近代知に適していないのではなく、一般に日本人の思考が知を細分化して「追い詰め」られることを嫌う。理性という名のムードで、自分に対することばの「厳しさ」(正確)を嫌う。共同幻想の中の自分が集団や社会と迎合する。アイデンティティーとは個性ではなく社会的概念になっている。わが国の小・中学生すら共同幻想を求め、アイデンティティー形成の契機が失われている。
ITのビジネスインテリジェンスとして特徴ある報道があった。
日刊工業新聞 平成20年6月10日
グーグル
営業パートナー100社に
企業向け検索ソリューション MSなどに対抗
グーグル(東京都渋谷区、村上憲郎社長、03・6415・5200)は、企業向け検索ソリューション事業で、営業パートナー企業を3年以内に現行比3倍強の100社に増やす。インターネットでの情報検索が浸透し、企業内の情報についても簡単に検索できる仕組みを構築したいというニーズが高まっている。同社では営業体制を強化してそれらを取り込み、先行するマイクロソフト(MS)などの牙城切り崩しを狙う。
グーグルの企業向け検索ソリューションは、イントラネットやウェブサーバなどに保存された企業内情報を簡単に検索できる。一般の検索サイト「Google.co.jp」で浸透している操作感を提供できることなどが強み。
日本では現在、企業向け検索ソリューションで約30社とパートナー契約を結んでおり、うち販売代理業などのパートナーが20社、残りがコンサルティングなどを含め、より広範な提案を行うソリューションパートナーとなっている。今後はシステム構築(SI)事業者などに呼びかけ、主にソリューションパートナーを増やす計画。
米グーグルは企業向け検索ソリューションを世界で約1万2000社に提供中。うち日本は1000社強だが、日本法人では「早期に世界の10%を占める規模にしたい」(大須賀利一エンタープライズセールスマネージャー)としている。
知の創出(作法)としては二段階だ。出版インテリジェンスから学ぶ。
文芸やノンフィクションのノート(取材メモ・草稿)から文芸インテリジェンス、ノンフィクションインテリジェンスを抽出し構成される。「語って説かず」の姿勢が基本だ。
日本経済が重化学工業化の道へ歩み始めた頃、わが国企業は外国の諸文献を翻訳することもあっただろう。知識や技術を資本提携して輸入し、製品として技術開発した。模倣の時代である。
こうした日本経済の模倣の時代は「バブル経済」の崩壊をもって終わった。
知識や技術は模倣から始まった。今のアジア諸国と同じである。
「失われた10数年」をへて、わが国の知識や技術の独創性が求められる時代となった。
巨大データの集積であるインターネットへの戦略的検索は知の創出の新しい意味をもつ。自らの気づきでインターネットのデータを情報として「知」を再構築して創出する。
「知」は本質・形式・要素・目的に整理する。「知」の論理をもって、理論的土台をしっかりつくる。
一方ではわが国政府のように欧米先進国の政策立案に向けての官僚の情報収集、世界企業の最新の技術開発情報、グローバルスタンダードは先進国としての欧米と足並みをそろえる政治経済政策を政府は進めている。「欧米に追いつけ、追い越せ」をへて今や世界仲良しクラブでもある。政治も欧米から学ぶという一面と、歩調を合わせるという一面と、世界仲良しクラブの一員として良い意味でいえば、グローバルスタンダード下において先進国としての政治や経済政策で足並みをそろえている。安全保障理事国入りを意識している。
地球規模での共同の課題に政治も経済も社会も直面している。しかし、わが国政府は内政の課題に後ろ向きである。国民が現実に生活する経済活動の安定という視座(施策)が欠落している。
こうした世界市場の中で生きていくにはわが国経済としての独創技術の開発が欠かせない。
ヒト・モノ・カネ・情報がひとつになって企業は世界市場と直面している。
この新聞記事は特に注目される。
企業は独創技術の開発にいかにチャレンジすべきか。
先日ホームページで東大型の集団討議型による知の創出と、早稲田型による知の創出について提案した。
『日刊工業新聞』は40歳代から毎朝購読して25年が過ぎた。特に最近注目されるのは各産業の「どんなふうにつくるのか」という生産現場の工夫や改善についての独自の生産インテリジェンスに基づく取材記事の工夫されたリポートだ。佐藤はここから小社の適用すべき生産の工夫をビジネスインテリジェンスとして学ぶことが多かった。
企業を動かす生産現場や現物、そして現実に適用できるようクセのない理論的で普遍的な人間の関わり合いを「ものづくり」の基本と考えた。標準化していくことができる。
起業当時は鉄鋼業界からビジネスインテリジェンス(ソフト化)として学ぶことが多かった。しかし、小社は出版社、放送局、通信業界をひとつにするような企業を目指した。
メディアミックス&ソフトノミックス/はこんな目標をもった。
今注目されるのはどのように知を創出するのか?
上記の記事は本格的な知の創出の構図なのである。
どの企業にも人生のように妻とよべるようなパートナーが大切で必要である。その道の学者もいいが、業界にあかるい人も加えて鼎談の形(形式)で知を創出していくことが提案できる。決意にカネを使え!
技術の組み合わせには独創技術はめったにでない。地方自治体のリーダーシップも必要だ。学者や研究者は書をすて町工場から学ぼう。最新の生産の現場をつくることに自信と喜びを感じ、学生に伝えることも必要だ。「経営社会学」の立場といえる。
こうした姿勢はイノベーションの風を学内にも企業にももたらす。
「独創性」は小手先の他社との技術の結合(組み合わせ)だけではない。かき回されるな。社長は知恵を出し、カネを出し、強いリーダーシップを発揮して自社技術の一点突破の全面展開をもたらすような真剣さがないとだめだ。産科医ではなく産婆にすぎない。研究者は自社技術展開の触媒となって新技術を開発することができるようでなければならない。リーダーシップは衆知を集め、技術インテリジェンスとして生み出すことだ。
ものの働きは本質・形式・要素(機能)・目的をもつ。日本人は内容(本質)については「一家言」ある。日本社会、民族の優れた資質だ。本質と形式を英語で考えて整理しよう。「物知り」(知が道具になっている)にふり回されるな! 技術観に哲学がないのだ。「たまげたもの」をつくるな! 形式は本質(内容)である。ドロドロした(単純な原因だが)根源性からは形式は生み出せない。知識(理性)ともいわない。偽物と本物を見分けろ。
医療現場(病院)で看護師が離職するのは最新の医療機器の操作性――使い勝手の悪さに原因があるのではないか? 生命にかかわる操作性の使い悪さは看護の精神と融合していないのではないか? ヒューマンエラーの原因を誘引しないか? 機器の中は見えない。せめて自分よがりの技術者が設計する操作方法に人間工学が不在なのではないか。
物象化の論理――「入れたものを出し、出しものを入れる。延長の思想」の物象化はスピノザの『エチカ』から学べ。モノラルな感覚がデジタルの基準なのである。でなければインターナショナルな製品とはいえない。男と女の論理、延長の思想――つまり古典的な論理が人間工学のどの民族にもわかりやすい人類の伝統的観念で前提だといえる。テープレコーダーやVTRのインターナショナル性はここにあった。技術哲学はこうした物象化から生まれる。市場を失っている原因はここにある。
(ウェブ「営業情報」平成20年6月7日投稿を修正・加筆しました)
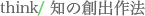
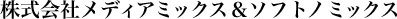
代表者
代表取締役 佐藤 正明
資本金 1,000万円
社員数 88名
平均年齢 40歳
| 年商 |
06年度 |
1億1,000万円 |
|
07年度 |
1億1,000万円 |
事業内容
① トランスクリプション(録音再生原稿)
② コンポジション(電子組版原稿)
③ 校正
主な取引先
PHP研究所 プレジデント社 リクルート 講談社 光文社 角川書店 ダイヤモンド社 幻冬舎 扶桑社 集英社 日本実業出版社 大和書房 青春出版社 三笠書房 現代書林 祥伝社 中央公論新社 東京糸井重里事務所 医療経済研究機構 東京財団 三菱総合研究所 PHP総合研究所 松下政経塾 読売新聞東京本社 産経新聞東京本社
パートナーシップ・ジョイントビジネス
『読売ADリポートojo(オッホ)』(読売新聞社 パルナス)、『読売新聞』(文化部)『PHP』『Voice』『THE21』(PHP研究所)、『正論』(産経新聞社)、『婦人公論』(中央公論新社)、『プレジデント』『プレジデントファミリー』(プレジデント社)、『月刊プレイボーイ』(集英社インターナショナル)、『SPA!』(扶桑社)、『野性時代』(角川書店)、『エルネオス』(エルネオス出版社)、『works』(リクルートワークス研究所)『週刊現代』(講談社)出版社及び関連95%以上
主な作品歴
『それいけ!! ココロジー』1,2,3,4(青春出版社)
交通
小田急線町田駅、JR横浜線町田駅
情報管理及び営業管理によるコンプライアンスの推進
本局では生産と納期の「見える化」をしている。ウェブ営業情報の「見える化」にも試行錯誤に取り組んできた。
音声ファイルでの入稿はインターネットで小社受付サイトを編集者にご案内し、パスワードをお知らせして入稿されている。翌日早朝「営業情報」に掲載し、仕事の入稿内容で、出版社編集者名、著者名、タイトル、タイトルに関する参考のホームページ(作家、著作者、タレント(芸能タレント)、企業など)、入稿のメディア媒体、納期、小社担当者名、本局のコメントなど、出版社編集者の取材参考情報など情報(取材メモ)を「見える化」、過去の生産や納期に対して、蓄積した顧客データから検索することができる。そして、本局のキャスティングは納期の設定もあり、営業情報を通して「見える化」してきた。それは労働生産性の見える化につながる。
生産、労働生産性、納期を業務プロセスの見える化を通して文書化し、スタッフ全員と共有している。
このように営業管理は「業務の見える化」を社内ウェブを通して行い、また検索することにより顧客の多様なニーズや、トラブルの背景を「見える化」することに役立っている。
知識労働の営業管理も含めて生産の全工程が「見える化」された。
情報の内容に携わっているのは担当トランスクライバーとコンポジショニスト、校正者だけで、情報内容については担当者のみに音声ファイルを開示して作業しており、校正を除いたすべての仕事の内容については本局だけが知る立場にあります。担当者以外は音声ファイル及び原稿を閲覧することはできない。情報が監理されている。本局では納品をもって音声ファイルは即完全削除しており、一部企業様への原稿の納品はウェブサイトの「企業様のお部屋」で暗号をかけて納品され、また秘話機能付ウェブ「新本局納品窓口」の暗室で約1カ月間原稿(トランスクリプション)を保管している。そのあと本局もスタッフも音声ファイルと原稿を完全削除している。
出版社様への納品はインターネットを通して電子納品されている。電子メールでの添付で納品されており、個人情報保護法の適用外ですので、電子メールの送信履歴で1年間保存されている。自社サイトの「仮納品窓口」はトランスクライバーのeラーニングとして格好の教材であり、学習に活用している。マルチテクノロジストとしての学習の場で、自社サイトの暗室での保存ではありません。自社サイトはIDと8桁のパスワードで内外からのアクセスを監視している。
社内サイトへつながる広義の生産工程のIT統制
「どんなふうにつくるのか?」という小社生産のインテリジェンスを標準化するためルール化し、手順・順序を定めている。仕事の原理・原則・基礎・基本・ルール・手順・順序は行動の土台となる共通語で、これ以外はすべてに対し理論的な自由がある。グローバルスタンダードはみんなの共通の「土俵」で、小社の経営理念とつながる。
個人情報保護のコンプライアンスを徹底するため、生産、生産性、納期の「見える化」に取り組んできた。これは内部統制へ連関する。
品質管理は個人の知識労働の能力に負うところが大きいが、品質を向上させるドゥハウを社内サイトのウェブオフィスで日常的に営業情報やeラーニングで教育してきた。業務プロセスの改善と工夫に活かした。
社内サイトはインフラが標準化され、全員と共有されてセキュリティ対策が適時見直され、電子文書(本局発表)として更新できるようPDCAのサイクルを回して調べもののインターネットへのアクセスなどリスクを管理している。
週・月刊誌、また書籍など、原稿のデットラインを抱えて突然の地震(安否の確認、女のネットワーク)や災害、親の介護(病院の付き添い)、学校――子どもの発熱、事故、PTA、会長、役員会、出席――、その他、納期時間を抱えてのリスクは自己の負担と、スタッフ同士が支え合い、助け合って解決している。女のネットワークは偉大だ。
電子デジタル音声ファイルは時空を超えて、「いつでも、どこでも」分割してダウンロードし、作業に入ることができる。カセットテープ(標準、2倍速、3倍速)、MD、DVD、マイクロカセットテープも入稿の8割を電子デジタル音声ファイルへ転換してコンピュータに統合している。モノラルのデジタルへの転換には録音時間が同等に必要であり子局スタッフの協力を得ている。CO2排出削減に一歩前進した。デジタルの力だ。Voice transcriptionは前進する。
こうして、スタッフの採用は点から面へと拡大する。日本全国北は札幌から南は南国市、アメリカ合衆国在住のスタッフへと拡大している。リスクにはスタッフ全員の協力が必要である。
少子高齢化社会の未来を予言している。
原稿のつくり方(技術力)は出版社や、入稿の内容によって異なるが、担当者の能力、専門性(適性)など参考に本局がキャスティングしている。
成果としてITによる統制は生産工程、品質管理、労働生産性から納品まで「見える化」することにより企業としての企業戦略(最高の経営方針)とのつながりを「見える化」することに役立っている。
個人情報保護法の遵守をIT化により監理されている。
(これは日本編集制作会社協会『AJEC会員ガイド2008−2009』へ向けて作成したものです。来る7月10日(木)〜13日(日)に開催される東京国際ブックフェアの「編集プロダクションフェア」向け冊子です)
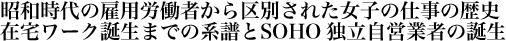
何度かweb「自由アジェンダの部屋」に投稿いたしましたが、焼き直して、もう一度振り返ります。企業化、産業化の可能な生産物の創出にこだわって概観したい。
戦前わが国の産業資本主義経済下の昭和、まだ戦争の足音が身近に聞こえようとしていた頃、在宅ワークの女の仕事として編み物と洋裁・和裁があった。今、アジアの後進国では産業の芽として女たちは家庭用ミシンという文明の利器を使って貧しさから脱出しようと所得を得ている。女の文化性をこめて生活を豊かにしようとしている。中国では一人っ子政策があって外資による草刈場となり、家庭用ミシンに関心がないようだ。
佐藤の母親は今年93歳になる。昭和に青春時代を過ごした母にとって和裁と洋裁は身に付いた女の武器であった。父の退職後は老人ホームでお人形作りとパッチワークに楽しみを持った。
佐藤が子供の時、何かしら和裁と洋裁をすることが日常の生活だった。初期出版インテリジェンスとして産出される月刊女性誌のグラビアが文化の香りを伝えた。文化と仕事が結びついた。
戦前は編み物の商品を在宅で手掛けることもしていた。お店から毛糸の束を預かり、それを男女のセーターとして商品を作った。
戦後の物資難でもお店は仕入れルートをもっていた。
夏になると昨年の冬に着たセーターをほごして、子供時代(小学生時代)の佐藤の今年の冬に着る新しいセーターを編みかえしてデザインを一新してくれた。母の毎年の夏の仕事である。
母から聞いた話しだが、在宅ワークで毛糸の束を預かる時は、お店の人は毛糸の束をハカリにかけて重さを量り、できあがったセーターとの重さを比較していたらしい。ここにいろいろなドラマがあった、と聞く。余った毛糸と抜き取られていた毛糸を量っていた。
働く者の評価もそのようにされていた。
戦前、逓信省といわれていた頃、電話交換手も女子の仕事だった。郵便局で母の結婚前の仕事であった。
戦後、わが国に編み物学校ができ、短期大学や大学を卒業した若い編み物教師は、自宅で編み物教室を開いた。機械編みが出てきた頃だ。昭和45年ぐらいまで続いていた。
出版される女性誌のグラビアのファッションを研究しながら、こんにちのファッションデザイナーはここから生まれた。女の仕事として注目された。
わが国は高度成長社会へと向かっていた。女の内職(在宅ワーク・家内労働)に小さな機械の部品を組み立てる仕事もあった。日本経済は工業化社会へと向かっていた。政府の政策に家内労働法があり、メディアミックス&ソフトノミックス/が設立される頃、家内労働法から在宅ワークガイドラインが成立してくる時代を迎える。
女の仕事は家事手伝いから洋裁、和裁、編み物、茶道や華道、音曲(お琴、三味線)、そして工場の部品つくりと広がっていた。高度成長期時代に農村から金のたまごとして工場の労働者になった団塊の世代を中心に、地方自治体の中小企業政策のひとつにぼくたちが加入している都市の勤労者福祉サービスセンターはこの農村から都市へ出てきた人たちの花嫁修業のはしりの場であった。日本で明治時代以前から長い歴史をもつ花嫁修業は町内会の一角にある家で結婚前の修業をおさめることから、地方自治体の政策により「教室」へと近代化された。
昭和32年(1957年)政府は「もはや戦後ではない」といったが、1960年(昭和35年)大学ではまだ女子の大学進学は始まったばかりで、文学部の英文科や国文科に女子が集中した。高学歴化社会の始まりである。
女子が自然・理工学分野へ進学したのは、それからずっと後である。女子は紅一点で目立った。
大学は地方から出てきた男子学生の方言が飛び交っていた。今のようなテレビの発達で標準語を日常語とする学生は少なかった。
当時、女子も企業へ進出した。短大や大学を卒業した女子は結婚するまでの間、企業のOLだった。
60年安保闘争の敗北と、すべての価値観の崩壊とその挫折を背負って、佐藤がヨーロッパへ渡航したのは、1966年である。円は1ドル360円であった。
そして、女子が結婚を理由に退職して、主婦業に専念した時代でもある。もちろん中には企業に残り、子育てと仕事を両立しながら社会に参加していた女子も多かった。
バブル経済の最盛期、職場では総合職が誕生した。1988年佐藤が起業するにあたって調べたNHKの「国民生活時間調査」(平均時間)によれば、当時の女性に対する一般的な社会通念があった。その通念の内容は、
炊事 2.53時間、掃除 1.01時間、洗濯 1.27時間、実用品の買物 0.56時間、子どもの世話 2.22時間、家庭の雑事 1.24時間、合計 10時間3分
という調査結果が出ている。
当時、一般にいう在宅就業の問題点は家庭問題、社会問題、労働問題などを考慮に入れた家庭にいる「潜在的労働力」として、また出産・育児をかかえる高学歴女子の採用と組織の課題を探ることであった。
1986年頃、山形は流行のワープロ教室へ通った。当時、100〜200万円以上はする業務用ワードプロセッサーで操作できることを目指した。ワープロ専門オフィスの女子はキャリアウーマンの風格があった。
1988年本局は起業するにあたってリコーのワープロをリースした。パーソナルワープロが誕生し始めた頃で、インストラクターは女性の仕事だった。時代の流れはビデオカメラやVTRからワープロへと移っていた。
本局が富士通のオアシスを導入したのは起業から3年後で、当時はワープロが主流だった。女子の新しい仕事として操作できることが求められた。
まだ一般の家庭にはワードプロセッサーがあるところと持たない家庭があった。当時、採用されたスタッフの何人かにオアシスを購入して貸し出した。1台23万円ぐらいだった。
本局では当時はカセットテープの時代なので、サンヨー製のディクテマシンを40台購入して貸し出した。1台3万円だった。設立3年後、青春出版社から『それいけ!! ココロジー』のベストセラーが出て、その印税を組織の拡大のためのディクテマシンの購入やオアシスAX401の中古を40台購入し、スタッフを増強した。
そうして1995年、本局がコンピュータへの移行を決意した年である。
こうして高学歴女子をトランスクライバーやコンポジショニストとして育てた。
働く女子にこころを開き、女子同士のきずなとネットワークを大切にし、経営の方針として独自の経営観、独自の職業観、独自の勤労観、そして独自の生活観の変革と創造を目指して経営の組織観(組織の装置)を高めていけば、女子の力は「がんばる時に巨大な力を発揮し、またみんなの力」を統合すれば、小社のこんにちのような成果をあげることができる。
企業は人間の、社会の基本である家族の多様な生命活動を企業の目的のためにだけ利用(資本の論理で)している。
利用から真に活用へ転換することは、「工夫」によってできる。
出来高制はマスコミにおいては「芸能プロダクション」と同じだ。「知識」プロダクションと言っていい。芸能において求められる資質と知識に求められる資質は同じで、一般の企業の会社の「単なる社員」ではない。スタッフの多くは雇用労働者の習慣が身についていた。
能力と実力は人によって違うが、専門性や得意分野の知識や技術があるか、ぼくたちは一般企業で働いているのではなく、マスコミ業界で働く一員としての資質が求められる。
芸能プロダクションのタレントもマスコミ業界で働くぼくたちも、一般社会を市場としている。それは各産業界の一般的な業界知識や専門性も必要だ。
一般企業と異なった女子の仕事の歴史は、今、知識産業社会にふさわしい知識労働が求められる。それは個人の尊重・尊敬と企業化・産業化の調和で、働く者の感情のストレスを和らげることに気を使っている。納品時間(デットライン)の調整である。プロとしての「人間機械」技術と知識労働の衝突である。品質の確保に焦点を合わせる。これが知識労働者の働く現実である。
一般社会の多様な産業へ向けた知識への資質というか、ビジネスインテリジェンスの基礎知識の土台があるか? 出版される分野への専門性とそうしたプロとしての知識の基礎が形成されているか?
メディアミックス&ソフトノミックス/は出版社を中心に広くマスコミを対象として、「編集プロダクション」としての働きを目指している。
女子だけの狭い生活意識(家庭の大将)というか、言いにくいことですが、子供の同級生同士の、遊び友達の親の一般的な主婦意識というか、「○○ちゃんのお母さんがやっているから」というのか、主婦の同等意識で「在宅ワーク」の意識を持つ女子がいる。隣のお父さんの仕事を、おれもやってみたいと思う男子はいないだろう。主婦だけがなぜこうした非社会的な意識を持つのか? 知識産業社会においては、知識が価値を生み、唯一貨幣と交換でき、所得とすることができる社会である。
女子の意識の変化が時代とそぐわない。遅れているのだ。
世論へ狙いを込めて、企画する編集者のインタビューの内容とインタビューイーの「談話」でも日本語が外国語のように聞こえてしまっては、「資質」が問われる。
採用で間口を広く開き、そして応募者が「わたしにもできるかしら?」と、不安を漏らすくらいでちょうどいい。
かつて家事労働と区別された生活苦を抱える内職者(家内労働)と、小社が成立された知識産業社会への幕開けに情報機器(ワープロ、コンピュータ)を操作する在宅ワークから進化したのではなく、選ばれた種として風格のそなわったSOHO・知識労働者の誕生と成長は、コンピュータにウィンドウズが搭載されて発売されたのが、ぼくたちの企業化、産業化に大きく寄与した。革命的であった。
採用の間口を広くし、わが国の高学歴化社会の到来と集積の中で、企業として成長をしてきた。知識産業社会のインフラ=産業としての裾野をいま形成している。
政府によって保護される個人事業者と区別されて生きていくことは、「小さな力を大きな力」として、企業化し組織の装置をつくり物質的力となって現れていくことだ。
しかし、アジアのどの国にも知識産業社会へのインフラ形成の契機は今のところない。
インフラの形成は企業活動が成り立つ社会的な産業の集積である。知識が価値を生み出し貨幣と交換でき、つまり働く者の生計が成り立つ一定の水準の所得が確保され、企業活動として永続的に発展できる民力といっていい。アジア諸国は知識産業社会の中核となる出版インテリジェンスの手法すら形成されていない。
科学技術、教育水準、ビジネスインテリジェンス(ソフト化)、文化・消費の形成、そして経済民主主義の発展、産業構造のサービス化がアジアのどの国にも発見することはできない。
■アジアの国々の所得について、日本経済新聞は2008年(平成20年)3月10日次のような報道があった。
インド・ベトナム昇給率鈍化
日経アジア社など、11ヵ国・地域調査
香港や台湾、事務職が上昇
日経アジア社と日経リサーチがアジア十一カ国・地域で実施した「日系企業の現地従業員給与・待遇調査」によると、高い給与の伸びが続いてきたインドやベトナムで昇給率が鈍化し始めたことがわかった。香港、台湾、シンガポールでは給与の緩やかな上昇傾向が続き、なかでも現地管理職の給与水準の上昇が目立った。
二〇〇七年の昇給率が前年比で二ケタを超えたのはインド(同一五・三%)、ベトナム(一一・五%)、インドネシア(一〇・〇%)。ただ、いずれも昇給率は〇六年の調査より鈍化した。三カ国の〇八年の予測昇給率をみると、〇七年より伸びが一層鈍化する結果となった。最も賃金水準の低いベトナムを含めた二ケタ上昇国で、工場従業員を中心に急激な昇給を抑える動きが出てきたようだ。
中国の昇給率は〇七年に前年比九・二%と四年連続で前年を上回った。緩やかな上昇が続き、北京夏季五輪が開かれる〇八年も前年を上回る見通しだ。
香港とシンガポール、タイは四年連続で昇給率が前年を上回った。事務系課長職の昇給率が工場従業員を上回ったのが特徴。シンガポールの事務系課長職の〇七年の給与は米ドル換算で年五万ドルを突破し、韓国を超えた。香港では〇七年の工場従業員の年収が一万ドル以下に下落したのに対し、事務系課長職は前年を約二千ドル上回った。
台湾は事務系課長職の年間給与が〇七年に三万ドルを突破。この間、工場従業員の年収はほぼ横ばいだった。日系製造業の層が厚いタイでも事務系課長職の給与水準はマレーシアに並んだ。
香港や台湾、シンガポールでは日系企業の進出初期に採用した従業員が管理職に育ち、要職に就くケースが増加。雇用期間の比較的短い工場従業員との給与水準に開きが出始めている。
現地従業員の労務管理では「人材確保」が最大の課題。五七%の企業が問題があると回答した。
「従業員間の給与水準に不満」との回答も四四%と高い。給与問題は「従業員間の意思疎通」などよりも大きな課題として残る。
調査は〇七年八―十月に実施。現地に進出している日系企業千百四十八社が営業、熟練工などの職種別に回答した。
アジア11カ国・地域の2007年の給与水準(年収)と2008年の予測平均昇給率
|
工場従業員 |
事務系課長職 |
予測昇給率(%) |
| 韓国 |
2万7699 |
4万8348 |
6.4 |
| シンガポール |
1万5860 |
5万0185 |
3.9 |
| 台湾 |
1万4465 |
3万2255 |
3.0 |
| 香港 |
9495 |
4万5525 |
3.5 |
| マレーシア |
5031 |
2万2328 |
5.0 |
| フィリピン |
4293 |
1万5213 |
7.5 |
| タイ |
4095 |
2万1197 |
5.3 |
| インド |
3282 |
1万2008 |
14.4 |
| 中国 |
2969 |
1万3998 |
9.7 |
| インドネシア |
2592 |
1万0876 |
9.8 |
| ベトナム |
1399 |
7110 |
10.5 |
|
(注)日経アジア社、日経リサーチ調べ、給与は米ドル換算、昇給率予測は全職種平均で
現地通貨ベース
この表の示す所得の幅(範囲)は、日本の1960年代の国民の所得(年収)の幅と酷似している。アジアのこれらの国々を合わせた所得の構図が、1960年代の日本経済の実情だったといえる。日本経済の国民の所得格差はこの図表全体と酷似している。当時の日本と欧米との労働者の所得格差と同じだ。
アジア諸国は、知識産業社会の到来までには数10年の時間と経済の成長が必要だ。
ビジネスのモデルとして企業化できるビジネスインテリジェンスの産業としての集積と知識・文化の土台は、インテリジェンスの手法の形成を待たねばならない。アジアの産業資本主義の物象化として国民の意識、文化産業、産業が生み出すビジネスインテリジェンス(ソフト化)、消費文化の形成はアジア経済の「下部構造」成長とともにある。
1950年代の日本とアメリカの文化との関係と同じだ。
現時点での企業のビジネスインテリジェンスの成長と、その産業的集積をどのように形成していくか、企業の成長そのものである。
こんな発想が成り立つかどうか、東大の学生は集団討議型だが、早稲田は優秀なリーダーが大隈銅像の前で、知識を「ピーチク・パーチク」アジることがリーダーの必要条件で、知識の持つムードが学内に醸成されていく。それは一面、共同幻想型だ。
知の構築のための構図として、政府・省庁も懇談会づくりや審議会づくりがはやっている。集団討議型の知の創造なのである。
みなさんもご存知のように、議事録(トランスクリプション)がつくられ、政策コンテンツが抽出される。
大企業においては同様にビジネスインテリジェンスを創造するために、このような手法も今ならできるだろう。しかし、中小企業においては早稲田型の社長がリーダーシップをとって、たとえば経営コンサルタントが新規事業の創出やその他経営課題についてインタビューすることにより、一定の戦略的方向を目指しながら多様な角度から知識を抽出して新しいビジネスインテリジェンスの創出として生み出していくことができるかもしれない。
東大型や早稲田型を組み合わせて、企業のビジネスインテリジェンスとして新規事業の構想を打ち出せるかもしれない。そして、出版インテリジェンスはコンテンツを生み出す鏡(反・理論的本質)だ。
出版インテリジェンスの道のりは紆余曲折してきたと思う。
技術的なことだが、「談話」は速記者によるハショリの速記原稿よりも、文明の利器を活用したテープレコーダーによる記録のほうが圧倒的に完全で正確な記録が再現できる。出版社の「テープ起こし」は編集者の希望により、それはトランスクリプションの真価を発揮できる情報(取材)の完全な再現へ向けて、テープ起こし業者を育てたといえる。紆余曲折もあっただろう。しかし、わが国出版業界は正しい方向に歩んできたといえる。速記者なんか信用できない。手作業の限界ばかりでなく、人間の力(人間テープレコーダー)の限界を露呈した。
メディアミックス&ソフトノミックス/の登場は、欧米のディクテーション教授法から生まれている。トランスクリプションの持つ意味と、一般的には速記者のトランスレーション(翻訳)風の、いわゆるトランスクリプション(速記録=反訳)は編集者から矯正を受け、ディクテーション教授法とは学問的に根拠のない非科学的な「個人的力量」におうものであっただろう。わが国にディクテーション教授法は存在しない。
それは知の創出にとって紆余曲折を伴うものであった。
アジアの国々では速記が国家の占有物になっていて広く社会性がない。国民にもこうした知の創出の教育的体験や文化としての社会的集積もない。
知の創出を担うディクテーションは欧米において学校教育で行われてきた。文明の伝統である。アジアの諸国(東洋)にはこうした文明というものは存在しない。
書くという「翻訳=トランスレーション」が存在しても、データの集積とそこからの抽出という重要な意味の真価が論理的に理解できない。
佐藤はトランスレーションよりもトランスクリプションの重要性について指摘し、その構造はコンテンツを生み出す意味で、二段階なのだということを指摘した。
トランスクリプション(transcription)とは、「顧客データ」の集積を転写したもので、顧客データ(顧客の生の声)の第一義的重要性を言っている。
アジア諸国に知識産業社会はやってくるのか、ぼくたちの経験からアジアの人々にトランスクリプションの真の意味について伝えなければならないだろう。
知の集積は東大型であれ、早稲田型であれ、トランスクリプションとしての情報の社会的集積とリーダーシップが知識産業社会への本格的な幕開けとなる。
アジア諸国にはディクテーション教育の新しい風が必要だ。知識産業社会の段階へ到達以前の産業社会で知を創出するインテリジェンスもなくITが一人歩きしている。
韓国にも中国にもこの国民の教育的伝統の風土がない。
ぼくたちの企業化、産業化は知識産業社会のインフラとして出版業界を中心に出版インテリジェンスとして集積し、専門職として分業化が可能となった。そして、企業(産業)として成長している。
トランスクライバーの誕生である。女子の仕事としても注目されている。知識産業社会で携わる女子の仕事だ。
「知」が道具化している社会や経済からは、模倣から脱出できない。
佐藤の気づいた問題意識だが、テキストの織りなす表現力は作家の文芸作品から学ぶものが多いが、映像のもつ演出力(演出用語)の狙いの間に思考空間の、気づきへの反射と創造力が知識産業社会でマルチメディア時代をむかえ、後世の日本人はマルチメディアにそなわった新しいことばを生み出すだろう。創造的な実験は明日の日本文化をつくる。
佐藤はかつて「電子テキストなくしてマルチメディアは成立しえない」と言った。
テキストの魔術師たちは映像の空間をどのようにテキストで織りなすのだろうか?
知識産業社会は発展していく。
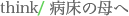
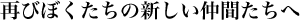
先平成19年10月の31日に終了した日本経済新聞『私の履歴書』に掲載された、60年安保の全学連を指導した共産主義者同盟(通称ブンド)の理論的指導者は、ペンネーム 姫岡玲治(本名 青木昌彦 現スタンフォード大学名誉教授、今わが国で唯一のノーベル賞経済学賞の候補)であった。
佐藤も楽しみながら読んだが、その彼が最終回で次のように言っている。
「ゲームの理論というと、何かいかめしく感じられるかもしれない。しかし社会科学の対象は、他人の意図や行動を推察しつつ自分の行動を選択する人間たちの相互作用だ、という意味でゲームなのであり、それは必ずしも狭い経済交換には限らない。政治も社会的行為のやりとりもゲームの一種である。それぞれのゲームは異なったルールに従うとはいえ、それらの間に相互関係もある。そういう意味で、様々な社会・人文科学の交流や統合の可能性がある。
この「履歴書」で、私は自分史と同時代史をできるだけ絡めて書こうと試みた。書きながら、意識上の自分がコントロールできないDNAが私の深部で働き、自分の前に現れる社会現象と相互作用しつつ、自分の意識と行動を決めるのではないかと、今更のごとく感じた。そしてそういう個人の意識と行動の総和が社会過程を作るのだろう。
これまで経済学、社会学、心理学は、社会と個人のいずれかを主、他を従としてしか見てこなかった。だが最近、個人と社会・時代の循環的相互関係を見直そうという機運がいろいろな分野で生まれつつある。このような状況にあって、私は様々な分野の学者と話し合い、学びたいと強く感ずるようになった。」
60年安保はそれは既成左翼の論理に反対して、新しい自己の思想や論理などの構築を目指したものでもあった。
佐藤の仕事はメディアミックス&ソフトノミックス/を足場に、ぼくたち自身の自己構築をどのように進めていくか。
それは知識資本(人的資本)の形成と専門技術の開発であろうと思う。
出版関連知識労働者としての知識資本を形成することだと考えている。そうしてぼくたちの働く場として、その分野の知識資本をつくり、生み出し、形成していく歴史をもつことだ。
そしてこそ、ぼくたちの存在は歴史的に形成される。
それは存在としての生命力を持ち、「在宅ワーク」の自分たちの論理を20年目に目指すべき目標として武装することである。そして、ぼくたちの仕事を通して、仕事と生活を創造していくことではないか。
SOHO独立自営業者の思想と論理をもつことだ。それは就社し、賃金労働者となる道以外に、独立した独自の論理を構築することではないか。
ぼくたちの組織はネットワーク時代の分散型共同企業群として、個の自立を前提にクモの巣状になっている。佐藤の仕事は一言でいえば、「人を育てる」の一語につきる。
基礎にあるのは、仕事がある、仕事が循環している、それは循環してお金が入る──この循環を通して人は育つ。出来高制で行われている。余裕をもって個の経済力を身につけるこの論理をいかに豊かにしていくか。
一方、スタンドアロン(単体)の軍隊を見本とした組織には、命令と服従によって統率される。命令は軍隊と同じように古典的な給料制によって保証される。ここには仕事の「外」(そと)に楽しみがある。専門知識と技術をゆっくりと育てる環境にない。職場の経済合理性は「人を育てる」ことを目標としていない。目標は利益だ。
この論理の転倒である。
自宅──それは働く場であり、暮らしの場でもある。
この場は生活の舞台だ。仕事の舞台でもある。自分がどう演じるか、演じることを学ぶ場でもある。誠実に仕事と向き合い、対話して自分の成長に結びつける。
事業と商売は違う。事業には夢があるが、商売には勘定がある。
こうして自己研鑽をとおして自己実現へ向かって目指していくのだが、どのように自己の知識と技術を高めて豊かに組織化していくか。
与えられた場のサーカマスタンス(周囲の情況)を受ける。
それはわが国のマスコミ出版業界の動向や局面に携わり、「それはそういうもんか」と納得を繰り返し、幅を広げて編集者との対話を通して学び、自己を高めていける豊かな場をつくり出して人は育っていく。
それで上記の青木昌彦氏の最後のことばと錯綜する。
どう演じるか、自分はこの社会という舞台(社会的な相互の関係)で演じていることを意識した時、そこには自己の描くシナリオが必要だ。シナリオとは楽しみをもった成功のストーリーでもある。仕事の楽しみを通して自己実現する道である。
佐藤は生命科学に物象化(連想)のヒントを求め、社会的現象の分析などを弁証法や電気理論(本質・形式・要素・目的)で整理し、ゲームの理論を駆使して、そして演劇論から自己の行為の「演じる」ことを学ぶ。自己の組織化として武装し、独立の過程を自己認識(学ぶ)していくことだ。それは、ぼくたち自身の現実的生活感が土台になければならない。レーニンは「社会主義プラス電化は共産主義」といった。思想や論理を統合する夢や柔軟性、リダンダンシー(redundancy;冗長度、誤りの訂正、余裕)がここになければならない。演じる迫真もここにある。自分に正直であることだ。自己の行為は物質的力を持つようになる。
そのためにどのように演じることを行為するか、行為の哲学として
自己の営業行動=運動(ゲーム)の構築と成果が組織をつくる。
組織が先にあって運動が後にあるのではない。運動が先にあって、組織は後からつくられていく。
組織がまず先にある組織主義者のもつコスト/コンプライアンスは組織主義のもつ弊害そのものである。その閉鎖性──開かれた「マイホーム」というと多くの人はピンとこない。それは自分のこころの中(こころの腫れもの)に理由がある。それが組織主義を生み出す。
自分が企画を立案し、企画(提案営業)が成果(仕事)をつくり、そして自分の企画した一枚の紙が、自分の営業した仕事が自分を振り回し、その結果として組織は後からつくられていく。自己や事業の組織化が始まる。
役割分担でネットワーク化しチーム化する。それはミッションのためのチームだ。今年ホームページで発表したトランスフォーメーション戦略のイメージでもある。
低コストの運動としてそれを組織化する。SOHO独立自営業者の仕事はこうして始まる。
組織主義は自己を保身する。それは運動(営業・行為)を通して最適に修正していく。
存在論者(根源性)は組織主義に陥る。自分は常に社会(クライアント)と共にあることを忘れる。非社会的な自己論理(世界)に陥る。
ぼくたちは社会派といっていい。社会の一員として現実の市民社会観をもち、積極的に社会との関わり、社会への貢献をし、社会の中で自己を認識する、それは社会と個人の統合という自己組織化の過程でもある。
どのようにビジネスを構築するか。
それなりに豊かで高度な市民社会を迎えている。若い世代の「マイホーム」は閉じ込められた家族のこころから社会へ開かれた家族のこころを持つだろう。こころの封鎖性を乗り越えて、欧米先進国で20世紀末に出現したスモールオフィス・ホームオフィス(SOHO)の企業体としての原理がここにある。21世紀初頭──確かな存在として成長し、現れようとしている。社会問題化する「崩壊する家庭(家族)」を目前に見て自分の進路を生み出していくことだ。経営理念に賛同し実践できる「普通の人材」を求めている。
命令・服従型組織の否定と対等の役割分担(適材適所)の創出、企業権力の否定の体系を目指す。「組織の装置」は他者文化との異文化交流(ろ過装置)でもある。 労働の自由と快適な環境、そして各人の個性の発揮──生き方の体系の構築──「自分らしさを生きる」生き方を求めて、いわゆる「経験者の即戦力」を求めにくい理由がある。みんな初めての初心者ばかりだ。経営情報を公開して労使の関係をつくらない。各人が自立した対等のパートナーシップを実現しようと努力している。
企業の成果主義は欺瞞だ。
ルール・手順・順序に基づいた人間の感情が入らない、働いた分の単価の集積を自分で計算し、請求書を自分でたて働いただけ報酬をもらえる出来高制が基準で、ここには経済学的論理を否定した経営学の立場からアブローチする。月収5万円以上はこの8月から労働生産性手当てとして2,000円を追加して、手当て6,000円で、SOHOならではの経営コストが安くなり実施した。音声ファイルの入稿が増えたのが一因である。スタッフへ還元した。音声ファイルでの入稿──クライアント様には感謝しております。
出来高制以外、人間の感情が入る。それは欺瞞が多い。管理者はいらない。不要だ。
ルール・手順・順序に従うだけだ。こうした組織を目指していく。
再びぼくたちの新しい仲間たちへ
起業の土台づくりをいかに進めるか。
多様性の中で個性の自由な輝きを求めて、ぼくたちの働くこの場をいかに豊かにしていくか。
ぼくたちは知識と技術を使って原稿をつくっている。材料費にコストはほとんどかからない。原価は知識労働の適用でコンピュータとその電気代が必要である。
そして、交通費はかからない。自宅での食事以外はほとんど現金は不要である。女性においては出勤するための装いも、それに対する様々なコストも不要だ。
自分本来の専門職をこなしつつ、基本は時間を有効に活用して売上げを高める。いかに生産性を高めるかに焦点をもつ。
生計の土台を構築しつつ、自分の仕事の土台をいかに拡大していくか。
独立すると、仕事への姿勢の軸が変化する。サラリーマンではないという自己規定が必要だ。
この仕事場において営業は不要だ。自宅で待っていればどんどん仕事は入る。現金が必要になれば本局が負担してくれる。
夫婦でチームを組み、生計費50万円ぐらいを確保するのはそうむずかしいことではない。
まず生計の土台をつくり、自己責任において外からの受託もこなす。こうした作業計画を本局に提出し、時間を有効に活用し、労働生産性を高めるよう工夫もできる。
所得増大のチャンスは夫婦の役割分担(パートナーシップ)を発揮することだ。夫婦の専門性を活かして呼吸を合わすことである。
不思議なもので起業時の事業計画からはみだした業務が天職となることもある。
ご夫婦の性格は、仕事をとおしてのみ人間性がいろいろな場面で現れる。夫婦の「価値観」の衝突で意外と知らなかった二人の側面である人間性と性格を知る。意外と世の中の夫婦は表面的にしかパートナーを知らない。一般に夫は妻を知らないし、妻も夫を知らない。夫婦愛は仕事の局面に立ち会うことによって磨かれていく。「お金」に対する価値観はこころの中の深部に宿る。新しい次元の夫婦関係の第一歩となる。絆は深まるであろうか。それとも仕事(局面)の判断をめぐって対立するか?
現下の経済環境下において、仕事に一本の「信念」を持つことだ。他人であるコンサルタントは信念まではつくってくれない。パートナーシップで仲良く真価を発揮することだ。
自宅をオフィスにして、起業拡大のチャンスをつくり出していく。
起業しても形のないサラリーマン的力量で「変な仕事」に携わったこともあるだろう。仕事に形(職名)をつくる。安定した取引関係を生み出していくことだ。一般賃金労働者と変わらない非定型業務をこころの中で拒否することだ。そうしてこそ事業に形ができてくる。形は「1本目の柱」にする。いわゆる請負労働者になってはいけない。様々な格差のワナに入るな!
小さくてもオフィスはオフィスだ。自分の存在証明でもある。
本局には出版社から相談された思わぬ仕事──専門性を活かした仕事も入る。
生計費50万円相当は、本局の売上げで何%になるか、あなたの利益率は悪くない。夫婦で自宅でできる仕事の利点はいろいろある。
1日24時間、二人は一緒だ。夫婦関係は新しい次元へと向かうことができるか。前向きに進むSOHOの新しい未来がここにある。サラリーマン夫婦の「夫、元気で留守がいい」はぼくたちの夫婦の次元とは異なる。それとも「愛の共同幻想」の中か。事業に「真剣」に取り組むようになると愛のミスマッチは拡大する。パートナーシップの土台は大丈夫か。
この50万円の所得は、サラリーマンにおいては「所定労働時間」(4〜6時間)の範囲内の収入である。仕事はすべて所得増大へと結びつく。この所定労働時間の範囲内で生計の土台は間違いなくつくれる。残業時間分を外からの受託の業務にあてるという「逆転の発想」をもつことと、「比較優位」の業務としてだんだんと認識できるようになる。現実の「受託業務量」をプラスして考えてみては? 二人で月収70万〜80万円は難しいことではない。自分の仕事として事業の夢も軌道にのってくるようになる。
仕事がある。働ければお金が入ってくる。頑張れば頑張っただけお金が入るという原理が、勝利につながる。あまり言いたくはないが、残業5、6時間程度で所得は倍増する。
しかし、この考えが大切なのではなく、どんな「生き方」をするかだ。考えることと楽しいことが一致しなければならない。知識産業社会でいかに生きていくかだ。自分の生命(いのち)を大切にする生き方である。
ぼくたちは有限な1日24時間という時間をもっていることになっている。
時間は増えもしないし減りもしない。時間は有効活用して時間をつくる以外にない。時間は誰にでも与えられた平等な資源だ。
多くのスタッフは1日所定労働時間として8時間を設定しているかというと、ぼくたちはサラリーマンやOLよりも更に週労働時間は圧倒的に少ない。パートタイマーよりも少ないだろう。知識・労働集約の原稿をつくっている。
しかし、1日4時間、5時間のスタッフがいるかとすれば、8時間以上労働時間を確保しているスタッフもいるだろう。
朝9時から夜8時までの11時間通しの労働時間はきつい。スタッフの内心は「稼げる所得は企業秘密」だ。それはリダンダンシーが働く。
朝9時、コンピュータに向かって座る。午後3時にはそろそろ子どもが保育園や幼稚園、小学校からの帰宅時間だ。「お母さん、ただいま」と元気のいい子どもの声を聞いて、どんなことがあったかゆっくりと話しをし合い、元気な子どもの成長を感じ、お父さんへ楽しい報告の話しのタネもできる。そうして、やがて夕飯の支度と、子どもの習い事で子どもが出る時間だ。子どもと一緒に出かけて、ついでにスーパーに寄って夕飯の買い物をする。そして、帰宅して夕飯の準備に入る。子どもを向かいに行き、子どもとの帰宅で一緒に夕飯をいただく。
夫の帰宅時間は平均午後9時である。夕飯を済ませて、再び仕事に入る。
夜8時、9時、10時の3時間は原稿の納期を抱えた貴重な時間だ。子どもの成長と夫婦間の話にはトランスクライバーの新しい仕事の内容が知的会話をつくる。そして、くつろいだ楽しい自由な時間でもある。
この労働時間のモデルは、在宅ワークにとって普通の家庭で行われている。
日中3時間ぐらいの労働時間をつくれば、夜の時間を活用することもできる。
なかには、徹夜して納期に間に合わせている人もいる。
子供が高校生ぐらいなると、親からだんだんと自立していく。子供が受験勉強に集中するようになると親として共に“残業”の仕事をしてもあまり苦にならない。
しかし、本局ではスタッフからの仮納品時刻を見て驚くこともある。たびたび深夜だ。
みんな頑張って仕事をしている。毎月の報酬料金の支払日には、感謝の気持ちでみなさんにお振込みしている。ここには経済学的論理はない。資本の論理もない。どのように経営が成り立っているのか、ここに本局は焦点を合わせている。
ノーベル経済学賞を受賞したシカゴ大学のゲーリー・ベッカー教授の人間を経済学的労働力の市場価値としてしか見ない人間の「人間性」に対する攻撃を拒否する。人間を土台とした経営は情感や感情にあふれた生活を抱えて呼吸する複雑な人間としての存在を認める。経済的人間の一面的な経済学的概念を拒否する。経済学の合理的人間を拒否する。
労働と生活が融合する現場で、市民社会で暮らす普通の家庭の目線(常識)でみつめ、企業経営にとって多様な個性を活かして働く者の誠意あるエネルギーを発揮できることに焦点を合わす。旧世紀の経済学と言っていい。人間と経済学が対立している。資本の論理があって21世紀哲学する人間の知恵が捨象されている。旧時代の経済学教科書でしかない。
社内においてもベッカー教授の経済思想は「総スカン」だ。それではスタッフのこころがつかめない。悪徳経営者の思想に対して本局の考え方はスタッフの求心力を強めている。
ベッカー教授の経済思想では働く者のこころがつかめないのだ。そして、企業のコンプライアンスは内部からの危機におびえている。
イラクやアフガニスタンにおけるアメリカの軍事戦略は人民のこころをつかむことはできないだろう。新しい時代への幕開けとなるか。
仲良しクラブの価値観が同じだという思い込みだけで、「新テロ法案」はどうなるのか。
かつて私の師匠であり東京・茗荷谷の禅 林泉寺住職であり、テレビドキュメンタリー『裏から見た世界旅行』(TBS)のプロデューサーであった故 江田和雄師は、イタリアで、映画『世界残酷物語』のドキュメンタリー作家ヤコペッティ氏とお会いした時のお話をしていただいた。
ヤコペッティ氏は、「これからは発展途上国やアフリカに秘境があるのではなく、世界の都市に“秘境”が潜む」と言われていた、と伺った。先進国のいわゆる最先端都市にテロや秘境が隠されている。政治中枢の頭脳そのものに原因(秘境)が潜んでいないか? 現代の秘境とは格差だ。やがて格差は文化として分化し、固定化するかもしれない。同盟も仲良しクラブになった。国連の安全保障理事国入りを目指すわが国にとって、世界にどのようなリーダーシップを発揮することが可能か? 中央アジアの統合に向けたわが国の外交にふさわしい世界戦略をもう少し政府は国民に説明すべきだ。
ぼくたちはベッカー教授の経済思想を否定した新・新日本的経営の風土の構築を目指していく。
毎日の仕事を通して人は人材として育っていく。人間を「教育」で育む新・新日本的経営にこだわっていく。人間を金儲けの道具だと思っている経済学に反対する。
利潤の最大化は人間を経済に従属させる。ぼくたちのような貧乏会社にできて、なぜそれなりの企業にできないのか? 育児と介護を抱えながら働く知識労働者の未来を建設したい。
やがて生活が安定し、楽しさが見えてくる。軌道にのるとおカネはくっついてくるようになる。
この実人生はサラリーマンにとっては「所定労働時間」である範囲内の普通の「生き方」である。「自分スタイルの生き方」が軌道にのる。
だが知識能力が問われる。「上級」の日本語の知識能力も問われる。この土台の上に知識労働の地平がある。編集者と原稿をとおして対話できる力だ。原稿は呼吸しているか?
呼吸を感じる原稿と呼吸を整えて読む原稿は違う。句読点は息の切れ目と意味の切れ目に入れる。前者は呼吸を感じ、後者は呼吸を整えて読んでいく。ある意味で芸術とは呼吸だ。感じながら読む原稿と意味の切れ目を活かした原稿とは違う。感じるというのはことばに音色や香り、スタイルや匂い、調子、語調など雰囲気を感じることだ。呼吸が乱れた原稿は読みにくい。再現の物象化である。そこには禅的な深淵が見える。感じるだけではない。見えてくる(見抜く)。
その呼吸を活字に置き換える。ディクテの手法は一つ一つに意味を持つ。形式の美しさがある。内容を持つ。何事にもいえることだが、我流は下品だ。
「聞き漏らし」「聞き間違い」のない「ディクテの力」が付いてくる。それは国語一般の力と国語の特別な知識も求められる。「ボケッ」とディクテしていると意外な「聞き漏らし」や「聞き間違い」の落とし穴に陥る。
プロになっていくことだ。だんだん普通の「男と女」からプロの知識と技術を持つトランスクライバーやコンポジショニストになっていく。校正者として育っていく。
街角で「ホームレス」が『ザ・ビック・イッシュー』を持ち、路上で立って販売している。
英国ビックイシューの創始者 ジョン・バート氏は「ホームレスには金を与えるのではなく、仕事を与えよ」と言っている。
佐藤もよく考えてみた。
格差のない普通の報酬料金で仕事があることが前提である。コストが安いからという多くの経済学的発想ではなく、またバラマキでもなく、仕事の循環をとおして人を育て暮らしていけることが大切だ。
あえていえば起業して週休二日や年末年始休むというのは、どんなことになるか? しっかりと仕事をして誰よりも働くことである。現ナマをより多く手にすることだ。自立・独立する意味である。身体に気をつけて!
メディアミックス&ソフトノミックス/には知識を持つ労働者と、SOHO独立自営業者が混在している。これがすばらしい組織となっている。リダンダンシーが生まれる。
しかし、起業して10年は無我夢中で自分の仕事とその存在を高めていくことだ。
今年も年末年始、年中無休、SOHOであるがゆえの24時間稼動で、この現下の状況を乗り切っていきたい。こうしてみんなに「仕事」が届いていく。営業は本局の仕事で、みなさんの仕事ではありませんが、この組織が成り立っている土台でもある。企業社会ではこの土台が末端になっていて転倒している。悪質さの温床となっている。
本日11月11日、クライアント様への納品時、メールにこのメッセージを入れて、納品していきます。
「給料」では実感のない本物の達成感を味わっていただきたいと思います。
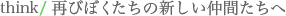
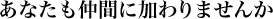
先メディアミックス&ソフトノミックス/の経営理念は正直・率直・誠実・個性であることは、みなさんもご承知のとおりです。この4つのことばには経営理念の規律ある働きがあります。
この経営理念はぼくたちの仕事の土台(受託生産)であり、根底に流れている精神です。
それは企業の永続性を目指す生命力であり、原動力であり、もし事業に、いわゆる営業が必要だとすれば、すべての業務の根底に流れている精神です。
新聞社、出版社の、新聞や雑誌、書籍の取材に、その出版社らしい伝統のDNAに輝きを入り込むのも、この経営理念の現実化が求められます。
この経営理念を現実化するために、現実化を通して毎日お仕事をしています。
仕事の継続性とはこの経営理念の生み出す現実化によって生命力を発揮し、原動力となって事業の永続性を生み出すのです。経営理念の働きです。
この経営理念はのびのびとしたあなたの個性から生まれます。資本の論理を「組織の装置」にろ過して、ふたたび経営理念として生命力が蘇える。蓄積しているのは「お金」ではありません。精神の喜びです。自己精神の自己実現です。自分らしい喜びです。そして、自分の大切な家族の喜びです。
組織には「憲法」が必要です。この経営理念とみなさんとの「労働協約」という第一番の「憲法」に従うのは本局です。本局とスタッフの共通の土俵に憲法があります。この「憲法」はみなさんとの約束事です。まず従わなければなりません。組織の原則でルール・手順・順序があります。
また経営理念はインデペンデントキャピタル(独立資本)によって守られていなくてはならない。クライアント様の思想および言論の自由はインデペンデントキャピタルによって不正流出が守られている。一般企業の営業活動とは異なっています。
そして、クライアント様の知的財産権を守り、個人情報保護法を遵守している。
ぼくたちのビジネスモデルの形式はマスコミ業界に携わりつつ「在宅ワーク」を可能にする事業のビジネスモデルを構築してきました。
それは職場へ毎日電車に乗って通勤することではなく、自宅で仕事ができる事業を開発してきました。
ぼくたちには家庭生活、社会生活、経済(活動)生活などがありますが、人間として、また市民社会で市民として生きていることと同時に経済活動その他も大切です。しかし経済活動が日常生活のすべてではありません。
みなさんが社会生活や育児、介護など抱え、そうしたなかでお仕事(経済活動)をしています。地域の行事、学校の行事などもあって暮らしています。本局の考える市民像です。
「雇ってもいなく 雇われてもいない」労働関係と生産関係を20年間続け構築してきました。
この持続可能なノウハウを公開しても他社が真似のできない特有のものだと考えている。
成り立っている土台をあなたは知りました。
この労働関係と生産関係は3つの側面から成り立っている。
1) 仕事を通じて知的実現が可能であること。仕事が楽しいこと。
2) 持続可能で仕事に切れ目がないこと。お仕事が継続的にあること。
知識労働者を囲い込み、“放牧”している。みんな自由だ。
3) どんな些細な仕事としての行為にも「お金」がくっついていくこと。
「カネ」にならないことは皆無であること。さまざまなサーカマスタンス(周囲の情況)の中で、心情が測定される。一般企業の職場には「カネ」にならない「仕事」が多く、給料として支払われている。どんな仕事にも「お金」がくっついていくこと。請求しにくいクライアント様の便乗にも「お金」がくっついていること。そのためには「経営コスト」を安くする。
スタッフが「元気」なのは、非定型業務にも時給レベルでコスト(報酬)が計算されている。知識労働の価値が測定されている。たとえば、「担当スタッフと打合せしたい」と電話が入る。時給と交通費がくっついていくことが重要だ。できるだけ電子メールを使うようにしている。
それはウェブオフィスで全員に報告される。
ぼくたちは「在宅」で仕事をしている。在宅での属性行為は出来高制だが、「外出・出勤」は属性と考えていない。
交通費や時給は自宅から外出先、帰宅まで労働時間と考えている。本質的な前提はSOHO独立自営業者だ。
ある先生は「バカにならない交通費」と言いました。
また、クライアント様との信頼関係のなかで、瑕疵が発生した場合、本局が一切責任をもって修復している。担当者を替えたり、請求を放棄したりして、修復などしている。担当者への報酬は支払われる。
労働基準法に基づく。
だから、スタッフは責任ある仕事をしている。各人の業務への自覚が非常に高い。この職業意識を持つまでお仕事をとおして教育している。何人か個人的事情で仲間から離れていったが、新しい職場でキラリと光る人材となった、と言ってお礼の電話が入ったこともある。どこへ行っても光る人材として注目される。
「仕事とはなにか」仕事に対するあなたの考え方をお聞きしている。キャリアデザインはここから始まる。みんな「普通」から出発する。
当然のことですが、職場で飛び交う乱暴なことばも親しい職場の人間関係とはいえ、ぼくたちには一切乱暴なことばはありません。上下の関係もなく組織は全員平等主義が基本です。丁寧な言葉遣いが基調です。在宅で仕事をしているので録音状態が良くないこと以外ストレスはありません。
こうしたことはその企業の文化をつくるばかりではなく、人間関係が独立した人格として尊重されていなくてはなりません。そこには知識労働者として尊敬される人格が息づく。
この20年間、本局から子局への業務命令は一切ありません。仕事とは命令によって行われるものではありません。軍隊の組織を見本とした一般企業の職場とは区別されます。
企業社会の職場には「命令と報告」が義務づけられますが、ぼくたちには「命令」ということばはありません。パートナーシップに命令は不要です。夫婦関係は「命令」によって成り立っていない。
出版社からの毎日のお仕事は、本局でキャスティングされていて、お仕事はメールと電話、FAXでみなさんと相談しながら「このお仕事お願いできますか」と言って、納期を確認してお願いしています。これはいわゆる「命令」ではありません。本局と子局の対等のパートナーシップで成り立っている。
また労働衛生週間に参加し、福利厚生制度に加入している。
メディアミックス&ソフトノミックス/は新しいネットワーク時代の組織です。組織の在り様はSOHO独立自営業者の共同企業群で、本局が組織の装置の要となっています。要とは働き(機能)をいいます。スタッフの実体は知識をもつ労働者です。
各人は尊重されるべき独立した人格として本局に統合されます。
メディアミックス&ソフトノミックス/は「在宅ワーク」をつうじて出来得る仕事を事業として求めました。みんなの力で支え合い、ある時は依存し、しかし自立した働きをもって構成されています。ウェブオフィスはみんなが見ている。報告やコミュニケーションは電話やメール、FAXなど活用して行われています。
子局は北海道から四国まで分散点在し、ウェブオフィスをとおして全員が仕事の情報を共有し、みんなの力がひとつに統合されている。能力があり、地方に在住している人にとっては地方にはない「異文化」に接することでしょう。
本局も忙しい。そんななかで「一言」のスタッフへの「営業」もクライアント様への「営業」も同等に大切だ。給料で雇用してはいない。みんな自由だ。いかに統合するか! ノウハウの本質は上記の3つである。この20年間、「相変わらず」が大切である。10年越えたらあと「10年」、「相変わらず」が大切なのである。スタッフも本局も共に10年、20年、「相変わらず」が大切である。
この組織の経営理念と目的は、かつて「やりたい仕事、なりたい自分」を天職として求めましたが、今は「自分らしくを生きる」生き方を目指しています。
人間として「自分づくり」と「自分スタイル」を生きて、もっと「自分らしく」を今に生きようと思っています。
仕事も暮らしも只今を生きる。
子どもの成長(精神の発達)と仕事とを結びつけて自分の家族の「今」を生きる生き方。
「今」だから「今」らしく「今」を生きる、生きていくヒントや知恵を仕事を通して学ぶ。
お仕事には生活の知恵があふれている。自分の仕事である経済活動と家庭の仕事とのバランスは自分でつくる。
労働時間である経済活動6、7割、家庭3、4割、となるのは子どもが中学生になってからだ。それまでは3、4割の経済活動と6、7割の家庭とのバランスだっていい。
塾へ通うようになる子どもの成長とともにバランスも変化する。所得の増大を求める時期もやってくるだろう。1日90分もの7、8時間で月収20万円〜25万円を越えるようになると家計経済に組み込まれる。ご主人の態度も協力的になる。妻(パートナー)の仕事として認めるようになる。午前中3時間、午後4時間〜5時間、自宅なので夜の時間も使える。
お仕事で楽しいのは、子どもの年齢とともに、そのお仕事のテーマ(内容)とともに子どもの成長と歩むことだ。
保育園へ通う子ども、幼稚園へ通う頃、小学校へ入学した子ども、中学校へと行くようになった子ども、仕事のテーマが子どもの成長とともに母を意識する時だ。母であると同時にトランスクライバー、コンポジショニストでもある。
佐藤も祥子が小学校3年生の時、教育技術法則化運動の「とび箱」のビデオをつくった。
先輩が塾を経営していたが、そこの塾生をバスに乗せて、ロケ地の立川の小学校まで運んだ。祥子も先生の指導によってとび箱が跳べるようになった。祥子の喜びを父として同じように感じた。「なわとび」の新兵器も買って与えた。「なわとび」が上手にできた。
両親の娘として「介護問題」に取り組むお仕事も勉強になる。
ぼくたちの求める自分らしさは、現代の現実の普通の生き方である。仕事と生活の境界に生きる生き方。「自分らしく」を生きていこう。自分の家族とともに生きる自分の仕事と夢を大切にした生き方である。
経営は大変だが、経営理念とパートナーシップの目的は、この楽しさをつくっていくことだ。
快適な環境と働き方を自分らしく求めて! あなたの日常の自然な生活に「異文化」をつかもう。
SNS、ブロガー、雑誌への投稿経験者は応募をご遠慮ください。
(この一文はウェブオフィス「営業情報」平成19年10月21日投稿された、これに修正、加筆しました)
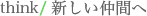
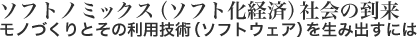
先週土曜日、町田へ買い物に出かけた。
街のどの小売店でも販売員にアルバイトやフリーターが多くなったと思う。スーパーストアーの花屋さんだったが、接客技術のイロハが未熟で、販売サービスに対する基本や技術のレベルが低いことに気づいた。観葉植物など関心があったが話しかけることをやめた。
小売店にも優劣がつくようになった。
かつて後進国やわが国の戦後の長い歴史においても、モノの販売は「ハードの販売」であった。今ではモノとしてのハードの販売からソフトウェア(利用技術としての消費)へ変わった。置物のハードに囲まれることから、快適な生活、行為・行動をたのしくするソフトウェアとしての開発が注目される。
消費はソフトウェアとしてその利用技術でたのしんで消費生活をするように変わった。
消費はリピーターをよぶ。
フリーターの販売員と専門性をもつ販売員とでは、リピーターをよぶかよばないかで売上げが異なる。売上げがあがれば労働生産性は向上する。
訓練された接客技術は小売店の優劣を決めるようになった。
いまわが国は先進国型の消費社会へ移行している。豊かな社会でたのしい生活を求めている。しかし、多くの消費者はこころの豊かさを実感できないでいる。
もともと日本人はハード志向で、その利用技術を使ってたのしんで消費生活をしているだろうか。暮らしの多様性の面で都会的な生活環境の中で、利用技術を生み出す感覚に慣れている。
モノは道具だ。道具としていろいろとたのしむ利用への開発が不得意である。こんなものにも道具として使えないか? これにも、あれにも工夫できないか。使ってみて意外なたのしみ方がうまれないか。
開発技術者の独善で顧客にたのしみ方(操作)を教える「ハード志向」ではなく、「モノ」がいろいろな生活場面で活用できるモノのもつ完結性が本質であることが問われる。
いまは開発技術者の独善によって人間は道具に使われている。ハード志向は顧客が開発技術者のアバターとなっている。
経済のソフト化、サービス化とは何だろう。
モノの働きである機能の普遍性が国際製品を生み出す。「つながる」「延長の思想」である。
モノの本質が失われていないか。モノという自己完結性と無限の活用性が両立していないのだ。
日本文化の伝統と欧米との相違がここにある。
日本人の消費性向である物象化に日本人特有の個人的(普遍的ではない!)独善はないか。
フリーター販売員は販売の基本技術が未熟で、販売まで到達しない。
サービスのレベルが低いのである。
専門性への接客の知識や技術を学び、知り、適用するこころの構え方が教育されていない。売上げに差がつくのは当然である。リピーターを生み出せない。
フリーターの教育で気になるのは教育による「こころの構え方」で、販売の現場に立ち顧客が手に取る商品――顧客の空気をよみながら「見る目」「気づく目」「販売員の自分のこころへの目」、これらを養う目を持つことである。見えないこころを見る目である。
フリーターの粗雑なこころを教育で直すことができるか?
現代の社会はソフトノミックス社会でもある。
情報化、デジタル経済化、知識経済化、ソフト化、サービス化のモノの働きにこれらの要素を商品にこめて、販売員はモノの情報性や知識経済性、ソフトとしての活用事例、成功事例など顧客へその商品知識をサービスとして実現しなければならないだろう。消費の最前線が高度化してサービス化している。
ソフトノミックス(ソフト化経済)の経済要素が現れてきた。
ぼくたちの仕事にもこの経済要素を付加して、業務工程を改善してモノ(製品)へこめなければならない。生活と労働(職場)が融合しソフト化、サービス化が価値を生み出している。
こうした経済要素を工夫して付加していく。
顧客は日常の生活にモノの利用技術を適用し価値を生み出してたのしんでいるだろうか。
発展した先進国の経済、欧米において消費者はこの商品の利用技術が生活の豊かさを生み出している。消費者として現代性をもつ。
フリーターにはこうした消費者としての意識はないようだ。あるいは意識と労働がかみ合っていない。商品知識も教育されていない。ソフトノミックス社会においては、生産者であると同時に消費者でなくてはならない。
意識の高い消費者にとって「きれい」とか「美しい」とかは、いまや消費社会の最前線では旧時代的なのだ。消費者は知性のかたまりとして中身が濃いソフィスティケート(洗練された)都会の文化的な消費感覚をもっている。
ソフトノミックス社会の消費者の時代として、いまや「美しい」から「都会的、知的でおしゃれ」へとこうしたサービス感が変化していることに気づく。「生活と労働(職場)の境界」を生き、どちらでもない二面性をたのしんでいる。
ここには快適な行為をともなうもの(不快ではない)としての消費であって、部屋の置物ではない。
自分の行動のまわりにある快適な消費財、街にでかけるファッションにもそれは置物ではなく、利用技術(ソフトウェア)への感覚として変わってきている。それともアバターとして変身しているのか?
経営者がこのことに気がつくとフリーターの仕事はなくなる。
いまは人手不足が仕事をみつけているが、消費社会は欧米型になっていることに気づく。それは行動する消費者なのである。消費がソフトノミックスの新しい生活文化をつくっている。
いわゆるブロガーは企業の開発技術者のアバターとして、コピーとなっていないか。システムが存在論者のつくった仕組みなのだ。
現下のソフトノミックスの陰の部分としての文化的現象だと思う。
モノづくりも大切だが、その前に人づくりがある。
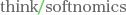
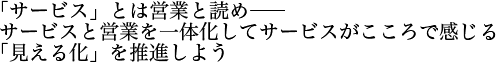
メディアミックス&ソフトノミックス/という「学校」は、人間についての教育や仕事を進めていく上で、必要な知識や技術について学ぶ場である。
それは金儲けを教育する場ではありません。正直・率直・誠実・個性をもった勤労精神を教育する場でもある。パートナーシップ理論の原理です。
この豊かな勤労精神は、生産的であることから生まれなければならない。
ぼくたちの仕事の立場は、著者に対して勤労の生産的協働(効果を上げる)から自分の成長が育まれていく。得善損悪の思想からは生まれない。思想は官製のNPOよりも原理的である。
パートナーシップは共に成果を目指す生産的協働を通じて、ぼくたちの精神の喜びや仕事の楽しさが生まれる。自己の有と権力をもつ国家利益(企業利益)よりも原理的である。パートナーシップの存在の有は、一般の「夫婦関係」の物象化、科学、理性的連想にその原理を求める。
営業は常に生産的でなければならない。それはこころに響きあう営業だ。共創のための愛(知恵)である。
ウェブの「営業情報」が編集者と本局、子局を結ぶコミュニケーションの場でもある。
編集者とのコミュニケーションは電話や電子メールを活用し、編集者の細かな指示を受け入れ、この受け入れが編集者と本局、子局のコミュニケーションを構築している。
ウェブ「営業情報」は本局へ伝えられたすべての情報をスタッフへ公開することから一日が始まる。
ぼくたちの課題は、編集者の「無理な注文」を受け入れてこそ、本当にお役に立つ時である。自己の有をパートナーシップへと発展させる。
最大のサービスとは納期を早めることである。
このような生産体制をどう構築するか、みなさんにとっては余裕をもって、そしてこれを受け入れるにはスタッフの増強が必要である。本局最大の課題となっている。
「協働」とは共に成果を上げることだが、それは生産的であることだ。快適に生産的であることを前提にしなければならない。そして、ぼくたちの組織の仕組み(協働)がパートナーシップで成り立っている。
こうした状況をつくり出し、生産者の都合(プロダクトアウト)は顧客第一(コンシューマーオリエンテッド)に考えて組織の仕組みを顧客第一の一色に染めなければならない。
いま政府はカネのとれるサービスを発明しようとしている。
スタッフにとって生産的であるかというと、常に「みんなで渡ればこわくない」、官製サービスを権力によって実現しようとする。「夫婦の関係」に権力は無用だ。
こうしたなかで、サービスとは営業と読めと言った。「官製サービス」の典型といえるマニュアルメニューのサービスは、生産者志向(プロダクトアウト)だ。このコペルニクス的転回こそほんとうのサービスといえる。原則や方針をもたず、具体的事例にそってケース・バイ・ケースで境界のないサービスで対応している。
アメーバ営業の本質は個人の編集者から編集部全体へ拡がり、他の編集部へ、そしてフロア全体へと、次のフロアへと拡がっていく。こうしてアメーバは拡大していく。
メディアミックス&ソフトノミックス/のDNA(正直・率直・誠実・個性)の良心がくっついていく。それは編集者個人と相談することから組織的対応へと発展し、「企業対企業」のパートナーシップへと発展してきた。サーカマスタンス(周囲の情況)半分、社会的常識半分の「拮抗」を測定する。本来、性悪説の立場に立たない。パートナーシップ(夫婦関係)の原理だ。この意味で「官製サービス」とは二枚舌だ。サービス営業の偽装(偽装業者:性悪説)と対立する。スタッフの採用にあたっては、「どんな人間か」を見ている。
小社の貧乏経営で吸収していく。ビジネスを超えて安心の営業こそ基本で、アメーバとしてDNAが広がっていく。こうして編集者との長期継続的関係で経営が成り立っている。サーカマスタンス(周囲の情況)は顧客とはいつも「恋愛中」なのだ。緊張関係が続いていく。結婚はしていない。官製サービスとは一線を画す。良貨は悪貨を駆逐する。
どこの企業よりも経営コストを安くし、経営の組織それ自体が新しい概念である「環境プラン2」の経営システムとなっている。これは新しく現下の緊急の経営課題に対するぼくたちの考えでもある。
一般企業の、いわゆるサービス残業は出来高制の実績主義に転化し、自分にとって超過労働時間は、すべて自分の所得に結びつく。
こうして今こそ目指していくのは、組織をさらに拡大してこそ、自分の求める(個人による労働時間の個人的規定、働く労働時間の自由)快適な労働時間へ本局と子局は相互にめぐり合う。出来高制による組織の拡大こそ、1カ月の総労働時間を標準化することができるだろう。
本局はこうして編集者への最大のサービスをつくり出したいと思っている。
サービスとは営業と読め
eサービス(営業)を新しく構造化したい。
営業効果とは、リピーターの連鎖による好循環の創出である。
仕事が忙しい、それを更に生み出す。全員納期まで平均3日〜6日以上、作業を抱えて走っている。
これには好循環の連鎖(アメーバ営業)が必要である。
サービスはこれまでのように続けて行い、特にインターネットによる営業窓口の構造化、システム化をしたい。顧客窓口(管理)別にし、編集者にとって便利で、いつでもどこでも安心して手軽にBOX(窓口)にアップロードしていただく。
いっそうのデジタル化、ソフト化=サービス化として構築し、統合し、営業の新しい時代(デジタル時代)をつくり出す。サービスとは顧客からカネをとることではなく、営業として考え、構造化、システム化、サービス化することである。
営業基盤をシステム化 高度化して形成する。営業とサービスは別個のものではなく「一体化」と考える。
旧来からのソクハイ便による巡回はこれまでどおり続けます。
個人情報保護法の施策の推進は、ウェブオフィスとの連携によって行われている。本局の電話受付24時間体制に対する対応の研究も必要だ。編集者は電話の声を聞いて、電話のこちら側を見ている。電子メールの受信は24時間体制である。特に編集者と本局とのコミュニケーションは電話やFAX、電子メールなどをご活用ください。デジタルメールはウェブへの転写が容易で、そのまま編集者の声をスタッフに伝えることができます。
これらお客様の情報は、ウェブ「営業情報」に管理・整理されて、仕事の情報がみなさんにお知らせされている。毎日の仕事の納期管理が行われている。
本局では出版社のバックオフィスとして更にパートナーシップを生み出し、編集者の影のオフィスとしての構想をなんとか実現したい。サービスの「見える化」に力を入れていく。
政府の構想はカネがとれるサービスの実現であり、その立脚点は、権力によって法律をつくる「官製サービス」の概念であり、この考え方は、民間企業の努力によってのみ可能な営業と切り離されたサービスという考えで、好循環を生み出すことはできないだろう。
政府の発言は、企業社会へ影響を与える。デフレ経済から脱却を目指してきたが、生産者の立場にあえて「苦悩」を持ち込み、消費者である「家庭の目線」を重視しよう。企業間格差をさらに生み出すには、リストラ前の人員(約120名)への回復であり、スタッフの増強で対応していかねばならない。
サービスを営業と読むことにより、結果として売上が上がる、嫌いな言葉だが、儲かる営業のシステムづくりに結びつく。営業とは具体的な付加されるサービスであり、サービスが営業なのだ。営業がサービスを生み出す。生き生きとした個性を出そう。サービス営業として感じる「見える化」を推進しよう。
編集者の利便性を強化して、いつでもどこでもインターネットとつながっていて、仕事の窓口をバックオフィス感覚で使ってもらいたいと思っている。
品質を高め、納期を早めて、それが編集者にとって最大のサービスになると思う。
山形の電話の営業窓口は宝の山となっている。もちろん電子メールも宝の山である。編集者の「ひとこと」を工夫して新しいサービスを生み出そう。TOPへの報告や、毎日のチェックが生命線である。お客様の声を0120でやっているようでは、下の下だ。宝の山を失っている。徹底的に差別化しよう。
全員がこの「気づき」の敏感なアンテナになろう。
「一点突破の全面展開」はアメーバ営業から生まれる。設立10年以上は倍々で成長してきた。それは権力や資本の意地悪じいさんからは生まれない。花咲じいさんの論理から生まれる。「夫婦間の愛情・恋愛感」を良心にもとづく測定された判断を基本として、それを見本としてパートナーシップは前進する。
ぼくたちは全員自宅で仕事をしているが、編集者に対して「会社のビジネス感覚」ではなくて、「家庭での普通の感覚」で営業とサービスを考え、「一体化」していく。
社内で20年前に言っていた「当たり前」のことがいまなぜ「新しい」のか?
企業社会はいま「当たり前」のことが遠くの彼方にいってしまった。
この感覚をいまに戻すことはできない。一線を画すということは、こういうことだ。
安い経営コストで、普通で、当たり前で、家庭の感覚でビジネスと向き合おう。
「ビジネスで人が変わる」会社が多い。ここから徹底的に差別化し、区別し、差異、相違をつくろう。ぼくたちのブランドイメージを育てよう。
より質の高い安心のサービスをつくり、安心を営業しよう。
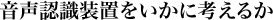
本局では、今後の動きとして良質な書籍のもつ国語力、表現力が問われ、日本語書籍の未来をつくっていくと予測しています。良質な書籍制作へと回帰するのではないかと思っています。
この点に留意し、みなさんにおいては毎日読む雑誌・新聞記事から、文芸欄や政治や経済の欄においてもどのような日本語の表現法を使われているか、記事を読むのもいいですが、新聞社の新聞記事のニュースがどのような表現法へと流れをつくっているか、こうした視点から新聞から学んでいただきたいと思っています。
表記法や表現法が変わっています。
インターネットでのブログなどへもこうした時流の流れに敏感となるでしょう。
トランスクライバーとして、新聞を見ながら、読むというよりも表現法と「表現力」に注意しながら、職業トランスクライバーとして学んでいく素材が身近にあります。
「閉じ 開らき」などに注意し、原稿の質を高めてください。
さて、政府の「イノベーション25」の政策の中に音声認識装置の技術開発が目録にあります。
ことばとしてではなく、それは表現をもったことばとしてではなく、ただ、活字を並べただけの音声認識装置の完成をもって開発技術者は、満足すると思います。
ぼくたちの仕事において録音の音質は不明瞭で、不明瞭であってもトランスクライバーはなんとか認識(D・I=ディクテーテッド・アンデンティティ)して原稿をつくっています。
音声認識装置は癇癪(フリーズ)を起こすこともなく、一過性で高校生のように「ストレス」なんかにならないように動くように設計されると思いますが、トランスクライバーのように何度も聴き込み、繰り返して聴き込み、D・Iを獲得する「良心」「忍耐」と「気長さ」をもっているかどうか? デットラインを前にして仕上がり時間に間に合うだろうか? 校正しなくてもいいだろうか?
これまでの納期時間に対して後工程があり、労働生産性を低下させる要因となれば、「イノベーション25」は失敗する。国会の常識と民間の常識には巨大な常識の相違がある。労働生産性の大差だ。校正の量によっては企業の成長は失われるだろう。もちろん納期破りの常習になる。
出版社への納品原稿は、活字だけの並べた原稿からなぜメディアミックス&ソフトノミックス/に仕事がきているのか、ぼくたちの心構えとして今から訓練していかなければならない点は、「目で聴いて、耳で見る」という禅的な発想です。
談話の臨場感をテキストで再現することができるだろうか?
原稿をより立体的にするためには、「耳で見る」というトランスクライビィングの技術が必要で、どんな姿勢か、どんな態度でお話しされているのかも――それを再現できるかどうか? インタビューイーにもっと関心をもとう。「リクルート情報」はここを見ている。
「編集者の目」を想像すらできない技術者の都合に案内する技術設計が予想される。
佐藤はよく文学的な対談においては、原稿を読んでいると、その臨場感が原稿から伝わってきて、対談者が自分の前に座って「話している」かのような情感の放射線を浴びる原稿(トランスクリプション)に出会ったことがあります。
小説の作品の世界に入っていく心理描写に出会う時と同じです。対談の雰囲気や香りがテキスト世界で再現され溢れているのです。
芥川賞を受賞した青山七恵さんは、
「とるにたりないものとして流されていってしまう感情を、丁寧に拾って言葉にしていくのは、なかなか根気のいる作業だ。砂粒ほどの小さな感情を選り分け、慎重に重ねあげて、文ができ、その文がまた重なりあって、一つの小説が生まれる。そうやって集まった言葉たちが、小説を読んでくれた人たちの心の中に、またさらさらとほどけていけばいいなと思う。」(読売新聞「芥川賞を受賞して」平成19年1月30日)と言っています。
ことばの一音の生命(いのち)を大切にしながら、その重みを「丁寧に拾って」テキストとして成仏してもらうのがトランスクライバーの仕事なのである。この「仏」(ほとけ)は、永遠のことばの海に生きる。
「耳から見た」模様をカッコ書きして、トランスクリプションの行間を立体的にしていくことも、これからぼくたちの挑戦になります。
日本語には同音異義語が多いので、人間に代わる知性(表現力)をつくろうというのですから。
そして、また日本語は英語に比べて含蓄のあることばが多いので、その意味深長さを、音声認識ロボットでつくろうというのですから、宇宙技術よりも難しいと思っています。
現代の科学は弁証法的に知の分裂と細分化の歴史であり、概念とその表記も細分化の中にある。「知の分裂」という論理構造の中でフリーズドするだろう。音声認識装置は希望や思いでは実現できない。
コーパス(corpus:collection of written or spoken texts)を集積するだけでは実現は不可能だ。
テレビ放送やラジオ放送、インターネット放送(ポッドキャスティング)などのアナウンス原稿と求められるものが新聞記事や雑誌記事原稿とは本質的に異なる。
「聞いて」知る原稿と「表現される」原稿とは違う。談話と表記の違いでもある。
直接「聞く」原稿と筆致で表現される原稿には「五感に与える力」と「読ませる力」(表現力)が違う。テレビの前の視聴者と書を前にする読者との違いがある。
テレビなどで映像と音声、そしてテロップなどで「段落改行」や「句読点」の見えないアナウンス(目と耳=光(照明)と音 息の切れ目と意味の切れ目)と、たとえば新聞記事(目)との分化は、理解を促すために工夫もされている。言文一致の大衆化でもある。この件については、また別項で述べる機会もあると思う。
表現力(法)を工夫しなければならない。
ぼくたちは、放送ジャーナリズムや映画、テレビ番組へもメディアとして関心をもっている。
パッケージや音声ファイルから耳にする著者(ディクテーター)の肉声――作家やアーティスト(クリエーター)や芸能タレント、音楽家や芸術家のアクセント、イントネーション、リズム、ポーズ、スタイル、かおり、エナンシエーション(語調)を伝えるには、どのような原稿にしていくか、テレビと記事の違いがここにある。
トランスクリプションの真価が問われる。
「ことばに力」を求めてテキストはどんな「衣装」をまとうことができるだろうか。
「転写」の立脚点から飛翔し、「転換」へといかに合致へ向かうにはどうしたらよいかを工夫しよう。
ロボットは耳から「見る」ことができるのでしょうか。
文節をどうつくるか、音節を文節にしているわけですが、どこに句読点をおくか、そこに立体的な原稿づくりの妙があります。テレビと書の相違でもある。
耳で聞いて、濾過して目で原稿を読むのですが、このとき見るは読むと「同意語」です。認識は目で聴いてこそ深みが出てきます。
そんな原稿づくりへの心構えを今からもってください。
音声認識の土台であるフォネティサイズ(phonet'icize ディクテの仕事場用語集参照)の原理を弁証法的に証明した。(『ディクテーティング研究』第6号1995年4月 ――ディクテーション学、トランスクライビィングの理論はマルチメディアへの独創的技術を生み出すかもしれない――31頁)これが音声認識装置の原理でもある。
自然日本語のフォネティサイズの自然様態には男女の違いや年齢、職業、地方の人などで多様な発話の不明瞭感がある。はたして装置の原理として成立するのか。
そして、自然科学、社会科学的談話やビジネスと人文・芸術の談話には「渡れない橋」がある。原稿づくりの違いがある。
ここでトランスクライバーのトランスクライビィングと音声認識装置のあいだを考える。
トランスクライバーは毎日のトランスクライビィングをとおして、電子音声としての電子談話を聴いています。
電子音声としての談話は、放送局仕様のCD音質の明瞭性(スタジオ録音)と比較して、実用の録音品質は何かについて話している聞こえる、聞こえるのレベルでの音質が普通です。ふだんテレビやラジオで聞く音質とは異なって60%以上はなんとか「聞こえる、聞こえる」の自然録音の範囲内の不明瞭感です。テレビの音声は「注意」なしに耳に入ってくるが、聴き込まなければ頭に入ってこない。
トランスクライバーは編集者の取材現場で傍聴(スタンバイ)していないので、実感としての明瞭感は「聞こえる、聞こえる」の範囲内で、スタジオで録るCD音質の澄み切った明瞭感とは異なっています。
ぼくたちはその実用範囲内で原稿づくりに挑戦している。
音声認識装置は1回きりの談話の再生による識音能力をもって表記能力で「実行」するのか、その箇所を再々聴き込んで「実行」してトランスクリプションの精度を高めることができるのか。トランスクライバーはそれを毎日繰り返している。ぼくたちのように文脈(コンテキスト)から識字能力(ディクテ)をもっているのか、そしてそれは、インターネットではヒットしない表記も含めて。
そこで音声認識装置は、検索するまでの「あたり」をつけて正式概念表記に至る音声認識能力をもっているのかどうか。
ぼくたちは「繰り返し、繰り返し」聴き込み、録音の「現実=明瞭性」から「あたり」の認識に至る心象を強めて、ことばの表記を獲得しディクテしていくが、音声認識装置の「思考構造」は哲学的にどうなっているのか、文学的な「思考回路」から発することばとの間にニュアンスなど表現の違いもある。
日本語能力と知識能力を必要とするが、反対に機械的認識ができうる低レベルな日本語会話の談話のみなのか。
音声認識装置としてのロボットは繰り返し、繰り返し聴き込んでいかなければ認識が獲得できない同等の録音レベルでも処理できるのか。繰り返し聴き込んでも乱暴な性能の「ディクテ」しかできないのか?
音声認識装置は、音質(録音)の入り口が劣悪でも音声認識が可能になるのか?
そうではなくて音声認識装置とは、現実の人間の談話にただ冷酷に機械的に反応していくだけであると思う。
それでは音声認識装置が実用化されたとはいえない。「推測」と「認識」とは異なる。音声認識装置は未来と過去のこの距離を測定できるのか?「認識」へと着地していく飛翔が可能か?
音声認識としてのロボットは、いつもやさしく、怒ることなく繰り返し超・超・光高速の演算能力で、何度も気長に不明瞭(ノイズ)な音素を求めて語(ことば)を獲得できるのか。
ぼくたちの文脈(コンテキスト)から心象(物象)する思考過程をロボットが代位できるのか、人間にかわって人間の思考過程を、その心象過程を再現できるのか?
そして音声認識装置は人間の精神を模倣することができるのか?
「録音の明瞭感」に注文をつけている間は、おもちゃにしかすぎない。実用的ではないのだ。実用的とは、労働生産性に貢献できる道具の実現である。そして、編集者が第一稿として仕上がり原稿に使える「価値」があるのか? 「財との交換」は成立するのか?
たとえば高校生、プロガーレベルの「談話」を音声認識装置を使って表記文字に転換することはさほど難しくないと思われる。しかし、編集者は「カネを出す」だけの価値があると思うだろうか?
ぼくたちの毎日の仕事を考えてみると、「おもちゃごっこ」をしているように思える。
そして、弁証法的に考えてみると、音素が語を形成する、ことばを認識する、つまりつくる、表記する原理は科学的にも技術的にも普遍である。ぼくたちは音素と格闘しているのだ。
「渾然一体」となった塊として設計技術者が考える哲学的不全からコーパスの集積に技術的土台を求め(活路)ては失敗の原因となるだろう。不全とは十全な働き(機能)に対する機能(働き)不全である。国家プロジェクトとして音声認識装置は人間の思考過程を模倣できるだろうか。技術開発(工夫)では実現できない。ことばは人間の、民族の精神構造と深く関わっている。人間の認識構造を道具が代位できるのか? 「転倒」すると機械が「小説」をつくる。異常な精神世界に突入する。道具の思想性と身体言語(生命意識)の衝突である。
現実は、この音素がノイズで不明瞭なのだ。フォネティサイズの原理が成立しない。それとも高校生の書き取り(コーパス)の発想か?
いずれにせよマッサージ師に頼るか、マッサージ機に頼るか、プロの肩こりは満足しない。カネを払えないのである。
同音異義語が多い日本語にとって、音声認識装置が漢字の書き取り(コーパス)に博士号をとったとしても、人間の認識と概念の特有性を獲得することはできないだろう。
音声学的には自然音声言語のコーパスの様態は多様で重層的なのだ。そのうえ、録音の品質が加わる。
これはメディアミックス&ソフトノミックス/の公式見解である。
(第一稿は小社web「営業情報」2007年4月26日、27日、28日の3回ディクテーションで投稿され、まとめて加筆されました)
■杉並区NPO法人 シニア総合研究協会との協働による「自宅でできる録音物再生談話筆記講座」の説明会が、去る平成19年4月21日(土)杉並区荻窪の「ゆうゆう荻窪東館」で行われましたが、本講座は中止しました。
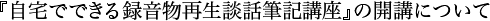
すでに発表いたしました杉並区のNPO法人 シニア総合研究協会との協働による『自宅でできる録音物再生談話筆記講座』の説明会が、杉並区荻窪の「ゆうゆう荻窪東館」で平成19年4月21日(土曜日)午後6時〜7時、説明会が行われます。
『広報すぎなみ』の4月1日号に掲載してお知らせします。
説明会は無料で、講座は全5回で参加費5,000円 参加者の決定は抽選。(コンピュータ保有者のみ)
参加者は10名前後を予定しています。
説明会 平成19年4月21日(土曜日)午後6時〜7時
講座開始は平成19年5月26日開講で、講座は全5回で参加費5,000円
隔週土曜日の18時〜20時開講で、週1回5週間を予定しています。
説明会では、「ディクテの仕事場」から見た出版社編集記者の取材と取材記事がどのようにつくられていくか、をテーマに、トランスクライバーが携わる取材の第一稿、その原稿のつくり方など説明し、トランスクライバーがいかにマスコミ出版業界に携わって原稿(トランスクリプション=録音物再生原稿)をつくっているかに焦点を合わせて、このお仕事の楽しさや原稿の品質や納期などをいかに厳格に守るか、などを中心にお話しいたします。
小社では、この講座の参加者の中から優秀な人をトランスクライバーとして採用する予定です。全員採用を目的として開講されます。
第1回 談話筆記の歴史(わが国出版業界における独得の本づくりの革命)
第2回 談話筆記の理論
第3回 談話筆記の実践とその理論的背景
第4回 談話筆記の技術(1)(談話筆記原稿を実際につくってみよう。デジタルディクテ・マシンの操作・貸し出し)
第5回 談話筆記の技術(2)(電子音声ファイル、コンピュータ操作の進め方)
以上より構成したいと思っています。
配布資料(テキスト)
『ディクテーティング研究』創刊号
『ディクテーティング研究』第2号
『ディクテーティング研究』第3号
『ディクテーティング研究』第4号
『ディクテーティング研究』第6号
『ディクテーティング研究』第8号
『数字表記基準』A基準、B基準
『M&Sディクテ作業基準』「文化庁公用文の書き表し方の基準」送り仮名用例集以外の使い方
『国語表現法』佐藤喜代治編(朝倉書店)
『文章の書き方』成川豊彦著(PHP研究所)
『インタビュー術!』永江 朗著(講談社現代新書)
説明会では小社が携わった店頭出版物をとおしてマスコミ出版業界でトランスクライバーはどんな仕事をしているか、例として店頭出版物を例示します。
なお、出版社へ納品されたトランスクリプション(録音再生原稿)は出版社の許可を受けておりませんので公開することはできません。
各種出版物をとおしてトランスクライバーとしてどのような知識や能力を必要とするかが説明されます。
■例示出版刊行物
【新聞】
読売新聞東京本社 『読売新聞』水曜夕刊「ALL ABOUT」2006年6月7日〜2007年3月までの水曜夕刊から5部ぐらいをお持ちしたいと思っています。
読売新聞東京本社 広告局 読売ADリポート『ojo』(オッホ)2006年6月,7月・8月,9月号
【月刊誌】
PHP研究所発行 月刊誌『PHP』(小冊子)平成19年1月号
PHP研究所発行 総合月刊誌『Voice』平成19年1月号〜4月号
中央公論新社発行 総合月刊誌『中央公論』平成19年4月号
中央公論新社発行 月刊誌『婦人公論』平成19年2/7,2/22,3/22の各号
産経新聞社発行 総合月刊誌『正論』平成19年2月号〜4月号
プレジデント社発行 隔週誌『プレジデント』2007年1.29,2.12,3.5,3.19
プレジデント社発行 月刊誌『プレジデントファミリー』2007年3月号,4月号
集英社インターナショナル 月刊誌『PLAYBOY』2007年3月号
【バックナンバー】
月刊誌『PLAYBOY』1997年2月号,1998年4月号,1998年11月号,1999年5月号,1999年7月号,2000年4月号(各号の日本美女図鑑)
幻冬舎 月刊誌『GOETHE』[ゲーテ]平成19年4月号
扶桑社 月刊誌『en-taxi』2007年VOL.16
角川書店 月刊誌『野性時代』2007年3月号
【週刊誌】
扶桑社 週刊 『SPA!』2007年1月16日号,1月30日号,3月13日号
【書籍】
幻冬舎 幻冬舎新書 手嶋龍一+佐藤 優著『インテリジェンス武器なき戦争』
光文社 光文社ペーパーバックス 藤井厳喜著『総下流時代 なぜワーキングプアが増えるのか?』
日本経済新聞出版社 野中郁次郎+勝見 明著『イノベーションの作法』
以上の店頭出版物に目をとおしていただき、お仕事(トランスクライビング transcribing)の概要を理解されて、みなさんの参加をお待ちいたしております。
この夏6月頃、小社ではスタッフの採用を目的とした「談話筆記講座」を東京・杉並区のNPO法人 シニア総合研究協会との協働で、ゆうゆう荻窪東館(荻窪東4-23-12)で開催を予定しています。参加を希望されるみなさんのために──。
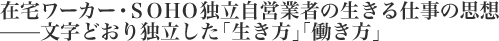
1.「生き方」は楽ではないが快適だ
現実の社会では生き方や働き方は二つに分けられる。
分からなくはないが、「食うために働く」道と、現実の社会でモノをつくりモノの価値を生み出して、それを交換(売買)して財貨を得て生きる生き方と二つある。
生きていくことである人間の生命活動の交換と協働にはこの二つの生き方を選択しなければならない。
ぼくたちは20世紀末に「知」を形にして交換する組織の装置を生み出した。
それは情報社会の到来を期待していた。
人間の歴史、人間の生命活動の交換と協働は物々交換や商品生産、そして手工業化や工業化をへて生きてきた。
小学生の国語、『かさご地蔵』は生命活動の交換と協働を学ぶことができる。
産業社会では「食うために働く」賃金労働者の生き方が理解できる。
この生き方は労賃が高いほどいい。それは独立自営業者との生き方とは違う。
ぼくたちは自分の生き方をマスコミ出版業界に求めようと思った。マスコミでぼくたちにできる「知」を形にする仕事に何があるかを考えた。
徒弟や奉公人、使用人も江戸時代まで続いた。賃金労働者の始まりであった。
時代は現代になるが、1990年を迎えた頃、ワードプロセッサーに従事して働く生き方が生まれた。わが国産業社会は情報化社会へと移ろうとしていた。在宅ワークを通して経済活動に従事する在宅ワーカーの誕生だった。
ぼくたちは更に進化し、SOHO独立自営業者として自らの道を開拓してきた。
ぼくたちは固有の知識と技術を所有し、情報社会に参画する知識労働者として自らの存在を「事業」にまで育てた。
知識なくして生産しえない情報生産物を生み出そうとしていた。
会社(企業)に雇われていた時と比較してこの仕事は楽な仕事でもなく、労働集約的で時間から時間まで労働力を提供していた時よりも自己管理が難しいと感じた。
そして、本能的に自分よりも大きな船に乗って今よりも楽に仕事をして暮らしたいと思った。ホームオフィス(自宅)で待機していると仕事がどんどん入る。報酬料金は一人で営業して仕事をする時よりも安い。どちらがいいか? 営業の時間やコストもかかる。しっかりと報酬に反映することができるか。いろいろと天秤にかける。またこれまでの職場への通勤や「時間」のコストと比較する。仕事が継続的にあればいいがそうはいかない。
「時は金なり」だ。
マスコミ出版業界にその活路を見出そうと、ぼくたちの生命活動は自分たちの精神の活動を外化して原稿(マティール)に価値を付加した。マスコミ出版業界のマーケットで組織の装置を通してマスコミ各社と自分たちのつくった原稿と交換している。
この生産の仕組みは「提供された素材を加工生産」して交換している。
情報産業社会へ参画していくにはマスコミ出版業界へ進出することだった。
政府は一般企業の情報をサービスする「在宅ワークガイドライン」をもうけ、いわゆる「下請法」を制定し、在宅ワーカーを賃金労働者化した。
ぼくたちSOHO独立自営業者はマスコミ出版業界で原稿料・印税をいただき、それはメディアミックス&ソフトノミックス/の目指す「組織の装置」を自分たちの仕事の道具として、原稿料・印税が「給料」のようにいただける夢を描いた。
ぼくたちはいま、一般企業を顧客とする人たちと自らを区別しなければならない。新しい時代を迎えた意識がある。
それは社会が「変わり」、この道を強い意思をもって「事業化」していくリーダーであることを意識する。
現下の情報化社会でマスコミ出版業界やインターネットを通した公開原稿の加工生産に従事するようになった。
「従事するようになった」と言いました。一般的には「賃金労働者」が「生産に従事する」という表現と同じように理解されがちですが、賃金労働者は一般企業において「生産の3要素」のひとつにしかすぎず、生産しているのは会社であり、会社の資本拠出者は株主です。生産しているとは表現できません。生産に従事しているという日本語表現法を使っています。
原稿料・印税の一部としていただくこの「仕組み」には、いわゆる下請法は適用されない。企業社会一般はマスコミ業界と区別されます。マスコミには放送、出版、広告の業界があります。
一般企業においては、いわゆる「下請法」が適用され、マスコミ業界ではこの「下請法」は適用されません。
2、3の出版社様においては、末日〆翌月にはお振込みをいただいています。それは例外的な扱いだと思います。また、60日以内にもお支払いを受けています。
メディアミックス&ソフトノミックス/の創立は、1988年家庭にいる高学歴の潜在女性労働力をどのように吸収し組織化していくか、そこに佐藤は着目しました。
出産、育児、そして介護を抱え、こうした高学歴女性を仕事を通じて社会へ参加できる仕組みをつくろうと思いました。メディアミックス&ソフトノミックス/の設立理念は出産、育児、介護を抱えた現実をみんなで支え、助け合う会社理念を前提として、こんにちに到っています。
そして、マスコミ出版業界への進出とその事業化が事業の夢でした。
みなさんにおいてどのような認識の基にあったか、それを問いたいと思います。
在宅ワークから出発し、在宅ワーカーとSOHO独立自営業者の二面性を持っていることを税務署に主張しました。
いま少子高齢化社会を迎え、出産や子育て、そして介護をしながら「仕事」をしている現実を持っています。
しかし、事業の現実と事業目的(事業内容)はみなさんご承知のとおりです。
所得税の源泉徴収制度において、「第240条第1項第1号の報酬・料金」について適用される業務を行っています。マスコミ業界に適用されるものですが、翻訳の料金、書籍・雑誌等の校正の料金、速記料が規定されています。
ぼくたちの業務と同じようにみなされているのは、書籍・新聞・雑誌などの原稿料、レコード・テープなどの吹き込み料、デザイン料(工業デザイン・クラフトデザイン、グラフィックデザイン・パッケージデザイン、広告デザイン、インテリアデザイン・ディスプレイ、衣装デザイン)、生け花、茶の湯、舞踊、囲碁、将棋、編み物、ペン字、着付、料理、ダンス、カラオケ、民謡、語学、短歌、俳句等の教授・指導料、原画、写真、弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、映画、演劇、音楽、音曲、落語、漫談、歌唱、奇術、漫才、等々、ラジオ放送局やテレビ放送局へ外部から出演、演出、企画される方々、キャバレー、ナイトクラブ、バーのホステス、芸者、舞妓さんの方々も、みなさんと同じように所得の10%を源泉徴収される対象者です。
メディアミックス&ソフトノミックス/の組織の装置と、放送業界を中心に事業化した吉本興業と同じような仕組みになっています。その他、放送業界には芸能プロダクション、出版業界にはフリーランス、編集プロダクション、広告業界には会社から独立されたデザイナー、コピーライターやカメラマンのプロダクションなど、その文化は重層的といってもいいでしょう。
一般企業を主に対象としていないのは、みなさんもご存知のことと思います。
しかし、佐藤は身の丈大で分相応の実力・能力、平等主義のもとに出産・育児・介護を抱えた高学歴女性を組織することから出発しました。
この現実とサーカマスタンス(周囲の情況)は、事業の創成期と初期社会的インフラの形成と成長と共に情報化社会のこんにちを迎えています。
マスコミ出版業界においてコンテンツの加工生産に携わり、出版(書籍・雑誌)、インターネットメディアとして公開コンテンツ、マスコミ社会に訴求するリクルート情報の公開情報等、企業内教育、社会教育などへも設立時の会社定款に盛りました。
出版業界における月刊誌の取材は平均何カ月前から始まるでしょう。しかも各号は公開発行月の前月までには発行される月刊誌もあります。月刊誌は再販制度にもとづき、書籍制作より早くなっていますが、出版社への入金も早いようです。
しかし、書籍の制作は平均6カ月から、第1回取材から平均10時間ぐらいの取材を何カ月にわたって行われているでしょうか。
本局では初期キャスティングで担当者が同じ取材を担当しました。そして、入金された書籍から担当者にお支払いしていた時期もありました。みなさんにとって入金と未払い(未入金)が混乱し、分からなくなることもありました。そして、出版社によってお支払いが異なるため、お支払いの平等を確保することが難しくなりました。
第一次リストラ、そして第二次リストラ、第二次リストラは苦悩の断行でした。不況に強いといわれた出版業界の神話が崩れ始めました。
そして、ぼくたちはマスコミ出版業界と共に生きる道をみんなで支え助け合いました。消費税は当時外税計算のものもありましたが、内税化しさらに価格を下げました。
個人消費の低迷が今も続いています。出版社と一緒に戦う意思を示しました。
それは巨大で偉大な「女の力」を発揮しました。
2.「働き方」が変わる──ソフトノミックス(ソフト化経済)の技術的インフラの形成
ぼくたちは自宅をオフィスにして仕事をしている。
2007年ウェブ2.0はデジタル経済化、デジタルソフト化がいっきにやってきた。
サービス産業は製造業を超える産業となりました。多様なサービスが生まれ、経済のサービス化は進展しました。本格的なソフトノミックス社会が到来しました。
ソフトノミックスを特徴づける経済の要素はデジタル経済化、ソフト化、サービス化である。
ぼくたちの生命活動は多様な性格を持っているが、経済活動において自分たちの精神の活動を外化して形(原稿)にしている。マスコミ出版業界のマーケットで組織の装置を通して自分たちのつくった原稿と交換している。
紙へ転換を前提とした出版社での電子編集へ向けた電子コンテンツの制作に焦点を合わせる。ぼくたちはマスコミのメディア(インターネットメディア)に従事する知識労働者として第一(初)稿の電子入稿(音声ファイル)が電子流通にのるイノベーション(技術革新)の新しい波を受けている。それは働き方が変わる。編集者は取材から帰り音声ファイルをインターネットでアツプロードし、直接それをトランスクライバーがインターネットからダウンロードしてすばやくディクテの準備が始まる。
目に見えたもの(カセットテープ)から目に見えない音声ファイルへと入稿が変わった。各メディアのパッケージをコンピュータ用音声ファイルへ転換して、すべての業務プロセスをコンピュータの働き(機能)に統合する。ぼくたちの働き方はコンピュータのソフトの働きで制御できるようになった。「モノラルな仕事場」から「デジタルな仕事場」へ変わる。モノラルディクテマシンはデジタルディクテマシンへ代替し、コストは7分の1に削減できた。
もちろんカセットテープやMDなどの物流は音声ファイルへと変わっていく。それはデジタル経済化であり、デジタルソフト化である。流通はインターネットへ変わった。
ソフトノミックス実現のためにデジタル経済化とデジタルソフト化へのインフラを形成しなければならない。イノベーションによるコストの大幅な削減である。二往復の宅配便コストが削減できる。こうしてe労働生産性は革命的に変化した。
新技術ソフトと経営の新結合は経営コストのいっそうの削減を可能にしている。ぼくたちの「ビジネスモデル」を革新し、進化できる。イノベーションはデジタル経済化を可能にした。
ぼくたちのこの課題は高度なユニバーサルデザインの物象のもとに、高度化したユニバーサルな技術設計を行い、デジタル経済化して、ぼくたちの仕事場に「使いやすさ」と「快適さ」を求める。
報酬料金の値上げが視界に入った。それにはクライアント様へのよりよいサービスの実現と対話が必要である。
これまでの「古い仕事」をデジタル概念(ウェブ2.0)で「新しい仕事」へと革新していく。それは仕事のことばも働き方も変わる。テープトランスクリプションの制作からヴォイストランスクリプションの制作へと本格的に移行する。
テープやMDによる入稿から音声ファイルでの入稿へ変わり仕事の現場がデジタルへ変わる。
「ディクテの仕事場」へ「ビジネスモデル」の進化を可能にする業務プロセスへのイノベーションの波が押し寄せてきた。
日本版新SOX法=内部統制による「新しい秩序」「新しいルール」を確立しよう。
技術設計の思想は「入ったものを出し」「出したものを入れる」目的から到着までのプロセスと帰りを延長概念の中で構築しなければならない。
延長は時間の概念でもある。それはつながっていく思想だ。子孫(新しいスタッフの採用)の思想や男と女の働き(機能)を永続の概念へ転化して独自の経営(新しいマネジメント)を生み出していこう。
ソフトは独立したモジュール(module)で交換を可能にし、設計への最新の合理性(普遍性)を確保する。合理性は常に新しい技術で革新していかねばならない。いつでも社会のイノベーションを受ける革新であり、技術設計でなければならない。
ユニバーサルな技術設計による操作(operation)の「使いやすさ」と「快適さ」を作り出していこう。それは技術者の自分の設計都合に案内するプロダクトアウト(生産者志向)が多い。顧客第一(トランスクライバー)の立場に立ち、論理的(シンプル)な「使いやすさ」を求めよう。
ぼくたちの「ディクテの仕事場」の生産手段=生産技術のデジタル化と高度化を進める。トランスクリプションの制作技術の改革に取り組む。サーカマスタンスはイノベーションの推進に取り組んでいかねばならない。それはデジタルディクテマシン稼動へのIT技術のエンジンニアリングによる革新でもある。
カセットテープやMDの音源をコンピュータに取り込む技術でもある。
2倍速、3倍速録音、150分カセットテープなどの音源をコンピュータへ取り込むことである。
また、課題としてICレコーダーの標準操作法の規格化への期待もある。
ぼくたちSOHO独立自営業者は対応へのそのテクノロジーの確立が求められている。
テクノロジーの形成と確立には普遍性(本質=核技術)を確立し、論理的な「手段」の「組み合わせ」=新結合の新しいテクノロジーを開発しなければならない。これが「ディクテの仕事場」のデジタル化、ソフト化、高度化であり、知識資本の優位性を追求していく。
それは知識資本とテクノロジーの新たな結合でもある。
3.模倣と物象化
わが国における出版業界からの入稿は、記録手段として速記記号→テープレコーダー→ICレコーダー(音声ファイル)へと移り、並存しているが作業はコンピュータへ全面的に統合される時代を迎えました。
いま生産工程の工夫・改善・革新へ向けてその実現に焦点を合わせる。
佐藤はしつこいぐらい「働き方が変わる」と言いました。
イノベーションによる新技術の適用によって生産コストを削減し、納期時間を短縮するため、デジタルソフトの導入によってコンピュータへ統合される。
実践されている「模範モデル」から学び、このコストの削減はこの経済様態の中で競争力を増強することにつながる。それは利益幅の増大に貢献されている。
しかし、出版社からのデフレ圧力は根強い。スタッフの努力に報いようと思っても料金の下げ止まりは感じない。技術経営力はデフレ圧力に解消されるかもしれない。
しかし、いま取り組まねばならない。
生産手段=生産技術をデジタル化するにあたり、本来日本人はどのように考え、話し始めるか、インターナショナルな論理はインターナショナルな製品をつくる。
日常の自然言語によって動作の入り口から動作の順序を、自然言語の表現によって時系列的にわかりやすくシンプルに説明できる順序は、日常会話の順序の物象化が観念の土台とならねばならない。
もちろん「日本語文章の書き方」が簡潔で上手だといわれるように動作を表現し、「行為の連続」(インストラクション=命令)が理解しやすいことである。
誰にでもわかる動作が順序だっていることが大事だと思う。
しかし、現実にはプロダクトアウト(生産者志向)が強く、人間が機械にあわせていくというチャプリン以来の工業化社会を経てきた。あえていえば、モノづくりへの苦悩が見えない。
人間の観念の土台である物象化に基づいて、誰にでもわかりやすく、簡潔な表現による動作でなければならないだろう。
それは「理解しやすいこと」と「間違いやすいこと」を発見する誰にでも適用できるマニュアルが必要である。
はじめに購入ソフトと関係なく日常の自然の話しことばで考え、上記の問題点は改善工夫ができるか、これらの原因を除去する丁寧な問題解決法を発見して、仕事の教え方に効果をもつことが必要である。
音の取り込みにあたり、動作の手順(operation)は工夫できるか?
自然の話しことばで考えたこれらの問題現象は、その複雑な動作の原因を除去できる改善の問題解決法が発見できるか。
先日、「わたしは息子の住民票をとりに」市役所の窓口へ出向いた。
住民票申込用紙の書式はどうあるべきか。
申込者の氏名、住所、そして息子の名前か?
息子の名前が先か、申込者の名前が後か。
日本語で考えるな! 英語で考えろ!
政府関係機関はどうなっているのか。自治体の書式はどうなっているのか。
旧来からの日本における教育の原点は、「読み、書き、ソロバン」の「書き」の側面からであったが、この側面から考えるのではなく、日常の「話しことば」の順序から考える180度の逆転の発想で考えてはどうだろうか。
にわとりが先か、たまごが先かは、いま暮らしている現実から出発しなければならない。生きているぼくたちの時代から現代という現実をみる。
「時間」に始まりもなければ終わりもない。キリスト教成立の「時間」という当時の今から出発している。何人も親から生まれる。
手前味噌な言い方かもしれないが、「180度の逆転の発想」とは第一義的な話しことばのディクテーション(談話筆記)の歴史をぼくたち日本人はもたない。
一般庶民は話しことばが生活の第一義的な側面をもっている。日常の暮らしの土台である。
「読み、書き、ソロバン」の教育は話しことばから教育しないで「書きことば」から教育する。
日本人の特有の日本人性が教育される。
工業化の歴史は「機械に人間は合わせてきた」「機械が人間に合わせる」時代の到来はいつになるだろう。モノづくりの発想は180度逆転の発想で設計されなければならないだろう。談話筆記の歴史をもたない日本人の思考のアキレス腱はここにある。
日常の現実的な暮らしでは、「話す、聞く、書く、読む」の順番だと、佐藤は言っているのである。
そして、技術設計のプロダクトアウト(生産者志向)からコンシューマーオリエンテッド(顧客第一)への発想の転換を進めなければならない。なぜ日本人にはできないのか?
日本人は工夫する力や改善する力があっても、この「読み、書き、ソロバン」のワナにはまりこんでいる。技術とは表に出てこないものである。むき出しに表に出ている。
ぼくたちはiPodの優越性がどこにあるかを学ぶ。
ぼくたちの談話筆記の手法は表には出てこないようになっている。そのために教育が行われている。表記法の確立とその模倣を通して教育している。
物象化は「話す、聞く、書く、読む」の基本を通して「模倣」し、また同化する。ここに教育の原点がある。教育とは模倣し、同化するものであるからだ。
日刊工業新聞 平成18年12月19日 こんな報道があった。
匠の技に磨き
NEC、モノづくり技能表彰
教材ビデオは門外不出
匠の技を伝承−。NECはハードウエアの現場技術者を対象に技能表彰を制度化した。モノづくりを担う現場技術者のモチベーションを高めると同時に、技能伝承を全体運動として推進する。かつてグループ会社ごとに行っていた技能認定を全社レベルで復活させ、匠の技に磨きをかける。
第1回の技能表彰はものづくり革新企画部がこのほど開催した社内イベントで発表。精密機械や設備技術、はんだ付け、化学などの分野から15人を表彰した。今回はグループ会社ごとの推薦に委ねたが「将来は全社共通の技能認定を体系化する」(ものづくり革新企画部)方針だ。
イベントでは匠の技にスポットを当てたビデオ映像を紹介した。撮影したのはNECで試作品のデザインを担当する大舘信広氏。カナダで開かれた「第1回国際ろうフェスティバルアート&映画祭」で大賞を受賞したほどの腕前で、才能を生かして匠の技の撮影に挑んだ。
上映された映像(ダイジェスト版)は受賞者が日々働く姿を1人1分間でテンポよく紹介。字幕に記された受賞者らのコメントは「マニュアル化できないノウハウは手取り足取り教える」、「覚えるまで教える。決して見放さないことが大切」、「私の技能のすべてを引き継いでもらいたい」など、ひとつ一つが奥深く、匠の世界が人と人の信頼関係で成り立っていることを示唆していた。
今後はモノづくりを担うグループ会社に75分間に及ぶオリジナル版を配布。技能伝承の教材の一つとして活用する計画だ。
ろう者である大舘氏が撮った映像は分かりやすく、的確に技能者の姿をとらえている。ただ技能内容は匠の技ゆえ公開は難しく、残念ながら門外不出の名作となる。
人間は「話す、聞く、書く、読む」に「見る、感じる、かぐ、味わう」などの五感で認識する。暮らしの基本、家族、社会・集団生活への同化模倣がはじまる。
ぼくたちの「職場生活」を通して現実の話しことばをマニュアルを媒介にして書きことばへと止揚(アイデンティティ)する。マニュアルに話しことばと書きことばの同等性を求める。自然発生的に移行(同化)するだろう。使う人にやさしい「マニュアル」ができるか。
模倣 もほう
Imitation(英・仏)。【原義】イメージということばと関係があり、原型や模範となるものがあって、そのあとをたどるという意味。【発展】イミテーションというと、模造品、にせ作を意味するように、模倣は元来、独創と反対のもので、価値のないものという考え方があった。しかし心理学者たちは、他人の行動を観察し、それに刺激されて類似した行動を行なうという、行動様式の再現が、子供が成長していく過程で必要であると、考えるようになる。子供は模倣によって、集団生活する方法を学び、所属する集団の規範への同調ができるようになり、社会化されていく。どのような場合に模倣が行なわれるかということについて、行動主義の心理学者は、条件反射の特性によってこれを説明しようとした。
それに対して精神分析派の心理学者は、模倣行動は、模範となる個体との同一化(アイデンティフィケイション)の欲求によって行なわれると解釈する。フロイトによると、その個人にとって特別な情緒的重要性をもつことのない相手は、たんに感情移入によって理解するにとどまるが、情緒的結びつきの強い相手には、同一化しようとする欲求が生まれ、模倣行動が行なわれる、という。フロイトは子供が同一化の欲求をもつ、最初の相手として父親をあげ、しかしその模倣しようとする行為が、性的なものであるとき、親からその模倣の衝動を抑圧されることによって、精神的障害がおこりうる可能性を指摘している。
しかし、模倣はたんに子供が社会化されていく過程において重要な意味をもつだけではない。流行・慣習・制度などいっさいの文化の根底にはなんらかの意味の模倣が存在する。G・タルドは「社会とは模倣である」といい、たんに文化現象だけではなく、社会そのものの本質が模倣だと考えた。すでにパスカルは、アリストテレスの、習慣とは自然のようなものである、という考えに対して、自然とは習慣のようなものだ、といっている。
この場合、習慣の本性が模倣にあると考えていいわけだが、フロイトの場合にもすでにそうなのだが、模倣が、親とか教師のことばによる教えではなく、具体的に形として見えている範例つまりイメージによって行なわれると考えていることに注目する必要がある。
つまり、模倣行為の根底には想像力が存在しているのである。流行とか慣習とか、あるいは人類の文化がこれまで維持され、新しくつくられてくるためには、民衆の共同の想像力がなければならず、共同の想像力は、民衆がおたがいに模倣する欲求があることによって可能であろう。個人が自分自身を模倣することによってつくられるのが習慣(ハビット)で、人間同士がおたがいに模倣しあうことによって存続されるのが慣習(カスタム)だという考え方がある。個人が一つの人格として、あるいは国家が一つの国家として存続するためには、模倣が必要だということになる。
このようにして、模倣の意義は、しだいに拡大されてきた。模倣に対して独創はどのような位置をしめるのか。とくに文学や芸術作品の価値がその独創性にあるといった分野では、このことは問題とされなければなるまい。芸術に関してはじめて模倣(ミメーシス)ということばを使ったのは、『国家』におけるプラトンであった。それは模写と訳したほうが適切で、プラトンはあまり積極的な意味を見出していない。アレクサンダー・ポープが、ローマの詩人ヴァージルについて、「彼は自然とホーマーとが同じものであることを知っていた」と書いた時、それは自然とホーマーの詩とを同じ重さをもったものとして見ようとしたのであり、模倣の意義をはるかに強調している。芸術作品が、たんに自然や現実の模写ではなく、それ自身の形式と秩序を持った創造だという考えが見られるからである。十八世紀以降、リアリズムによる小説が盛んになるにつれ、模倣はたんなる模写から、表現という問題に進み、その意義が深められていく。
(利沢 行夫 文芸評論家)
人づくりは、リーダーである「模範モデル」を積極的に個性をもって学び、同化模倣し、そして、その次に自分らしさを表現していこう。自己対象化の意味である。模倣は個体の物象化によって個別的に創造へ向かう。それは模倣の本来の意味でもある。
経験、体験、知識などの違いは新しい創造へのエネルギーだ。
優れた人を学ぶ意味である。そして、助け合い、支え合っていこう。
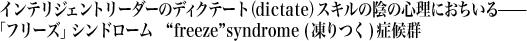
談話によって原稿を作成するにはいくつかの方法がある。
談話を録音してトランスクライブ(transcribe 録音再生)して原稿をつくる方法と、ディクテーション(dictation)による談話筆記原稿をつくる方法である。
日本語にはディクテートという意味のことばはない。
森 鴎外は『高瀬舟』で「同心が罪人の口供を口書した」情景を描いた。わが国においても作家の病気のとき、病室で使われていたこともあるようだ。
16世紀の欧米においてディクテーションが貴族の間に広がったといわれる。
そのディクテート(dictate 口で言って書き取らせる)の談話筆記がメディアの発達とともに広がっていった。一人で録音機のマイクの前に向かって電子音声原稿をつくり、出版社にカセットテープや音声ファイルで入稿するときにも使われている。
ある先生は口述録音をして電子原稿をつくり、自ら句読点まで指定して口述され文章をつくっている。
放送ジャーナリストである、ある先生は最新のディクテーションシステムを事務所にもち、先生の談話側(dictator)コンピュータと、横に並べてトランスクライバー(transcriber)=談話筆記者が筆記するコンピュータと共通のコンピュータ画面がLANでつながって、トランスクライバーのディクテの過程(ディクテーション dictation 談話筆記原稿)を見て文字やディクション(diction 語句の使い方)や句読点などを確認(推敲、対象化)しながら、そのディクテの速さに合わせてスピーキングスピードを調整しつつ談話筆記(同時に文字化)し、原稿はそのまま出版社に入稿される。
このディクテーションはトランスクライバーと気持ちを合わせて談話筆記していく。
ディクテーター(談話者)の思考過程であるスピーキングスピードにトランスクライバーはディクテーションスピード(リズム)を合わせる。政治や軍事、経済、文化などの専門知識、知性に基づく技術など秘書的な気持ちが合う相性が必要になる。トランスクライバーとしてコンピテンシー(業務達成能力)が必要で、口授が行われている同時筆記の最中に、漢字や表記上の変換ミスを繰り返してしまうとディクテーターの思考回路からセンテンス、ディクション、ことばが一瞬「蒸発」してしまうこともある。
談話で同時に文字化していく生のディクテーションと録音によるトランスクライビィング(transcribing)の違いはトランスクリプション(録音再生原稿)においては誤記につながるが、しかし、反対に、生のディクテーションはなんとか続いていく。ディクテートによる原稿の作成は最大4時間ぐらいでインターバル(休憩)が欲しくなる。
放送ジャーナリストのディクテート技術は、テレビの海外取材番組のリポートのようにそれは語りの格調高いアナウンス原稿のように整然としている。
また、マス・コミュニケーションではインタビューなどで原稿がつくられている。第一稿のトランスクリプションをつくるトランスクライバーの日常の仕事(ディクテの仕事場)風景である。
ビジネスの場において話すことや会話(対談)など、話すときは、「だれに向かって、何のために、何を、どのようなことばを使って、どんなふうに話すか」(『国語表現法』佐藤喜代治先生 朝倉書店 昭和47年)
改めて話すということを、佐藤喜代治先生のご研究を参考に考えてみると、話し相手に対して、生身の口語で適当に身振りなどしながら表情をもって話の内容や雰囲気(プロソディー)を出し、その場の空気をつくっていく。話し相手にニュアンスが伝わる。
ぼくたちは日常、談話を録音再生(transcribe)して聞いている。そして、録音の明瞭感は適切で良好だろうか。そのことばはどのようにニュアンスが伝わってくるか。
相手が不在で「ひとり(独り)言」のように話すことは不自然である。
誰もいないところで、一人で録音機のマイクに向かってディクテートするときの凍りつくような心理、それがどんなものかを考える。
最近では、ポッドキャスティングでホームページやブログその他などをつくるときにも利用されているようだ。録音(transcribe)と、ディクテート(口授)によって同時に文字化されるディクテーション(dictation)とは異なる。
聴衆を前にして話す講演などと違い、一人で録音機のマイクに向かう語りやディクテートは、活字のように振り返って読めない。独りよがりにならないよう気をつけるとしても、自分のディクテートを心配して「自己批評」し、自分の出来具合が気になって、あれこれ客観化して自分を責める。テープをプレイバックしようとする。
一般に談話筆記の「話すこと」と「書くこと」の関係は「ディクテーション教授法」の理論的土台になる。「話す」ことと、書くことの違いである。内容ではなく、形において「話す」ことへの真実が表現される。その自分の外化した現実の真実(事実)の公開への恐怖がある。
一般に談話筆記の録音を利用するとき、たとえばマイクをとった瞬間「大きな地震」が発生した時のように、こわばって気持ちが硬くなり凍りつく緊張した気持ち(心理)を、フリーズするという。
取材では編集者のことばを前提とし、したがって編集者のことを常に考慮に入れて話している。論理的に話される先生もおられるが、紙やコンピュータの画面に向かって、手でキーボーディングして書くこととは違う。インテリジェントリーダーと呼ばれる人のスキルは高い。
自作自演の一人制作のポッドキャスティングや語り、入稿など「読者」を想定するが、こうした話すときのバランス感覚が一瞬失われてしまい、また聞き手があって話が成立するので、そのあいづちも与えられない時、フリーズをおこしてしまう。それを“フリーズ”シンドローム “freeze”syndrome フリーズ症候群とよばれている。
こんな経験があなたにありませんか? 近年マスコミを中心にしてディクテーションスキルがインテリジェントリーダーに広がっている。
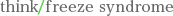
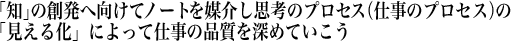
「ノート」の存在
ぼくたちのノートは、“「知」の創発の場”、“価値を生み出す場”であって、みなさんのお仕事を管理しようとするものではありません。知識労働者にとって、にじみ出てくる「知」の創出の場でもあり、「知」の仕事の活動の場です。管理と活動(運動)は全く別のものです。
「ノート」はアウトソーシングからは生まれにくく、編集者との響き合うパートナーシップから生まれる。新しい仕事の仕方から生まれる。「雇ってもいなく 雇われてもいない者同士が、一緒になって仕事をしていく」仕事の仕方から生まれ、編集者とのパートナーとしてのつながりから生まれる。
「ノート」は、自分の仕事の「弁明」を行う場ではありません。決まり文句になっていませんか。編集者のパートナーとして、適切なノートになっていますか?
行間から透けて見えるものを課題として「見える化」しようと試みるもので「見える化」とは、自らの自発的な知の創発への試みなのです。
「ノート」の形式
トランスクライバーの「ディクテ・ノート dicta-note」、コンポジョニストの「コンポージィング・ノート composing-note」、校正者の「校正ノート」などがある。
1992年(平成4年)、トランスクライビィングにおいて「ディクテ・ノート」が開発された年で、同年11月『ディクテーティング研究』(第3号)に発表された。それから、もう一つの主要な業務である旧「タイピング・ノート」へ拡がり、こんにちでは「コンポージィング・ノート」へと進化し、2000年(平成12年)夏、校正ミスの事故が発生、その改善策として校正作業のプロセスを「見える化」するため、同年秋、「プロセス校正」が導入された。
校正内容(小項目)をどのように網羅されているかは、ドウハウといえる。
編集者に校正者がどのように校正作業を進めたか、そのプロセスを「見える化」したものとして校正者の「校正ノート」の存在が重視された。校正ミスの歯止めを組み入れている。ぼくたちが編集者へ申し送りする発信の場です。
ぼくたちにとって「見える化」とは自分の仕事の達成能力(コンピテンシー)を外へ“さらけ出す”ことで、的確な指摘や知識の弱点などがともなって、その原稿に関する編集者との共同の課題について、考えたことや気づいたことをすべて伝えるノートでもあります。
ぼくたちは原稿と真剣に向き合っている。編集者との「共同の課題」について気づいたことをお伝えすることで、その仕事を通じて自分の成長も見えてくる。校正はどのように進めたか、自分の校正の能力を編集者へさらけ出すことでもあります。
「ノート」の働き(力)
編集者はノートを通して原稿のどこに「気づき」を持ったか、どこに課題として問題があったか、それらが正しく申し送りされているかを見ている。
誠意あるパートナーとして著者の原稿に対して「外からの意識」(ルカーチ)の意味と眼で、業務プロセスを「見える化」するとは、ノートを媒介として組み込んで、見えにくい仕事ぶり(達成度)を「見える化」したものである。何を考え、いかに考え、仕事をどのように進めたか、「見える化」されている。仕事(内容)の精度と密度がノートに現れてくる。
新人のあなたにもウェブオフィス(イントラネット)のe-ラーニングを通し、学習し、「開眼」する瞬間がある。先輩の同化模倣(ドイツフランクフルト学派の代表 マックス・ホルクハイマーの思想)を通し、1)知る・学ぶのステップ 2)やってみてわかる学習と訓練のステップ 3)私にもできる適用のステップ ここの基軸は同化模倣である。キャリアアップへのトランジッション(転換への局面)を獲得し、成長への転換点をつかむことができる。それは「守・破・離」(「形式-内容-分裂 Form−In・halt−Spal・tung」、内容の変容、形式と内容との闘争=筆者、植物の「形式」「形態」もまた不断に更新する内容と共に成長し、共に変化する カール・マンハイム著『歴史主義』未来社刊 1976年)へと発展していくだろう。
あなたの個性を尊重している。仕事に対し、自分のスタイルだって主張できる。それをみんなで学習し、自己適用(マンハイムの思想)していく。
「ノート」の目的――編集者と対話し、自分も成長する
繰り返しお仕事を進めていく毎日をP(計画)、D(実施)、C(見直し)、A(改善)のサークルを回して自分の仕事の進め方、気づきなどを広げ、深めていき、仕事の達成度を高めていく。それは自分が仕事を通じて人間的に成長していく過程なのである。
仕事ばかりでなく人生の見えなかったものも仕事を通して見えてくる。
これらノートと真剣に向き合っていくことが、自分の成長を「見える化」されてもいる。
そして、自分の書いたノートを自分が客観的に見れる時がある。自分の仕事の評価と自分の成長に気づくのだ。
こうしたことは仕事を管理することではない。ある人は内部統制によって管理しようとするかもしれない。ぼくたち知識労働者は、自己権力による自己統制によって自己の責任を仕事にこめる。自己実現を目指す。
あるときは編集者から担当者として指名される。重い責任と喜びが生まれる。「責任は達成されたか」と。
「仕事」を通じて何を考えたか、「仕事」の課題をどのように克服し達成できたか、知恵や知識を植え込めたか。「ノート」は輝くまで磨き込んでいるだろうか。編集者との信頼が建設(ビルディング)される。
仕事に対して仕事のプロセス、思考のプロセスを正しくノートの「見える化」によって向き合っていたかを、ノートを通じて編集者と対話し、編集者が評価できるようになっている。
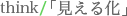

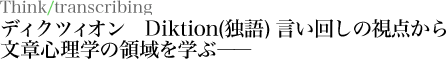
日本語で言い回しとは、「言いあらわし方、言いよう、ことば巧みに言う」(広辞苑)
ディクテの言い回しをドイツ語で、Diktion ディクツィオンというそうです。
ディクテのディクツィオンに聞き漏らしや聞き落としがないよう注意しましょう。
ぼくたちは書籍や週・月刊誌を執筆するための、元となるデータ原稿をつくっています。どのような含みがこの言葉の表現に含まれるのか? ディスコースの行間から聞こえてくるニュアンスを正しく編集者に伝えることの大きな意味について知らねばなりません。
このディクツィオンを常にトランスクライバーは心がけていることですね。
一般的に欧米語の論理性や規定性に対して日本人の使う日本語に対する特有の取り扱いが必要です。日本人は日本語で自分の気持ちや考えなどをどのように伝えているのでしょうか。ディクツィオンは談話(音声言語)のもつプロソディーと共鳴して意味を与えている。
トランスクライバーのトランスクライビィングで、「この意味も、こんなニュアンスも、こんな聞こえない声として」意味が含まれている豊かなディクテーションを心がけていますか? ディスコース(discourse 「音、音素」の結合が「語」として捉えられることばのこと)はプロソディーという衣装を身にまとっていますが、テキストは衣装を脱いで裸になってしまうときがあります。著者の生の声をいかに再現するか――ブレス(breath 息・音声学的気息音)をつかまえて、エナンシェーション(enunciation 発言振り、発音調)を再現していく。
言葉と言葉をつなぐ「言い回し Diktion ディクツィオン」には、その深さと奥行きをもっています。第一稿としてのデータ原稿に、その深さを伝えなければなりません。もちろん著者にとってもそのディクツィオンを正確に忠実に伝えられることが、コミュニケーションにとって大切なことです。
ディクテのテクノロジーは細かい、繊細な表現を聞き落とすことなく、聞き漏らすことなく、そのこころの言の葉の言い回し ディクツィオンを伝えましょう。
トランスクリプション(録音再生原稿)という十全な原文・荒文からライターさんが整文や成文、構成文をつくる「仕事のしやすさ」が純正な原文・荒文(素文)の精確(トランスクライビィング ウィズ プリッション transcribing with precision)なデータ原稿こそ求められているのだと思います。
そうして編集者のコンフィデンス ビルディング(confidence building 信頼を創る)のトランスクリプション(録音再生原稿)でなければなりません。
わが国には文章心理学という国語学の一分野がある。ディクテーションのニュービジネスへの適用は出版社の編集工程に吸収されて解放(止揚)され、そして佐藤のディクテーション学は国語学のひとつに吸収されて解放(止揚)されることを望んでいる。ディクテーション研究はわが国国語研究者たちの地平へとバトンタッチをされていくように望んでいます。
文章心理学
【原義】この用語はどうも日本的な意味が大きく、それだけにわれわれには明治以来親しんできた概念が伴う。したがってこれに適当する外国語はないようだ。言ってみれば「文章を話し書くうえでのすべての心理的現象を取り扱う学」というほかない。また「文章」という日本語が「文」というもう一つの言葉と違うこともあわせ考えなければならないのだ。
【類語】言語心理学・創作心理学・文体論・文体美学・言語学・コミュニケーション論・修辞学(新旧のレトリック)
【発展】すでに述べたように「文章」という昔の概念が大正末ぐらいから復活したことは、一つにはドイツ文芸学や心理学、とくに実験心理学の発達により、また一面は日本における「国語教育」の信念にもよる。
さらに重要なものとしてレトリックのほか、ヴント、ディルタイ、バイイらの言語観や文体観も一役買っていた。こうして「話」と「言」のほか「話者」と「聴者」の文の構成における創作性と社会性がとくに取り上げられて論ぜられる。
最近になると修辞学の概念が復活し、新しいレトリックというものが力説され、またその方法もいちだんと分析的になってくる。
しかし文学作品をとり扱う場合には心理学的解釈だけでは「文学性」「美性」がにげてしまうので、これを文体美学が少し哲学的に援助してくれる。
全般的にみると文章心理学の扱う領域は最近に及んでいちだんと分岐し、本来理性的認識から出発しながらもさらに感性的認識を重視して、ここで今日の視聴覚教育への貢献も見落としてはならない。
【解説】この方面では心理学の影響がもっとも大きいが、早くはオグデンとリチャーズの「意味の意味」とかアメリカ「新批評」のK・バーグの「動機のレトリック」、ハヤカワの「思考と行動における言語」も忘れるべくもないが、最近は言語批判的な立場からの研究もあること、ペレルマンの「討議の学としてのレトリック」も掲げておこう。こうして文章心理学は実用的な価値を発揮していて、とくに民主主義教育の基盤に触れてきている。
【文献】この方面の研究はまず領域が広大であるだけに方法論もいろいろある。早くは城戸幡太郎・矢田部達郎・吉田精一・小林英夫らの諸氏がこの方面に関心をもち、波多野完治『最近の文章心理学』6巻にわたる大切な寄与がある。ほかに同著者の『文章心理学入門』『実用文の書き方』などもある。(鍋島 能弘)
(本稿は平成18年2月13日「営業情報」に投稿され、修正・加筆しました)

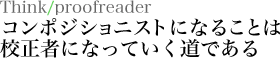
本 コンポジショニストのみなさんもお気づきだと思いますが、「キャリア開発のステップ」をスケッチしたものとして、コンポジショニストから校正者への道のりを描いています。
校正者のコンピテンシー(業務達成能力)をどのように身についていくか、それはコンポージィングから、つまりhand writing script(手書き原稿)の清書(manuscript)のワードプロセッシングを通してコンポジショニストになり、校正の入った「校正ゲラ」を自分で見て読んで、直し・修正の作業を重ねて、そして、何度も校正ゲラを見たり読み直したり、それを繰り返して、その道の行き着くところが校正者への道程だと思います。こうして校正者への人づくりに入ります。
メディアミックス&ソフトノミックス/は、そうした「学校」でありたいと思っています。
戦後教育の主要な流れは、中間管理職への養成の道を描くことでしたが、「口で言って」教えなければ、「わたしは、教えてもらっていない」と言う人が多くいたと思います。
子どもに母の働く背中を見せることは、口で言って教えることではありません。
「見て学ぶ」ことの深い意味について知らない人が多いようです。
モノづくりの職人は黙ってやって見せて教える――そうした仕事の場(学習の場)がメディアミックス&ソフトノミックス/の「学校」といえます。webでいろいろな原稿を見て学んでいくのです。
校正に失敗しないために、「プロセス校正」の道を開発してきました。人間だから間違いもあるということに対して、間違いをおこさないためにはどうしたらいいか、それがプロセス校正への始まりでした。
そして、メディアミックス&ソフトノミックス/は個性ある校正者を育成してきました。
起業したい人もいるし、わたしは何々になりたい人もいます。しかし、失敗は計算に入っておりません。失敗したら大変なことになるかもしれません。それを失敗のないように慎重に自己の自分で歯止めをもったコンピテンシー(職務達成能力)として獲得していく校正者への道のスタートがコンポージィングといえます。基礎をしっかり学び、編集の基本を学ぶことへ発展させ、文字を取り扱う心構えについて学び、「ほかの人みんなはどうしてこうした技術を獲得したのだろう」と、その鏡となった「校正済ゲラの直し・修正」をじっと見つめることから、「黙する校正済ゲラ」の用紙からその多弁が聞こえてこなければなりません。
「初校や再校の直し・修正」の入朱の校正ゲラをミスなく、精確に「デジタルテキストへ変換・修正」を完了して、初校や再校を「立て」る。それを繰り返して訓練していくのです。
それにはまず、みんなと同じように仕事の模倣から始まります。すべてにおいて模倣から出発します。そして、同化することにより仕事の模倣を通じて本当の自分(技能者)になっていくのです。こうした同化模倣を通じて仕事の順序を追って校正の形式(初校、再校)を立てることが、人づくりの始まりとなっていき、仕事への考え方、仕事への姿勢など、校正者を目指す「校正者」としての自分の仕事への理念が生まれてきます。
アメリカ人はアメリカ人になる。アラブ人はアラブ人になり、日本人は日本人になっていくのです。
そして自分は校正者になりたい。
コンテンツデータのワードプロセッシングからコンテンツデータの修正の「直し・修正点」(ゲラの見方、直しの意味の見分け方)の枠組み(仕事の範囲)を学び、つまり校正とはどういうことを校正というのか? それを学んでいきます。
こうして実践と座学(日本エディタースクールの通信校正講座)を経て、実践的な校正者に成長していきます。
人をつくっていくことは仕事を生み出していくことです。毎日の仕事を消化し、売上を拡大していくことにつながっていきます。仕事は常に入って出て行く。蓄積しているのはおカネではありません。校正の技術を蓄積していくのです。
メディアミックス&ソフトノミックス/では、座学を日本エディタースクールの通信校正講座で学び、実践は毎日の出版・書籍原稿のお仕事を消化して、そこから貪欲に仕事を学んでいきます。
世代は次の新しい世代へと巡り巡って行く。
(本稿は平成18年2月13日「営業情報」に投稿され、修正・加筆しました)
|