|
ディクテーテット アイデンティティ dictated identity を求めて――。
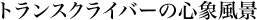
仕事に名前がある、仕事に形式があるということは、仕事を演じるということです。
――トランスクライバーという役がらを演じる、専門性という役がらを自分の中につくって行く。そう演じる「私は誰か?」と自らを問う時、内なる自己の内面へ降りていく。
「私は誰か?」わからない。私を見つける契機がここにある。私は今、私の心の中に降りていく。
この自分――いろいろな性質を抜きがたくもってこの世に生み出され、そして今日までさまざまな体験を重ねながら、十数年という生活を送ってきた現在の私がトランスクライバーという役を演じるということ、それが自分のテーマとして今自己の中にあります。その意味でトランスクライバーとして仕事をする自分自身をはっきりと自覚すると同時に、いい仕事をするためにはまず最初に、自分の欠陥を発見して仕事を通して意識的になおしてゆく、仕事へ向かう時、心を「空」(から)にする自己訓練を通して、平常の日常性の中へ、心を空(くう)の状態へ持っていき、そうしてはじめて、トランスクライバーの専門性をつくり上げる自己形成の土台づくりにやっと入ることができるわけです。
しかし、多くの人が考えるように、トランスクライバーは「耳」から音を聴いています。書き取っていく専門性の「耳」は確かにこの一面を持っています。この一面だけを取ってみれば、トランスクライビング―― Transcribing ―― の本質的側面ということができます。ここでは「耳」で聴くのではなく「心」で聴き取る――即ちディクテーティング―― dictating ―― の本質的側面を述べています。「心」で聴くとはどういうことを言うのでしょうか?「心」を「空」(から)にするということです。「空」(から)にした心をもう一人の自分が見ている。この状態を「心」の「空」(くう)といいます。
人間は誰しも、自分のなかにいくつかの“歪み”をもっています。それは幼児のころからもっていたものであったり、環境によって後に芽ばえたものであったりもしますが、人の話を良く聴く性格に邪魔になるようなものが、いくつも自分のなかに棲みついています。
ディクテーターのディクテートを聴き取りその全的な表現をディクテするとき、私の知識や語彙、能力や思考の飛躍、また想像力をもって、ディクテーターの思考や思考回路をくぐり抜け、彼の深淵な心の中に入り込んでいく。
自分のもの以外の概念像や表象をディクテーティングによってディクテーターの心象を描こうとするとき、自分のなかでそれを妨げるような性格やディクテートされる世界に屈折した自分の反射がもしあったとしたら、そしてトランスクライバーの知識や能力と乖離(かいり)したディクテートの内容なども、また誠実なディクテーティングを進めていく上で自分の心象と対立的なディクテートも、テープディクテーションの本質的内容をトランスクライバーがはっきりつかみとっていく鏡映過程と平行的に分離状態になるというべきか、そうした時も、自己の中に厳しい心の風景を生み出していきます。
そうしたことが起こらないようにするために、まず最初に、自分の知的弱さ、専門性に対する勉強、日々生起する時事問題、バランス感覚、また調べて「ハメ」る能力、等々知的弱点を克服しながら、努力していく状態を自己の中につくり出していくことができるようになる。――それが、いわゆる“トランスクライバーたる自分の修行”であって、いちばん基礎的な生活と業務への態度になるわけです。
子どもの役に扮する役者は、子どもと供に遊ぶことから、ただ無心に遊ぶことから入っていって、今度は、意識的にしかも自然に、子どもになろうとする。子どもは比喩ですが、ディクテーションを行うトランスクライバーを演じるためには、ディクテーターと供に「遊ぶ」ことから、素直に「聴く」という聴観察――聴くことを通じて観察するだけでなく、トランスクライバーの心を空(から)にする、純粋な心の空しさを用意して、ディクテーターの心の中へ入っていく「無心に遊ぶことから入って」「意識的にしかも自然に子供になろうとする」――ディクテートの世界へ自然に意識的に入り、その世界を創造・共有していくことができるようになるわけです。
それは自分の銹(さ)びついていた思いこみや歪み――ディクテに対する心の不誠実、正直と対立する不正、その場の「つくろい」等に負けない、自然状態に戻すと言うべきか。それを自分の精神と身体で、ひとつひとつ納得していって、初めてわかってくるものをつかみ取ることができるようになるわけです。「つかみ取る」――仕事へ向かう自己の充実をつかみ取ることができるようになるわけです。
もちろん、そのような純粋な空しさが、貪婪なまでの耳からの観察と高度の知識で裏打ちされなければ、誠実で正確なディクテーティングにはならないわけです。そのためには広く深い知的体験をつむということも、非常に重要なことになってきます。
知的体験を多く持ち、要は、自分が直接体験したことのない知的領域の世界であるディクテであっても、想像力を駆使してそれを自分のものとしてトランスクライバーを演じられる能力があるとか、それを創り出せるように自分を訓練し得ていたかどうか、ということが重要になります。しなやかな知性を自身のなかに蓄積して、自己形成のための栄養にできる芽を自己の中につくり出していくことが大切です。
そうして、ひとつのディクテートの世界の中に没入している自分、一心にワープロの画面に向かってディクテしている自分を、もう一人の自分が自分を客観的にみつめ、自己批評することができる能力を養うということのほうが大切なのです。トランスクライバーはディクテートの世界とディクテする自己の世界を観察(鏡映)しつつ言葉に置きかえていきます。
自分に鏡映される言葉を探して一瞬のうちに自分をも観察し、そして次の瞬間、それほど心をしぼられる「苦悩のディクテ」のさなかにあってさえ、無意識のうちに自らを観察している自分というものがあります。それに耐えられない自分の淋しさを、ワープロ画面はつめたく記録していくのです。苦悩の走る瞬間を生きている。
人間の内部というものは、いつでも随意にあるいは不随意的に、始終、動いています。人間というものは「考えること」を「考えている」。そして日常の場合、これらが本能的におこなわれていて意識されていません。しかしトランスクライバーの場合は生活の基礎として、ワープロへ向かっている時も実人生においても、つねに二人の自分をもたなければならないと思います。観察し意識化し批評する自分が、行為する自分と、いつも一緒です。
単に自己を観察をするとか、生き方をただすとかいうことだけではないのです。トランスクライバーがディクテーションというものに対して、どれだけ深くかかわり、苦しみ、考えていくか、という意味での批評性ということになります。何をどう考え、いかに見るか、どこまで深く見てとれるか、結局、深い目をもつためには深い人間性ということが問題になってくる。トランスクライバーの役を演ずるということの意味です。
もちろん耳を傾けることだけでなく、耳で良く聴き、良く観るのです。観えてくる世界を心で見ながら、ワープロ画面に目をこらしていきます。音声学的なるもの――音を耳で聴き自分で心象し自分の心象的空間の中に、音の音声学的特徴を位置づけ、自己の中に普遍的な音の像をつかみ取っていく。聞くのではなく聴き込んで、ほんとうに余念なく耳を傾ける。この時「心」でもし聴き取ることができたとしたら、心の「空」たる天(てん)から舞い降りて、言葉をつかみ取ることが一発でできるのです。
トランスクライバーの耳と普通の人の耳とは明らかに「聴き取る」力が異なっています。専門性の「耳」を自分のものとして訓練していくには半年はかかります。聴き取る訓練された「耳」です。しかしです、トランスクライバーの「耳」に認音した音と、音の音声学的言葉と、認識と対立する音に、より神経質なほど自分の中ではっきりと区別できるようになります。
その区別――機器(マシン性)的音、音声学的音、DI不能の音――との間で、口授の同等性とラキューナを正しく認識し、正しくキータッチしなければなりません。心の不誠実、自己の正直と対立する「いつわり」に、もう一人の自分は正しく向かい合っています。この「いつわり」が自分の中に棲みついているうちはけっして自己実現はできないのです。このことが、自分でわからない、認知できないということは能力にかかわってきます。
いま、ディクテーターの声を聴いていますが、あなたの仕事先であるディクテーターがトランスクリプションを必ずチェックするのです。トランスクライバーは誰に向かって仕事をしているのでしょうか。
ディクテーターは、あなたにまた仕事を出してくれるのでしょうか。――トランスクライバーのあなたが一番良くそれを知っているのです。正しく仕事に向かう姿勢へのきびしさをここでは――仕事の恐さ――と言えると思います。耳が聴こえるようになればなるほど仕事の恐ろしさが自覚されるのです。仕事に向かう専門性とは自己への限りない誠実を通して実現されるのです。口授の同等性は品質保証そのものです。仕事へ向き合う私は神の命令に従い心を空(くう)にする。そして、仕事が叫んでいる「仕事がこうしてもらいたい、という命令」をこなしていく。仕事はトランスクライバーに何をやってもらいたいか叫んでいる、神の命令に従って、もう一人の私に従ってそれを行う、ここに私の個人的な理由(わけ)は一切ない。
かつて、(株)メディアミックスでは、経験者、未経験者を問わず採用を考えていました。しかし、現実のステノグラハー(速記者)やテープおこしの経験者の仕事、速記原稿やテープおこし原稿は実にひどい品質でした。不誠実で不正で「いつわり」の多いものでした。待遇も悪く当然だと思いますが、こうした人格は、赤い色を真っ白にする努力以上に矯正することがむづかしいのです。矯正とは訓練して直して行くことです。
(株)メディアミックスでは、いわゆる経験者を採用しておりません。皆さんがつくり上げたトランスクリプションはいろいろあるにせよ、まあ 誠実な原稿なのです。当然といえば当然です。ガーブルド――勝手に選(え)り抜く、文章を勝手に改める――することは、仕事とは何か――に立ち向かう正しい姿勢と対立的な人格的性癖で、それを矯正することは困難なことです。トランスクリプションに手を加えてはならないのです。リライトなど、トランスクライバーは絶対してはなりません。録音取材テープと同一物であることを証明するのが、証明する仕事をトランスクライビングといいます。「証拠」を自ら失う仕事をすることは、自らのトランスクライバーという職業に対する裏切りです。証拠をつくる仕事を正しく誠実に行いディクテーターのディクテートを正しく再現し、そして、ライターという職業の人が、そのトランスクリプションに従い、ディクテーターが認知する範囲でゴーストライティングがゆるされるのです。トランスクライバーはディクテートされた内容と同一物であるもの――サブジェクト アイデンティファイリングを確立する仕事をしているのです。これを守ることが、訴訟問題、トラブルから身を守る専門性の条件なのです。
形式は内容である――形から入って心に至る――世阿弥の芸術から、仕事とは何かを学ぶことができるわけです。順や形式をみだすこと、無視することをメチャクチャといいます。糸川英夫先生の人間の生活を快適にしてきた「途中省略システム」と芸術は水と油です。芸術は途中省略しません。芸術的昇華を求めて、自己実現(神の命令)するのです。途中省略は産業廃棄物を生み出すのです。
かくて、これらは上記の“歪み”とは異なったものです。仕事に対する考え方や方法が人格的に異なるからです。
こうした異質なものを取り除いた心象の風景として、自然に、自由に、歌うように行為する自分と、それをみつめる自分を素直に表現する世界がいま共有されるのです。ここをしっかり考え、自分をみつめて、こうしてディクテーターの内的意味がきちんと聴きとれれば、表現(記)をつくり出すことができます。俳優や音楽家が台本通り「せりふ」や「楽譜」を口にして、その「せりふ」や音楽を聴き込んで、それを受けて内的世界に入り、自分の生きた「せりふ」が出てくるように、ディクテーターの「せりふ」をトランスクライバーは活きた表記としてそれを具象しなければなりません。――それを求めていくのです。ワープロの画面に文字化した音の像は二つに分裂するときがあります。同音異語はハッとして異なった言葉の世界を私に教える。
また、よく「ディクテート内容の耳で聴く」といいます。一瞬、DI不能の言葉も聴き取ることができるわけです。そのディクテートに耳を傾けるとき、自分はディクテーターとの共感を自分のものとして、ディクテしています。ディクテートの世界へ入り込み、描かれてゆく世界を共有しながら、ある時は記者の耳で、自分以外のディクテーターの耳で聞き込んでいる。描かれてゆく人物像であれ、対象物であれ、概念の世界であれ、受け方や感じ方を共有してゆく。苦悩や自分との対立現象が生まれたとしても、専門性と商業性の両面を持った事由からそれを乗り越えてディクテして行きます。「耳」で聴いたトランスクライビングと「心」で聴いたディクテーティングの喜びは喜びとして、共感は共感として、トランスクリプションにこの二つの相違があってはなりません。それを専門性といいます。――つまりプロなのです。素直な「心」の置き方、向い方は平常そのものです。力が入ったり、パワーになったり、エネルギーになったりと平坦な言葉の道のりであったりします。
静は動へ舞うときがあります。こうしてやがて、ディクテしている私はマッハ5の音速で現実の私にかえり、私の中に「空」を私は見ている。反射して屈折する思考の光は、縦横に飛び散り、夜も昼も自分の周りの世界が沈黙する中で、フォネティックディスコースの音は、言葉となってディクテートの世界を表現し通りすぎてゆく。ディクテーターのディスコースの香りやひびき、スタイルやにおい、など、言葉の音感覚は言葉の表情を身体(からだ)に受けて、私の肉体に同化して中身が伝わる。トランスクライバーの私は自分の身体(からだ)一杯に言葉を転がし、言葉の音色は、鳴りさけび、うなり、きしんで、いるときもある。再び言葉はうなり、こすって、はねて、震える、はじけたり、廻ったりしながら、言葉は泣きさけぶ、心にしみながら、音色の宇宙に私を見ている。次から次へと聴き取りながら、活字に置き換え、そして移し変えて目的に向って繰り返して進む。
私の知(愛)は夢みる力をもって言葉を、音声を大切にしながらワープロの画面と身体で覚える聴感覚をフットペタルを踏みながら……、続いていく。私の心に伝えられた緊密で緊張する時間を共有する――。この自分の身体(からだ)を通じて外へ表現していく。
もう一人の私に響く音色と間(ま)は、静かに訴えているかのように聞こえる。私に力がこみ上げてきて、共感していることに私は気付く。心が洗われる。心に響く言葉をつつんで……。音楽的ですらある。間(ま)は私の緊張する力を抜き快感に上昇する。言葉はリズムにのっているかのように……。言葉の時間と空間は芸術なのだ。この間(ま)が黙せる世界の象徴のように、人間の深淵な心と心の世界をつくっていくように思える。私と同じだ、という共感は私の自信と喜びをつくる。
――そしてそれらは、音声を主体化するということなのです。一つ一つの言葉を積み重ねて私はディクテしていく……。「考えること」を「考えている」だけにすぎない自分がいる。決して「我思うゆえに我在り」とは考えません。生命活動協働の場で私は生かされている。
そのことばの音色と呼吸が、ふっと私に間(ま)を持たせたり、間髪をいれずワープロのキーをタッチする。大空に音楽の調べをかなでるように……。ハッと受けとめて、そうだ、ここはどうしてもこうでなければだめなんだと、私の頭と身体とが強くそれを感じとっている。相手を批評しつつ、自分をも批評している。
こうして、「手法」は生まれるのです。独創はここから生まれるのです。
つまりディクテートを聴き込み、耳できいているときは、ディクテートの中にすっと入り込んで没入している。この場合、私の場である「ワープロ」におけるある集中が、確実におこなわれていて同時に、その集中によってもっていかれそうになる自分を引き離すような、ある拮抗する力がはたらく。集中という形で、表現の領域へ没入する自分と、それを対象化し批評する自分の精神と身体とが同時に成立している。
ここに全的な共感がワープロ画面に対象化――自分の考えや労働が外化(自分の外で、形になること)され協働という形で「共有」されるのです。生命活動の協働たる生産物――トランスクリプションは本来なら、この証明により、翻案権が成立するはずです。翻案権を今、主張する気はありませんが仮称「製造物責任法」と合わせて、トランスクライバーのコンフルージング ワード ペアス(confusing word pairs)――誤記の一文、混乱した一文――の存在は、簡単に翻案権を主張する意志を構成できるものではありません。この心象風景の中で描かれる世界は、仕事を私の身体(からだ)を通して形にしている哲学的証左なのです。出版社の深い理解と協働の成果を社会的認知という形にできるよう望むものです。ともあれ、仕事の喜びをここで歌っているのです。
この一文は岩波書店 岩波新書 山本安英先生「女優という仕事」の普遍的で、本質的な「女優」の心象を参考にしました。参考にあたり、岩波書店 新書編集部の山田女史に心のこもった「ご了解」を承り、ここに本題でプリントされました。
普遍性と特殊性の成果が生かされています。人間は同じだ! の風景を、こうした条件を越えて公開され、うれしく思います。
佐 藤
|